2025年度以降の共通テストでは、数学の出題範囲から整数問題が削除されることが発表されました。「整数がなくなると、今までの勉強法は使えないのでは?」と不安に感じている高校生も多いでしょう。
しかし、焦る必要はありません。重要なのは、基礎力と思考力をしっかり身につけ、変化する出題傾向に対応できる力を早めに育てることです。
本記事では、高校1年生から高3生までの学年別戦略を中心に、整数問題削除後でも共通テストで高得点を狙うための学習法や教材の活用法を徹底解説します。
※なお、この記事は以下の文部科学省の情報をもとにしています。
文部科学省「入学者選抜実施要項」
※2025年度以降の共通テストのポイントについて、以下の記事でくわしく解説しています。
2025年度からの大学入学共通テストのポイント:数学の整数がなくなる、社会の選択方法はどうなるかなど
共通テスト数学の新課程と出題範囲の理解
2025年度以降の共通テスト数学IA・IIBCの出題傾向
出題範囲の変更点と学習への影響
2025年度以降の共通テスト数学では、従来のIA・IIBの出題範囲が見直されます。特に整数分野が削除されることが大きな特徴です。これにより、従来の整数問題を解く練習に多くの時間を割いていた生徒は、学習戦略を変える必要があります。
- 影響1:学習時間の配分が変わる
整数問題の割合が減るため、関数・図形・確率・統計など、他の分野に時間を割くことが重要になります。 - 影響2:応用力の重要性が増す
整数問題は単純計算や論理的ステップが中心でしたが、削除後は複数分野を組み合わせた問題や思考力を問う問題が増えると予想されます。
整数問題の削除による試験構造の変化
整数問題がなくなることで、共通テスト数学の試験構造自体が変わります。
- 従来の特徴:計算力やパターン理解を問う短問中心
- 新課程の特徴:複合問題・文章題・データ活用型問題が増加
- 対策の必要性:単純な計算練習だけでなく、問題文の理解力・図やデータの読み取り力・思考の筋道を立てる力が重要になります。
整数問題が減ることで注目される分野
図形・関数の重要性
整数問題が減る分、図形・関数の理解力が試験で大きな差を生む分野となります。
- 関数:グラフの読み取り、変化の割合、最大最小問題など応用問題が増える
- 図形:面積や角度の計算だけでなく、空間図形や座標平面での応用力が問われる
- 学習のコツ:公式の丸暗記だけでなく、問題を自分で図示し、関係性を理解する練習が重要
確率・統計・データ活用の強化ポイント
共通テストではデータを読み解き、確率・統計を活用する問題の重要性が増します。
- 確率:順列・組み合わせ・条件付き確率など、複合問題が中心
- 統計・データ活用:表やグラフを読み解き、平均・中央値・分散を計算する問題が増加
- 学習のコツ:実生活のデータや例題を使って、読み解く練習を重ねることで得点力が伸びます
高校1~3年生が今から取り組むべき優先分野
学年別に優先度を整理すると以下の通りです:
- 高1:関数・基礎図形・基本確率の理解
- 高2:応用関数・空間図形・統計・データ活用問題の演習
- 高3:過去問演習、複合問題対応、思考力・読解力の強化
新課程対応で押さえておきたい公式・考え方
基礎公式の理解と応用力
基礎公式は単なる暗記ではなく応用できる力が重要です。
- 例:二次関数の平方完成は、最大最小問題や図形との組み合わせ問題でも活用
- 学習法:公式を使った問題を自分で作って解く、または複数の分野に応用する練習
思考力を伸ばす問題解法のコツ
- 問題文を読んだらまず図や表に整理する
- 小さなステップに分けて解く =論理的に考える習慣
- 公式や定理を当てはめるだけでなく、なぜその手順が必要かを考える
- 解き方のパターン化ではなく、思考の筋道を意識する練習を積む
☑ポイントまとめ
- 整数問題が削除されても、図形・関数・確率・統計が重要分野に
- 学年ごとに重点分野を分けて学習
- 基礎公式の理解と思考力を鍛えることが新課程対応の鍵
学年別の学習戦略とステップアップ法
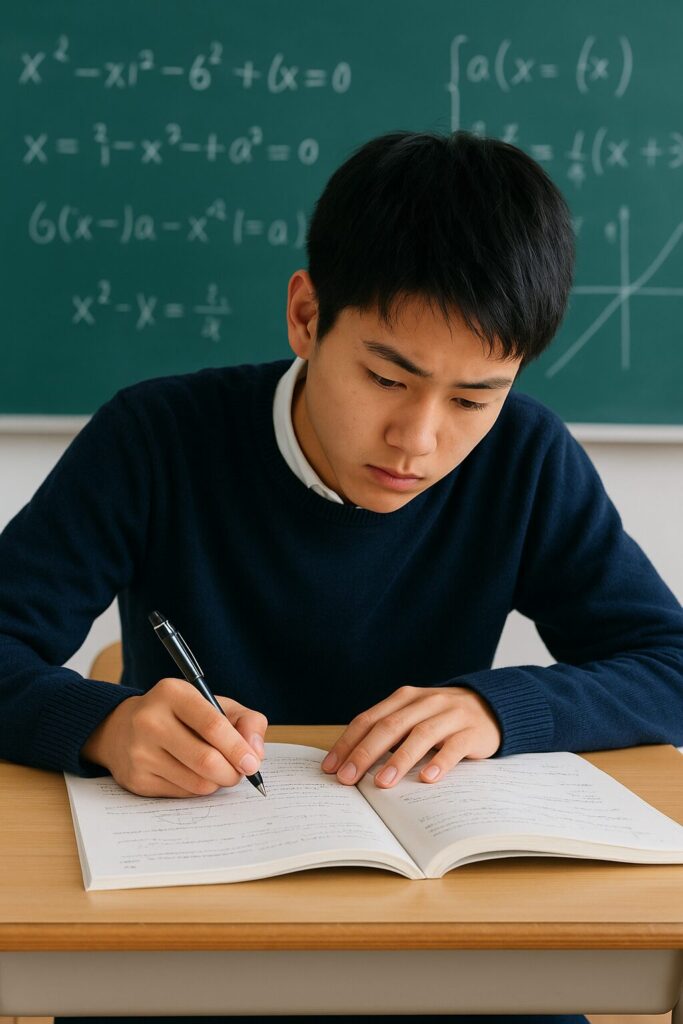
高校1年生向け|基礎固めと数学的思考力の養成
基礎計算・関数・図形の理解
- 目的:整数問題が削除されても数学の土台が揺るがないようにする
- 具体的学習内容:
- 計算力:四則演算、分数・小数の計算、式の簡略化
- 関数:一次関数・二次関数のグラフと式の関係を理解
- 図形:平面図形の面積・角度、簡単な立体図形の体積・表面積
- ポイント:公式を丸暗記せず、なぜその公式が使えるかを理解することが重要
思考力を鍛える演習問題の選び方
- おすすめ:
- 基礎問題→少しずつ応用問題へステップアップ
- グラフや図を自分で描きながら解く問題
- 問題文を整理して、論理の筋道を確認する演習
- コツ:短答だけでなく、自分の言葉で解答の理由を書く習慣をつける
日常学習で意識すべきポイント
- 1日10~20分でも計算練習や関数・図形の演習を継続
- わからない問題はすぐに解説を確認して理解
- 学んだ内容を友達や家族に説明することで理解が定着
高校2年生向け|共通テスト対応の応用力強化
典型問題演習と応用問題への挑戦
- 目的:共通テストで出題されやすい問題形式に慣れる
- 具体例:
- 関数の最大最小問題や複合図形問題
- 計算過程や論理的推論を重視した問題
- 学習のコツ:基礎を完璧にした上で、少し難しい問題に挑戦して応用力を養う
確率・統計・データ活用問題の攻略法
- 表・グラフを読み取り、平均・分散・確率を計算する演習
- 条件付き確率や組み合わせ問題をステップごとに整理して解く
- 過去問や模試を活用し、文章題やデータ型問題に慣れる
応用力を高める教材と参考書の活用
- 高2向けの応用問題集や共通テスト対策問題集を利用
- 問題を解くだけでなく、解法のパターンや考え方をまとめるノート作成
- 教材例:
- 「共通テスト対応 数学IA・IIB 典型問題集」
- 「図形・関数・確率をまとめた応用演習書」
高校3年生向け|過去問演習と新傾向問題への対応
共通テスト過去問の効果的な活用法
- 過去問は時間を測って本番形式で解く
- 解いた後は間違いの原因を分析して弱点を補強
- 過去問だけでなく、予備校の模試問題も活用して幅広い出題傾向に対応
整数問題削除後の出題傾向に対応する演習
- 文章題や複合分野問題(図形×関数、確率×統計)に慣れる
- 計算だけでなく、読解力・思考力を問う問題の解き方を身につける
- 問題を図や表に整理する癖をつけることで得点力が向上
二次試験・私大入試に向けた数学力の総仕上げ
- 共通テスト対策で身につけた基礎と応用力を二次試験レベルに応用
- 公式や定理の使い方を再確認し、複雑な問題も段階的に解く練習
- 過去問や予想問題で総合演習し、本番での時間配分や解答戦略を確認
☑ポイントまとめ
- 高1:基礎固め+思考力養成
- 高2:応用力強化+典型問題演習
- 高3:過去問演習+新傾向問題対応+総仕上げ
- 学年に応じてステップアップし、整数問題がなくても高得点を狙える学習習慣を構築
具体的な勉強法と教材の活用
※以下の河合塾の記事を参考にしています。
共通テスト受験生への教科別学習アドバイス(数学)
整数問題がなくても数学力を伸ばす方法
思考プロセス重視の学習
整数問題がなくなることで、単純計算だけでは得点が伸びにくくなります。
そのため、思考プロセスを意識した学習が重要です。
- 問題文の整理:文章題や複合問題は、まず図や表に整理する
- ステップ分解:1つの問題を複数のステップに分けて考える
- 理由の明確化:なぜその公式や定理を使うのか、解答の根拠を自分の言葉で書く
- 反復練習:同じ分野でも異なる問題形式で繰り返し練習することで応用力を定着
この方法を習慣化すると、整数問題の有無に関わらず考える力が伸び、応用問題に強くなるのが特徴です。
問題のパターン理解と応用練習
- パターン理解:よく出る問題形式や解法の流れを整理して覚える
- 例:関数の最大最小問題、確率の条件付き計算、図形の面積比問題
- 応用練習:単純に解法を暗記するだけでなく、異なる問題に応用できるかを試す
- 具体例:
- 同じ関数の問題でも、グラフ問題・文章題・図形結合問題で繰り返し練習
- 確率問題でも順列・組み合わせ・条件付き確率のバリエーションを解く
このアプローチにより、共通テストだけでなく二次試験にも対応できる力がつきます。
図形・確率・関数を強化するおすすめ教材
高校1~2年生向け基礎教材
- 基礎理解を固めるための教材が中心
- 例:関数・図形の基礎問題集、確率の入門書
- 使い方:
- 毎日10~20分、計算演習+図示練習
- 問題を解いた後に、公式の使い方や考え方をまとめる
高校2~3年生向け応用教材
- 応用力強化に特化した教材
- 複合問題や新傾向問題が多く掲載されているもの
- 使い方:
- 過去問や予備校の応用問題集を解く
- 自分の解法と他の解法を比較して思考プロセスを分析
共通テスト・二次試験両対応の問題集紹介
- 特徴:基礎~応用まで幅広く対応
- おすすめ教材例:
- 「共通テスト対応 数学IA・IIB 典型問題集」
- 「二次試験・私大入試対策 数学演習問題集」
- 活用法:
- 共通テストは時間を計って解き、解答スピードと正確性を確認
- 二次試験向けは複雑な問題をじっくり分析して、思考力を総合的に強化
※なお、高校数学のおすすめ問題集を以下の記事でくわしく解説しています。
高校数学のおすすめ問題集
効率的な学習スケジュール例
学年別・1か月単位の学習計画
- 高1:基礎固め重視
- 計算練習:週3~4回
- 関数・図形演習:週2~3回
- 文章題・応用問題:週1回
- 高2:応用力強化
- 典型問題演習:週3回
- 確率・統計演習:週2回
- 過去問や模試演習:週1回
- 高3:総仕上げ・過去問中心
- 共通テスト過去問:週2回
- 二次試験対応演習:週2回
- 弱点補強・復習:週3~4回
重点分野と演習配分の目安
- 図形・関数:全体の40%
- 確率・統計・データ活用:全体の30%
- 文章題・複合問題:全体の20%
- 計算練習・基礎演習:全体の10%
ポイントは、整数問題がなくなった分の時間を他の分野に振り分け、バランスよく学習することです。
☑まとめ
- 思考プロセス重視の学習とパターン理解で応用力を伸ばす
- 学年に合った教材選びで基礎~応用まで段階的に強化
- 1か月単位の学習計画と重点分野配分を意識して効率的に学習
将来の入試に向けた心構え
時間のある今だからこそ基礎力・思考力を積み上げる重要性
基礎理解の深め方
- 基礎の徹底が応用力の土台になる
整数問題が削除されても、関数・図形・確率・統計など他の分野で高得点を取るには、まず基礎を完璧にすることが不可欠です。 - 具体的な方法:
- 公式や定理を「暗記」するだけでなく、なぜそうなるかを考える
- 基礎問題を解いた後、似たタイプの応用問題に応用してみる
- 自分で問題を作って解くことで理解を定着させる
演習量とアウトプットのバランス
- 学習はインプットだけでなくアウトプットが重要
- インプット(授業や参考書での学習)+アウトプット(演習・問題演習)を組み合わせる
- 目安:
- 基礎学習:演習1に対して解説読解1
- 応用学習:演習2に対して解説読解1
- 反復練習で解答のスピードと正確性を高める
変化する出題傾向に柔軟に対応する学習習慣
定期的な自己チェックと弱点補強
- 学習効果を最大化するには自己チェックが必須
- 過去問や模試の結果を分析し、間違えた分野を明確化
- 間違えた問題は解法を確認し、類題を追加で演習
- 弱点分野は短期間で集中的に学習し、次回の演習で再確認
学年・学期ごとの到達目標設定
- 長期目標と短期目標を明確にする
- 高1:基礎理解と計算力の定着
- 高2:典型問題の演習と応用力強化
- 高3:過去問演習・新傾向問題対応・二次試験対策
- 目標設定のポイント:
- 月単位や学期単位で達成可能な目標を作る
- 達成度を可視化(チェックリスト・ノート管理)することで学習意欲が維持
現役塾講師からのアドバイス
公式情報の活用と信頼性の担保
- 文部科学省や大学入試センターの公式発表・ガイドラインを参照
- インターネットの情報だけでなく、信頼できる教材・模試データを基に学習計画を立てる
- 正確な情報に基づく学習で、無駄な勉強や不安を減らせる
実践的な学習法・モチベーション維持のコツ
- 勉強の習慣化:毎日少しずつ、継続的に学習する
- 演習+復習のサイクルを意識する
- 目標設定と達成感:小さな目標をクリアするたびに自信をつける
- 仲間との学習:友達と問題を出し合ったり、解説を教え合ったりすることで理解が深まる
まとめ|整数問題がなくても安心!共通テストで高得点を狙う学習法
学年別の戦略まとめ
- 高1:基礎固めと思考力養成
- 高2:応用力強化と典型問題演習
- 高3:過去問演習・新傾向問題対応・総仕上げ
今から始める基礎固めの重要性
- 整数問題が削除されても、基礎力があることで応用問題に対応可能
- 公式や定理を理解し、問題解法のプロセスを身につけることが得点アップにつながる
変化する共通テストに対応する長期戦略
- 長期的視点で計画的に学習
- 定期的な自己チェックと弱点補強
- 教材選びと演習のバランスを意識
- 学年に応じたステップアップで、整数問題削除後も高得点を狙える力を育てる
☑ポイントまとめ
- 基礎理解+思考力養成が高得点の鍵
- 学年別に計画的に学習し、弱点を定期的に補強
- 公式情報や専門家のアドバイスを活用し、信頼性の高い学習を継続
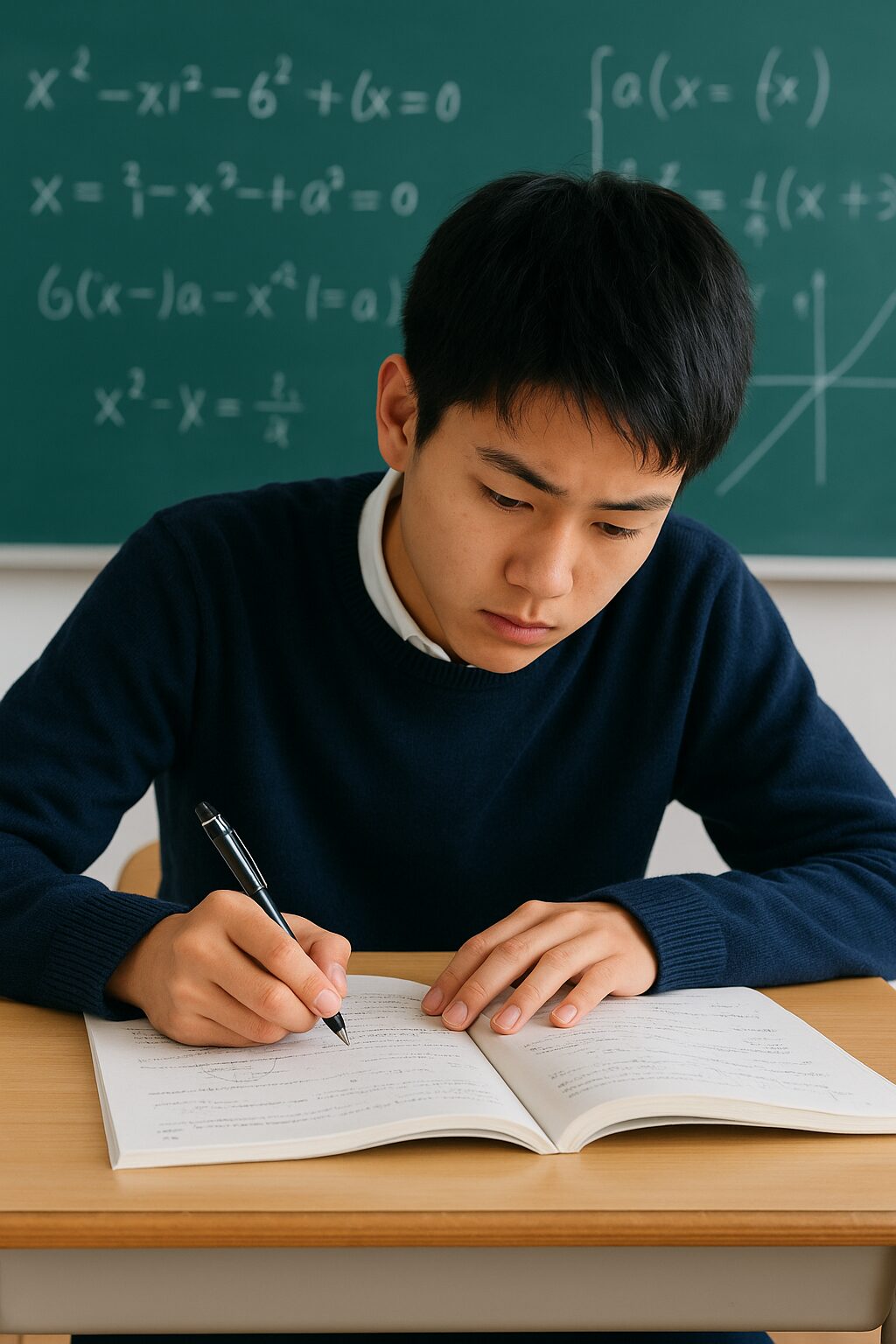

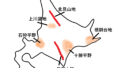
コメント