 中学生
中学生四大公害病とは?症状と発生場所を詳しく解説|中学生向け定期テスト・高校入試対策
四大公害病(水俣病・新潟水俣病・四日市ぜんそく・イタイイタイ病)の原因・症状・発生場所を地図も使ってわかりやすく解説!中学生の定期テストや高校入試対策に最適なポイントをまとめました。公害問題の歴史と環境政策の変化も詳しく紹介!この記事で中学社会のテストや高校入試対策はばっちりです!
 中学生
中学生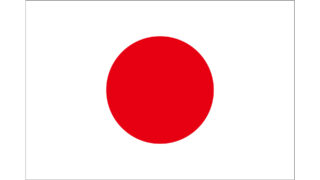 中学生
中学生 中学生
中学生 中学受験の勉強法
中学受験の勉強法 中学生
中学生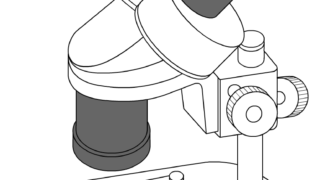 中学生
中学生 中学生
中学生 公立中高一貫入試
公立中高一貫入試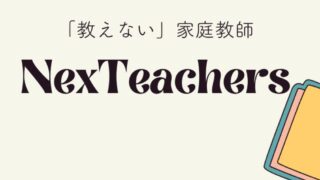 プロ家庭教師
プロ家庭教師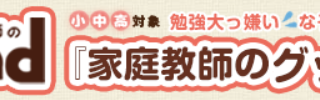 プロ家庭教師
プロ家庭教師