公立中高一貫校の受検では、学力だけでなく「思考力」「表現力」「意欲」など、総合的な人間力が求められます。
特に志望理由書や面接では、「自分の言葉で語れるか」が合否を左右する重要なポイント。
そしてもう一つ大切なのが、メンタル管理。小学生にとって大きな挑戦となる受検を乗り越えるには、親子での準備がカギを握ります。
この記事では、公立中高一貫校に合格するために必要な「志望理由書の書き方」「面接対策」「メンタルの整え方」を徹底解説。
さらに、親子で活用できる練習シートやチェックリストもご紹介します。
不安を自信に変え、合格に近づくための実践的なヒントをお届けします。
公立中高一貫校受検の概要と特徴
受検制度の特徴(適性検査・内申・面接)
公立中高一貫校は、「中学校」と「高校」の6年間を一貫して学ぶ仕組みの学校です。公立なので学費は比較的安く、かつ高校受験をせずに6年間のびのびと学べることから、毎年多くの児童が受検します。
文部科学省では、以下のように公立中高一貫の指導方針を定義しています。
中学校と高等学校の6年間を接続し,6年間の学校生活の中で計画的・継続的な教育課程を展開することにより,生徒の個性や創造性を伸ばすこと
中高一貫教育Q&A:趣旨・目的に関すること(文部科学省)より引用
受検方法は、私立中学とは異なり「学力試験(国語・算数などのペーパーテスト)」ではなく、「適性検査」「内申」「面接」などが総合的に評価されるのが最大の特徴です。
※なお、以下の記事で適性検査対策の問題集を紹介しています。
公立中高一貫校の問題集:適性検査や作文の対策におすすめの問題集
適性検査とは?
- 国語・算数・理科・社会の知識そのものではなく、「考える力」「読み取る力」「表現する力」を問う問題が出されます。
- 文章を読んで意見を書く、資料やグラフを読み取って自分の考えをまとめるなど、複合的な課題に対処する力が求められます。
- 計算が得意・漢字が書けるといった力よりも、「なぜそう考えたのか」を説明する力が重視されます。
内申(調査書)
- 小学校の通知表が反映されます。5年生・6年生の成績を使う学校が多いです。
- 主要教科だけでなく、「生活態度」「自主性」「係活動・クラブ活動への取り組み」なども評価されるため、日常の積み重ねが大切です。
面接
- 学校によっては個人面接や集団面接があります。
- 「なぜこの学校を志望したのか」「どんなことに頑張ってきたか」など、自分の言葉でしっかり話せることが求められます。
- 面接も「自分の考えを相手に伝える力」を見るための試験です。
ポイント:
- 「暗記」や「テストの点」よりも、「思考力」「表現力」「コミュニケーション力」が評価されます。
- 受検対策は長期的な取り組みが必要で、学校の成績や日々の生活態度も重要です。

私立中学との違いと保護者が知っておきたいポイント
公立中高一貫校と私立中学では、受検の目的や内容、学校の教育方針や環境が大きく異なります。
| 比較項目 | 公立中高一貫校 | 私立中学校 |
|---|---|---|
| 学費 | 安い(年間5~10万円程度) | 高い(年間70万円以上も) |
| 試験内容 | 適性検査(思考・表現力重視) | 教科試験(国・算・理・社)中心 |
| 面接 | あり(重視される学校も多い) | ないorあっても形式的 |
| 内申 | 重要(学校によって割合あり) | 基本的に関係なし |
| 教育方針 | 公教育をベースとした均等な教育 | 独自カリキュラム、大学進学重視 |
| 通学地域 | 学区内・都道府県内が中心 | 通学範囲が広い(越境あり) |
※なお、中学生・高校生向けの補助金について、以下の記事でくわしく解説しています。
私立中学や私立高校の学費無償化:授業料支援額や所得制限を解説(東京・大阪・神奈川・埼玉・千葉・兵庫)
公立中高一貫校の魅力
- 「教育の公正性」があり、家庭の経済状況に関わらず、優秀な子どもが学べる環境が整っている。
- 地元から通いやすく、公共交通での負担が少ない。
- 高校受験がない分、6年間を長期的な目線でじっくり学べる。
保護者が知っておくべきポイント
- 公立とはいえ、受検対策は高度。塾や家庭学習の支援が必須となるケースが多い。
- 私立のような「偏差値での勝負」ではなく、「総合力での勝負」になるため、志望動機や日々の生活態度が合否に直結する。
- 倍率が非常に高い(5~10倍超)学校もあり、早めの情報収集と準備がカギ。
志望理由書の書き方と面接対策
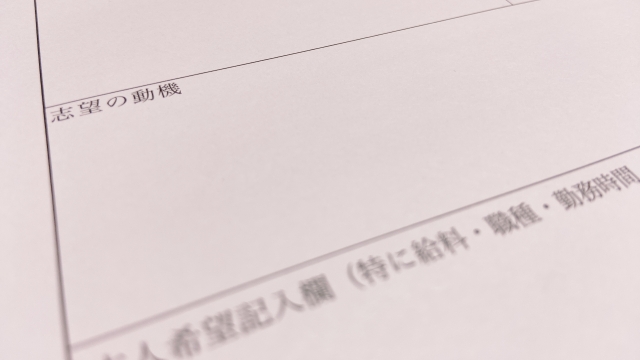
ここからは、文部科学省の指導方針をもとに、志望理由書の書き方や面接対策の仕方を解説します。
参考:中高一貫教育Q&A:趣旨・目的に関すること(文部科学省)
志望理由書の基本構成とよくある失敗例
志望理由書の基本構成(3つの柱)
志望理由書は、次の3つの流れで書くと自然で読みやすくなります。
- 志望動機(なぜこの学校か)
例:「調べ学習やグループ活動が多いと聞き、自分に合っていると感じたため」 - 自分の特長(どんな力があるか)
例:「自分の意見を文章でまとめるのが得意で、学級新聞をまとめた経験がある」 - 入学後の目標(どう成長したいか)
例:「調べ学習やディスカッションを通じて、多様な考え方を身につけたい」
よくある失敗例とその改善策
| 失敗例 | 改善ポイント |
|---|---|
| 「頭が良くなりたい」「有名だから」などの抽象的な理由 | 学校の特色(教育方針、カリキュラム)に具体的に触れる |
| 保護者が書いたような内容・表現 | 子どもの言葉で、実体験や感情を交えて書く |
| 「どこの学校にも当てはまるような内容」 | その学校ならではの活動や取り組みを挙げる |
アドバイス:「なぜその学校なのか」に答えるには、学校の説明会やパンフレットを親子で一緒に調べることが大切です。
印象を良くするための差別化ポイント
受検生が似たようなことを書く中で、印象に残る志望理由書にするには、「自分だけの体験やエピソード」を入れるのがコツです。
差別化につながる工夫
- 「自分の経験」×「学校の特徴」を組み合わせて書く
例:
「ぼくは学校新聞で地域の環境問題を調べ、記事を書きました。この学校では課題探究に力を入れていると知り、さらに学びを深めたいと思いました。」 - 自分の性格・強みを具体的に伝える
例:
「私は人前で話すのが苦手でしたが、児童会の司会を経験して克服しました。この経験を生かしてディスカッション活動にも挑戦したいです。」 - 学校の具体的な活動名を挙げる(パンフや説明会から)
例:「週に1度の探究タイム」「地域と連携した課題学習」など
アドバイス:「自分にしか書けない文章」を目指して、子ども自身の視点や感情を中心に構成しましょう。
面接でよく聞かれる質問と答え方のコツ
面接では、「志望理由」や「日常生活」について、自分の言葉で答える力が求められます。
よくある質問と意図
| 質問 | 見られているポイント |
|---|---|
| 「なぜこの学校を志望しましたか?」 | 動機の明確さ・学校理解 |
| 「最近頑張ったことは何ですか?」 | 継続力・取り組みの深さ |
| 「友達と意見が合わなかったとき、どうしますか?」 | 協調性・対話力 |
| 「この学校に入って何をしたいですか?」 | 将来の目標・意欲 |
答え方のコツ
- 「結論→理由→具体例」の順で答える 例:「探究活動が魅力だからです。私は調べてまとめることが好きで、地域のごみ問題をまとめたことがあります。」
- 長すぎず短すぎず、1分以内で簡潔に話す
- 背筋を伸ばして、笑顔でハキハキと(第一印象が大事!)
練習法: 家庭でロールプレイをしながら、保護者が質問→子どもが答える形式で繰り返すと慣れやすいです。
親子で準備したい「自己表現力」の育て方
公立中高一貫校の適性検査や面接では、「自分の意見を伝える力=自己表現力」が重要です。これは一朝一夕では身につかないので、日常の中でコツコツ育てていくことが大切です。
自己表現力を伸ばす家庭での工夫
- 日記や作文で「なぜそう思ったか」を書く習慣
→ 感想だけでなく「理由」をセットで考えるよう促す - 夕食中に「今日の出来事+感想」を話し合う
→ 家族で対話を増やすことが、言葉のアウトプット練習になる - 子どもに「説明させる」場面を意識的につくる
→ 「どうしてそれを選んだの?」「なぜ好きなの?」など
本番に向けた表現力トレーニング
- 録音・録画して自分の話し方をチェックする
→ 表情や話し方を自分で客観的に見て改善できる - 意見を言う前に「なぜそう思ったか?」を問う癖をつける
→ 適性検査の記述問題にも直結する力になります
アドバイス:「考えて→言葉にして→相手に伝える」練習は、家で親子で楽しみながら続けることが成功の鍵です。
合格するためのメンタル管理法
緊張・不安との向き合い方:小学生でもできるリラックス法
受検が近づくと、どんな子でも不安や緊張を感じます。大切なのは「感じないようにする」のではなく、「上手につきあうこと」です。
小学生でもできる!3つのリラックス法
- 深呼吸法(4秒吸って8秒吐く)
→「ふーっと長く吐く」ことが自律神経を整え、気持ちを落ち着けてくれます。 - イメージトレーニング
→「試験会場で自分が落ち着いて問題を解いている姿」をイメージする。脳が「大丈夫」と感じることで実力が出しやすくなります。 - お守りアイテムを持たせる
→ ハンカチや文房具など、「安心するもの」が1つあるだけで心が落ち着く子もいます。
親の声かけ例:
「ドキドキするのは真剣な証拠だよ。深呼吸してみようか」
モチベーションを保つ!家庭でできる声かけと環境づくり
長い受検勉強の中で、気分が乗らない日も当然あります。そのときに支えになるのが家庭での「声かけ」と「環境づくり」です。
効果的な声かけの例
- NG例:「なんでできないの?」「もっと集中して!」
- OK例:「昨日より頑張ってたね!」「この問題、あとちょっとだったね!」
ポイント:
「結果」より「努力」に注目する声かけが、子どものやる気を支えます。
家でできる環境づくり
- 集中できる学習スペースを整える(静かで、物が少ない机)
- リラックスタイムも大事にする(散歩やお風呂で気分転換)
- スケジュールに「休む日」も入れる(メリハリが大切)
プレッシャーに負けないメンタルはこう育てる
プレッシャーを跳ね返す力は、日々の「小さな成功体験」や「自己肯定感」から育ちます。
メンタルを強くする3つの習慣
- 失敗したときの言葉かけを変える
→ 「ダメだったね」ではなく「次はどうすればうまくいくかな?」と未来に目を向ける。 - 目標を「小さく」設定する
→ 例:「今日はこの1ページだけやる!」→達成できる → 自信につながる。 - 「頑張った自分」をほめる習慣
→ 子ども自身に「今日よかったこと3つ」を言わせるのも◎
親の関わり方:
「本番に強くなる」子は、「失敗しても大丈夫」と感じている子です。
受検直前の過ごし方とメンタルチェックリスト
直前期は勉強よりも「心のコンディション」が合否を左右することもあります。
受検直前の過ごし方
- 無理な詰め込みはNG! → 今までの復習を中心に
- 生活リズムを整える → 就寝・起床時間を本番に合わせる
- 「前日やることリスト」を親子でつくる → 荷物準備・持ち物確認
チェックリスト(前日~当日)
- よく寝ているか
- 食事はしっかりとれているか
- 「大丈夫」と言える雰囲気を家族が作れているか
- 自分で持ち物チェックができたか
- 試験会場までの行き方を確認してあるか
アドバイス: 最後に必要なのは「新しいこと」ではなく、「自分を信じること」です。
面接練習チェックリスト(保護者・お子さま用)
| チェック項目 | 内容 | チェック |
|---|---|---|
| あいさつができているか | はっきりと「よろしくお願いします」「ありがとうございました」が言えるか | □ |
| 声の大きさは適切か | 小さすぎず、大きすぎず、聞き取りやすい声か | □ |
| 姿勢が良いか | 背筋を伸ばし、足はそろえて座れているか | □ |
| 表情は明るいか | にこやかで自然な笑顔が出せているか | □ |
| 質問を聞いてから答えているか | 質問を途中で遮らず、聞き終えてから話し始めているか | □ |
| 質問に対して簡潔に答えているか | 長すぎず、話がまとまっているか(30秒〜1分程度) | □ |
| 自分の言葉で話しているか | 暗記ではなく、自分の考えで話しているか | □ |
| 「なぜ?」の質問に答えられるか | 「なぜこの学校を選んだの?」などの理由を説明できるか | □ |
| 好きなこと・得意なことを話せるか | 自分の興味や強みを伝えられるか | □ |
| 苦手なことや失敗から学んだことを話せるか | 弱みもポジティブに伝えられているか | □ |
親子で取り組む!面接&志望理由練習ワークシート
【ステップ1】自分のことをふり返ってみよう
| 質問 | 子どもの記入欄 | 保護者からのフィードバック欄 |
|---|---|---|
| 好きな教科とその理由は? | 例:理科。実験が楽しくて、身の回りのことがわかるから。 | |
| 苦手なことは何?どうがんばっている? | 例:漢字を覚えるのが苦手。毎日10分ずつ練習している。 | |
| 最近「がんばったな」と思うことは? | 例:学級委員をやって、話し合いでみんなの意見をまとめた。 | |
| 将来やってみたい仕事・夢は? | 例:生き物の研究者になって、環境を守る仕事をしたい。 |
【ステップ2】学校について考えてみよう
| 質問 | 子どもの記入欄 | 保護者からのフィードバック欄 |
|---|---|---|
| なぜこの学校に入りたいの? | 例:自分で調べて発表する授業があり、意見を伝える力をつけたい。 | |
| 学校に入ったらやってみたいことは? | 例:探究学習、理科クラブ、委員会活動など。 | |
| 自分のどんな力を学校で活かせそう? | 例:人の話を聞く力、まとめる力、あきらめない力など。 |
【ステップ3】よく聞かれる面接の質問にチャレンジ!
保護者が質問 → お子さんが答える → 内容や話し方について一緒にふり返りましょう。
| 質問 | 子どもの答え(練習用) | 保護者からのアドバイス・良かった点 |
|---|---|---|
| なぜこの学校を受けようと思いましたか? | ||
| 自分の長所と短所を教えてください。 | ||
| 最近読んだ本や印象に残ったニュースは? | ||
| グループで何かをしたときに大切だと思うことは? | ||
| この学校に入ったら、どんなことにチャレンジしたい? |
振り返りチェック(子ども用)
以下に〇か✕をつけてみよう。できなかったところは次の練習のときにがんばろう!
| 項目 | 〇 or ✕ |
|---|---|
| 声の大きさやスピードがちょうどよかった | 〇 / ✕ |
| 質問をちゃんと聞いてから答えた | 〇 / ✕ |
| 自分の言葉で考えて話せた | 〇 / ✕ |
| 笑顔で話せた | 〇 / ✕ |
| 前よりうまく話せたと感じた | 〇 / ✕ |
ワンポイントアドバイス(保護者の方へ)
- 否定せず「なるほど」「そう考えたんだね」と受け止める姿勢を大切に
- 間違っていても「自分で考えたこと」がいちばんの成長ポイント
- 録音や録画して一緒に見直すと客観的に振り返りができます
このワークシートは毎週1回など定期的に繰り返すことで、お子さまの「伝える力」「自己理解」がぐんと伸びます。
志望理由書のテンプレート(構成+記入例)
【構成】
- 志望動機(なぜこの学校に入りたいのか)
- この学校で学びたいこと・やってみたいこと
- 自分の長所・得意なこと
- 入学後にどのように学校生活に貢献できるか
【記入例】
志望動機
私は、〇〇中等教育学校の探究型の学びに興味をもちました。特に、自分で課題を見つけ、考え、発表する活動に力を入れていることを知り、自分の考えを深めたいと思いました。
学びたいこと・やってみたいこと
私は将来、環境問題について研究したいと考えています。この学校の理科の授業や総合学習を通して、身の回りの課題を調べ、解決方法を考える力を身につけたいです。また、科学部にも入りたいです。
自分の長所・得意なこと
私は、人の話をよく聞き、まとめるのが得意です。学校では学級委員をしていて、意見をまとめて発表することもあります。困っている友達がいたら声をかけるようにしています。
学校生活での取り組み姿勢
中学でも、自分の意見をはっきりと伝えながら、友達の意見にも耳を傾け、みんなが気持ちよく過ごせるようにしたいです。学校行事や委員会活動にも積極的に取り組みたいと思います。
※なお、中学受験の志望理由書について、以下の記事でくわしく解説しています。
中学受験の志望理由:志望動機の内容や書き方を親と子どもそれぞれに分けて解説します
まとめ:志望理由と心の準備が合格への鍵!
親子で乗り越える受検――成功の秘訣とは
中高一貫校受検は、子どもだけでなく親子の挑戦とも言えます。
成功する家庭に共通すること
- 子どもに自主性を持たせつつ、適度なサポートをしている
- 「がんばってるね」と日々の努力を認めている
- 志望校について親子で一緒に調べている
- 合否に関わらず成長を一緒に喜べる関係がある
▶ 一言アドバイス: 合格はゴールではなく、新しいスタート。その準備も一緒にしていきましょう。
本番で力を出し切るためにできること
試験当日は、準備してきた自分を信じるだけです。
本番で実力を出すためのポイント
- 前日は早めに寝て、朝はいつも通りの時間に起きる
- 会場で周囲が気になっても「自分のペース」を守る
- 問題が難しくても「できるところからやる」
- 「わからない=不合格」ではないと心得る
▶ 保護者の役割:
当日は「笑顔」で送り出すことが最大の支えです。



コメント