中高一貫校の中学生で、社会のテスト勉強に困っている子は多いです。
学校で使っている教科書に載っていない内容も普通にテストに出てきますし、市販問題集は公立中学生向けなのでなかなかピッタリなのが見つからない。
ですが、テスト勉強をしっかりしておくためにも、あるいはコースアップを狙うためにも社会は高得点を取っておきたい科目です。
そこで、私立中高一貫の中学生向けにテスト対策でおすすめの社会の参考書と問題集を紹介し、テスト勉強のコツをお伝えします。
※関連記事:私立中学生におすすめの数学の問題集
※関連記事:私立中高一貫生におすすめの英語の問題集
私立中高一貫の中学生におすすめの社会参考書と問題集4選
中高一貫生におすすめの社会の参考書と問題集を紹介します。
『自由自在』
まずおすすめなのが「自由自在」です。中学受験で使用された方もいらっしゃるのではないでしょうか。標準レベルから難関レベルまでカバーしている定番シリーズです。
このシリーズの良いところは「情報量が圧倒的に多い」という点です。中学生用は参考書と問題集に分かれており、合わせて900ページ以上あります。
学年別に冊子が分かれていないのも、中高一貫生にとって使いやすいポイントです。カリキュラム的に中2で習う予定のものが私立中だと中1の3学期などで出てきます。
テスト前になってあわてて次学年の問題集を買わずに済みます。
参考書↓
問題集↓
出版社:増進堂・受験研究社
特徴:
≪最新の教科書改訂版に対応≫
中学3年間の予習・復習・入試対策は、この1冊で!
がんばる中学生を応援して70年。
手に取ったその日から、高校入試まで使えます。【「自由自在」の“進化”は止まらない!】
Amazonより引用
・これからますます必要になる「思考力・記述力」を伸ばす問題も収録
・知りたいページを素早くLINEで確認できる「自由自在先生」機能
『最高水準問題集(特進)』(地理、歴史、公民)
つづいては、「最高水準問題集」シリーズです。こちらも難関校受験の定番です。
公立中学生向けの内容ですが、私立難関高を目指す人向けなので高校内容も一部含まれています。記述問題が多いのも特徴です。
網羅的な問題集ではなく、実践問題中心です。学校の教科書やプリントとセットで使うのがおすすめです。
国公立医学部に毎年2ケタ人数以上の合格者を輩出している中高一貫校なら、下記の「ハイレベル」のほうがおすすめです。
地理↓
歴史↓
公民↓
ハイレベル地理↓
ハイレベル歴史↓
出版社:文英堂
特徴:
実力をのばす2段階構成
各単元とも入試レベルの「標準問題」に加えて難しい「最高水準問題」の2段階構成になっており、確かな力を身につけることができます。■豊富な発展的内容
良問を厳選し、重要問題には「重要」マークを、とくに難しい問題には「難」マークをつけていますので、問題を解きながら出題の傾向とレベルをつかむことができます。■解答に役立つ情報を多数掲載
Amazonより引用
「標準問題」には学習内容の要点をまとめた「ガイド」を、「最高水準問題」には問題を解く糸口となる「解答の方針」を示しました。わからない問題に出合ったときも、自分で考えて解けるようにしています。
『新中学問題集』(地理、歴史、公民)
3冊目に紹介するのは「新中学問題集」シリーズです。個別指導塾で中学受験をされた方は、『新小学問題集 ステージⅠ/Ⅱ/Ⅲ』か『中学入試の攻略』という問題集をおそらく使われていると思います。
それと同じシリーズの中学生版です。
公立中学生向けですが難関高志望者向けなので、公立中の定期テストのレベルを越えた問題も多数出てきます。教科書に載っていない内容も一部掲載されています。
さらにこの問題集の良いところは、記述問題や思考力問題が豊富にあるという点です。
資料をみてその場で考えて解く問題も単元・時代ごとに載っており、私立中の定期テスト対策にも大いに役立ちます。
なお、地理、歴史は前半と後半で分かれています。
地理Ⅰ↓(世界の地理)
地理Ⅱ↓(日本の地理)
歴史Ⅰ↓(原始~安土桃山時代)
歴史Ⅱ↓(江戸時代~ラストまで)
公民↓(高校入試対策のページも多数含みます)
出版社:教育開発出版
『よくわかる高校歴史総合/地理総合』
高1向けの社会(地歴)の参考書です。高1では歴史と地理を広く・浅く学習するので、中高一貫中学生の勉強にも役立ちます。
資料を多めに掲載しており、カラーなので印象に残りやすいです。
地理↓
歴史↓
ちなみに、問題集編もあります。上記の参考書編だけで十分ですが、「予習もかねて勉強しておきたい!」という人には役立ちます。
地理問題集↓
歴史問題集↓
出版社:学研プラス
特徴:
■授業や教科書の理解をとことんサポート!
授業や教科書の内容をくわしく、ていねいに説明した参考書です。「定期テスト対策問題」を掲載しており、知識の確認だけでなく、テスト前に本番さながらのトレーニングをすることができます。基本の理解だけでなく、定着度のチェックや力だめしもしっかりできます。■オールカラー&図版・イラスト豊富で見やすい紙面!
重要な部分を色分けして強調したり、ポイントをまとめたりするなどの工夫がされているので、要点をしっかり効率よく勉強できます。文章の解説だけではわかりにくいところには、オールカラーの図解、イラスト、写真などを掲載し、理解をとことんサポートしています。■勉強のやり方もしっかりサポート!
Amazonより引用
巻頭特集の「よくわかる高校の勉強ガイド」では、高校3年間の勉強に欠かせない、大学入試を見すえた日々の勉強のコツや、勉強の悩みに関するQ&Aなどをわかりやすくまとめています。
選ぶ前に知っておきたい!良い社会問題集の選び方
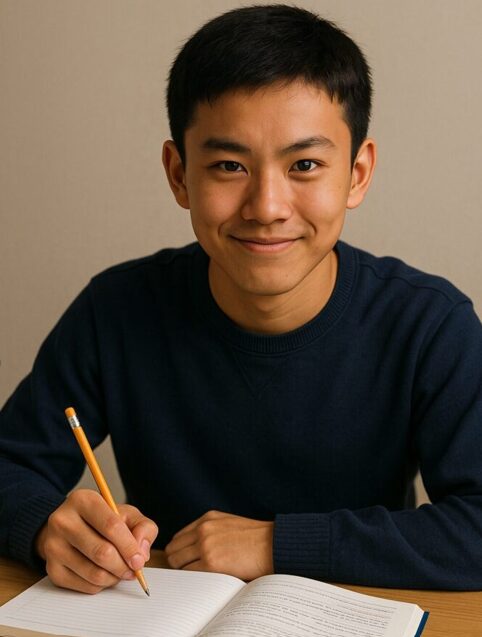
中高一貫校カリキュラムに対応しているか
私立中高一貫校では、公立中学校と異なり「先取り学習」が一般的です。中学2年生で中3内容を終え、高校内容に入る学校もあります。そのため、公立中向けの社会問題集では内容が物足りないことも多く、学習内容とのミスマッチが起きやすいのが現実です。
中高一貫生には、「中高一貫対応」や「体系的カリキュラム準拠」と書かれている問題集を選ぶのがおすすめです。特に、出版社が中高一貫校向け教材に定評のあるところ(教育開発、学研、文理など)であれば、安心です。
学校の授業進度とマッチしているか
社会は地理・歴史・公民と分野が多く、学校ごとに指導順序やペースが大きく異なります。授業でまだ扱っていない単元をいきなり問題集で解いても、理解が追いつかないため、テスト対策には不向きです。
そのため、購入前には必ず目次を確認し、自分の学校の進度と一致しているかどうかをチェックしましょう。できれば同じ教科書に準拠した問題集とハイレベル問題集を併用すると、授業とのリンクが強まり、定着しやすくなります。
演習量と解説のバランスが良いか
「とにかく問題量が多ければよい」と思いがちですが、解説が不十分だと理解が深まりません。特に社会では、「なぜその答えになるのか」を理解することが暗記につながります。
良い問題集は、
- 適度な問題数(1単元につき30~50問程度)
- 解答ページに詳しい解説(図・表・用語解説つき)
- 間違えやすいポイントへの注釈
などがそろっています。「解いて終わり」にならず、「解いて理解する」ための構成かどうかが重要です。
定期テスト対策用・入試対策用の違いを理解する
社会の問題集には大きく分けて、
- 「定期テスト対策用」:単元ごとの確認・暗記用、学習進度に合わせて使うもの
- 「入試対策用」:長文記述・統計資料・思考力を問う応用問題中心
の2タイプがあります。
中高一貫校では、高校受験がないため油断しがちですが、中学のうちから入試レベルの思考力を養う教材も使っておくと、高校進級後に差がつきます。
ただし、定期テスト直前は「定期テスト対策用」問題集で学校の出題範囲に集中するのが効果的です。シーンによって問題集を使い分けましょう。
中高一貫社会のテストの特徴
私立の中高一貫校では、社会の勉強に苦労している子が少なくありません。
中学入試で社会の勉強をがんばっていた子ならともかく、社会が好きじゃなかった子やそもそも中学入試で社会を選択していなかった子にとっては覚えることが多く大変です。
問題量が多い
私立中高一貫の社会のテストは、とにかく問題量が多いです。
問題プリントが公立中なら2~3枚で済みますが、私立なら5枚ほどあります。公立中の2倍です。
これだけの量になると、「これ何だったかな…?」とじっくり考えていると時間が足りなくなります。
細かい知識も聞かれる
問題量が多いというのは、言いかえれば「細かい内容も聞かれる」のです。
例えば歴史で、関ヶ原の戦いが何年に行われたか(1600年)を聞かれるのはもちろん、東軍の大将・西軍の大将を漢字で書かないといけなかったりもします。
公立中ではそこまでテストに出ないので、標準的な市販問題集では対応できません。
理解していないと解けない問題が多い
中高一貫の社会のテストは問題量が多いだけでなく、「なぜそうなったのか」という理解を問う問題も多いのが特徴です。
例えばある私立中学の定期テストで、下記のような問題が出ました。
「松平定信が政治担当者になり、寛政の改革を行った。…浮世絵にも変化が見られた。どのような変化か書きなさい。(記述問題)」
寛政の改革の影響で、浮世絵にどのような変化が見られたかを記述する問題です。ほとんどの中学生はそこまで暗記しませんし、こういう問題を掲載している問題集もほとんどないでしょう。
「寛政の改革の性格」を理解しておき、「そこから考えると浮世絵もこう変化したのではないか?」と論理的に結論を導くようにするほうが現実的です。
社会は暗記科目と言われますが、中高一貫の社会については「しっかり理解して」「考えて解く」ことが求められます。
高校内容が部分的に入ってくる
社会に限りませんが、中高一貫の定期テストではよく高校範囲も習います。6年一貫なので「中学」「高校」という垣根を越えやすいのです。
「ついでにこれも知っておくほうが理解しやすい」と先生が判断すれば、高校内容であっても中学のテストに出てきます。
そのため、前述の地理総合や歴史総合の参考書や問題集を使ってテストに備えるという人もいます。
中高一貫社会の定期テスト対策の仕方
前述のように中高一貫の社会は難易度が高いです。その割に、テスト勉強で使える教材が学校のプリントくらいしかないこともしばしばです。
そこで、中高一貫校の社会の勉強方法について簡単に紹介します。
授業前に予習する
まず、授業前に教科書や配布プリントに目を通しておきましょう。暗記する必要はなく、単元のポイントや歴史の流れを軽く理解しておくだけで十分です。
テストでは理解していないと解けない問題も多数出てきます。頭づくりをした状態で授業に臨むとポイントが頭に入りやすくなり、理解を問う問題をかなり解きやすくなります。
※関連記事:勉強の集中力を高める方法
授業後はアウトプット中心に勉強する
授業で理解したら、授業直後に問題演習でアウトプットをしましょう。記憶にまだあるうちに「思い出す」ようにしておくと、記憶に定着しやすくなります。
この段階ではまだ「覚えなおす」必要はありません。「思い出す(思い出そうとする)作業」が大切です。それをしておくだけでテスト前の勉強で覚えやすくなります。
配布されたプリントをしっかり解く
中高一貫では先生が独自に問題を作成します。高校内容が入ってきたり、ときどきマニアックな内容もテストに出てきます。
教科書には書いていなくても、授業で配布されたプリントの端っこに手書きで書かれていることもあります。プリントをすみずみまで見て勉強しましょう。
特に「手書き箇所」は「後から付け足した」ものですから、テストに出る可能性が高いです。わざわざ付け足すということは、それだけ先生が「生徒に伝えたい」と思っているわけです。
テスト前にしっかり覚えておきましょう!
地図や資料もよく見る
社会のテストには地図や資料がたくさん出てきます。定期テストの場合、教科書や資料集などに掲載されているものがよく使われます。
授業中に先生が資料について解説していたらその内容をメモしておき、テスト前には地図、資料をよくみて勉強しましょう。
記述問題をたくさん解く
前述のように中高一貫の社会は記述問題が多いです。記述問題はパターンが限られています。問題集で記述問題を解いているうちに、「これ、さっき解いた問題と似ている」と気づきます。
ここまでくれば、テストでも速く正確に解答できるようになります。
信頼できる問題集を使うべき理由【講師監修コメント付き】
現役講師が語る「問題集の選び方の落とし穴」
「見た目がカラフルで楽しそう」という理由だけで問題集を選ぶ生徒もいますが、それでは学力は伸びません。特に私立中高一貫校の社会では、単なる暗記ではなく、背景理解・資料の読み取り・記述力が求められます。
問題の質・解説の深さ・構成のバランスが整った教材を使うことで、勉強効率が大きく変わります。
実際に成果を出した生徒の成功事例(実例紹介)
中学2年生のAさんは、1年時は教科書準拠の簡単な問題集だけを使っていましたが、2年生になってからは「新中学問題集」を使うように。演習のたびに解説をじっくり読み、間違いノートを作る学習法を続けた結果、定期テストでは80点→96点にアップ。さらに、模試の偏差値も7ポイント上昇しました。
避けるべき問題集の特徴とは?
以下のような問題集は避けた方が無難です。
- 解答が単語のみで解説がない
- 最新の教科書改訂に対応していない
- 大学受験向けで内容が中1〜2生には難しすぎる
- 口コミ・レビューで「ページ構成がわかりにくい」と指摘が多い
一見お得に見える問題集でも、学習効果が薄ければ時間とお金のムダになります。必ず中身を見てから購入を検討しましょう。
よくある質問(FAQ)
中高一貫校の社会は先取り学習にどう対応すべき?
私立中高一貫校では、中学3年までに高校内容を扱うケースもあります。そのため、問題集も高校初級レベルのものを取り入れていく必要があります。最初は基礎問題集で理解を固め、その後に「新中学問題集」や「よくわかる高校歴史総合」など、広範囲を扱う教材にステップアップするのが理想です。
問題集は毎年買い替えるべき?学年別の使い回しは可能?
基礎問題集は繰り返し使えるものもありますが、定期テスト対策用は学年・範囲に合わせて更新するのが望ましいです。特に、学校のテストが単元ごとに構成されている場合、テスト範囲を見ながら問題集を使うほうが精度の高い対策が可能です。
塾の教材と学校の問題集、どちらを優先すべき?
定期テスト前は、学校の問題集やプリントに合わせて勉強することが最優先です。塾の教材は入試・実力対策には有効ですが、定期テストの出題傾向とズレることがあります。普段は塾教材で力を伸ばし、テスト前は学校の範囲にピンポイントで対応する問題集を活用するのがベストです。
まとめ|自分に合った問題集で社会を得意科目に!
私立中高一貫校に通う中学生にとって、社会は知識の暗記だけでなく、理解・応用力・資料読解など多面的な力が求められる科目です。そのため、自分の学校の進度や学習スタイルに合った問題集を選ぶことがとても重要です。
良い問題集は、あなたの成績を大きく伸ばし、社会を「好きな科目・得意科目」に変える大きな武器になります。ぜひこの記事を参考に、あなたにぴったりの一冊を見つけてください!


コメント