※この記事はPRを含みます
「小論文の段落分けの仕方が分からない」
「小論文では段落分けをしないと減点になる?」
このような疑問をお持ちの高校生は多いようです。
高校生にとって小論文を書く機会はとても少ないですが、大学入試で必要になることがかなり増えてきています。
そこで、小論文での段落分けの仕方について例文付きで解説します。
※関連記事:課題文型小論文の対策法:課題文と読み方、答案の書き方
※関連記事:テーマ型小論文の書き方
小論文では改行・段落分けが重要な理由
小論文では、論理的に分かりやすく主張を伝えることが求められます。そのためには、適切な改行や段落分けを行い、文章を読みやすく整理することが重要です。
読みにくい文章は採点者にとって理解しにくく、内容が適切であっても評価が下がる可能性があります。
誤った改行・段落分けによる減点のリスク要因
適切な改行や段落分けを行わないと、以下のような減点リスクが生じます。
- 論理の流れが分かりにくくなる: どの部分が主張で、どこが補足説明なのか分かりにくくなる。
- 視認性が悪くなる: 長文が続くと、採点官が読むのに負担を感じる。
- 減点の対象になる: 小論文の採点基準には、構成や論理性が含まれているため、適切でない改行・段落分けは減点の要因となる。
小論文の段落分けの仕方
作文など長い文章では大抵、段落分けをします。小論文でも同様です。
小論文における段落分けの仕方を説明します。
参考:さんぽう進学ネット – STEP.2 小論文を書くためのルールを知ろう
段落とは「意味や内容のまとまり」
まず知っておきたいのは段落とは何かです。段落とは「意味や内容のまとまり」を指しています。
1つの段落で1つの話題を入れます。
段落ごとに目的を持たせる
段落ごとに目的を1つずつ持たせましょう。
後ほどくわしくお伝えしますが、文章の展開に応じて段落を分けるとすっきりした読みやすい文章になります。
小論文の構成に沿って3段落に分ける
小論文は序論・本論・結論の3部構成が基本です。この構成に沿って段落も3つに分けると書きやすく、読みやすい文章になります。
この場合、各段落の目的は以下のようになります。
本論を2-3段落に分けても良い
前述のように小論文は3段落に分けると書きやすいですが、本論をさらに2つ3つの段落に分けることも可能です。
その場合、下記のような分け方が便利です。
| 序論 | 意見の主張 |
| 本論 | 意見の根拠① |
| 意見の根拠② | |
| 結論 | 再度意見の主張 |
また、自身の意見と異なる意見を提示し、それに対する反論をするという論旨展開も可能です。例えば下記のような流れです。
①段落:お客様は神様だという意見に賛成だ。
↓
②段落:なぜなら顧客に商品を買ってもらわないと店舗はつぶれてしまうからだ。
↓
③段落:顧客の言いなりになると店舗の運営に支障が出るという意見もある。確かに言いなりになると店舗側に大きな不利益が発生する場合もある。しかし顧客を尊重することと言いなりになることは同一ではない。
↓
④段落:顧客の要望をくみ取りつつ、店舗運営に重大な支障が発生しないような商品提供をすれば良い。
↓
⑤段落:従って、お客様は神様だという意見に賛成だ。
表にすると以下のようになります。
| 序論 | 意見の主張 |
| 本論 | 意見の根拠 |
| 反対意見への反論 | |
| 反論の根拠 | |
| 結論 | 再度意見の主張 |
段落の数も大切ですが、「その段落で何を言いたいのか」が重要です。
段落の最初に要約を入れる
段落にはそれぞれ目的があります。段落の最初に要約を入れるようにすると段落の目的が明確になり、さらに読みやすくなります。
イメージとしては、各段落の最初の一文を読むだけで、その文章の内容が分かる書き方が良いです。
一つの段落に入れるべき内容
1つの段落には、以下の3つの要素を入れると良いでしょう。
- 主張(結論):その段落で伝えたいことを明確に示す。
- 説明・理由:主張を支える根拠や背景を説明する。
- 具体例:説得力を持たせるための例を加える。
要約問題では段落分けしないのが一般的
課題文型小論文では、受験生自身の意見を書く問題以外に「要約問題」もよく出てきます。
要約する問題では、解答条件が特に示されていない限り、段落分けしないのが一般的です。
段落分けしないと減点される例
ここまでは、段落分けの仕方について説明してきました。段落分けをしないと、大抵の場合、減点されるでしょう。
その理由を例文とともに説明します。
※関連記事:教育学部の小論文過去問
※関連記事:医療系学部の小論文過去問
段落分けしないと読みづらい
小論文の採点で「段落分けをしているかどうか」は重要なポイントではありません。ですが、段落分けしていないと読みづらいうえに主張が伝わりにくいです。
そのため、大抵は減点されてしまいます。
段落分けしていない文章(例文)
段落分けしていない場合の例文を紹介します。
【設問】
「裁判員制度の課題とその対策を論じなさい」
【例文】
「裁判員制度には裁判員の負担の大きさが課題となる。心理的負担の観点から論じる。裁判員には、事件の内容や証拠の詳細などを直接聞くことが求められるため、その心理的負担が大きい場合がある。また、裁判員の判断が事件の結果に直接影響を与えることから、ストレスや心理的影響を受けることもある。この問題を解消するため、心理的支援やカウンセリングサービスを実施する必要がある。以上より、裁判員制度には裁判員の心理的負担解消の課題があり、カウンセリングの実施が必要と考える。」
いかがでしょうか。言いたいことが間延びしているような印象です。
何回か読みなおさないと「何を言いたいのか」が伝わりにくい文章です。
段落分けが多すぎる例文
つづいては、段落分けが「多すぎる」例文を紹介します。
【設問】
「裁判員制度の課題とその対策を論じなさい」
【例文】
「裁判員制度には裁判員の負担の大きさが課題となる。
心理的負担の観点から論じる。
裁判員には、事件の内容や証拠の詳細などを直接聞くことが求められるため、その心理的負担が大きい場合がある。
また、裁判員の判断が事件の結果に直接影響を与えることから、ストレスや心理的影響を受けることもある。
この問題を解消するため、心理的支援やカウンセリングサービスを実施する必要がある。
以上より、裁判員制度には裁判員の心理的負担解消の課題があり、カウンセリングの実施が必要と考える。」
先ほどの段落分けのない例文よりも余白が多いので、見やすい印象になるかもしれません。ですが、「何を言いたいのか」はやはり間延びして、ポイントが分かりにくいです。
適切な段落分けの例文
最後に、適切な段落分けをしている例文を紹介します。
【設問】
「裁判員制度の課題とその対策を論じなさい」
【例文】
裁判員制度には裁判員の負担の大きさが課題となる。心理的負担の観点から論じる。
裁判員には、事件の内容や証拠の詳細などを直接聞くことが求められるため、その心理的負担が大きい場合がある。また、裁判員の判断が事件の結果に直接影響を与えることから、ストレスや心理的影響を受けることもある。この問題を解消するため、心理的支援やカウンセリングサービスを実施する必要がある。
以上より、裁判員制度には裁判員の心理的負担解消の課題があり、カウンセリングの実施が必要と考える。
文字数が227字なので、序論・本論・結論の3つの段落に分けました。目的別に段落分けをしていて、なおかつ段落の数も程よいです。
600字や800字の解答になれば、本論をさらに2-3つの段落に分けても読みやすくなります。
小論文での改行の仕方
段落分けと同じく、小論文では改行にも注意が必要です。
参考:総合型選抜専門塾AOI – 小論文の原稿用紙の使い方を専門塾が解説!
改行を入れるべきタイミング
改行は、文章の流れを整理し、読みやすくするために行います。具体的には、以下のタイミングで改行を入れると良いでしょう。
- 新しい話題や主張に移るとき
- 具体例を示すとき
- 結論を述べるとき
改行のルール
つづいて、改行するときのルール(書き方)を紹介します。
はじめの1マスは空ける
改行すると、改行後の最初の1マスは空けるのがルールです。
句読点は最後のマスに書く
改行時、句読点は最後の行に書きます。マス目が下になければ、最後のマス目に文字と一緒に書きましょう。
小さい「っ」など小書き文字も最後のマスに書く
小さい「っ」「ゃ」「ゅ」「ょ」も最後の行に書きます。句読点と同じく、マス目がなければ最後のマス目に書きます。
減点になりやすい改行
改行のタイミングによっては「減点」される場合もあります。
字数稼ぎの改行は減点
まず、字数稼ぎを目的とした改行は厳禁です。
文章を書くときに改行を頻繁にする人もいます。なかには、一文ごとに改行している人もいました。
字数稼ぎで改行すると減点対象になります。
改行が多すぎると読みづらい
改行は頻繁にするものではありません。改行が多すぎると読みづらい文章になります。
段落分けと同じで、余白が生まれて見た目の印象は良いかもしれませんが、「何を言いたいのか」が伝わりにくい文章になります。
段落分けが改行するタイミング
以上の注意点を踏まえて結論を申し上げると、小論文では、「段落分け」をするときにだけ改行しましょう。
【まとめ】大学受験小論文で減点されない改行・段落分けのコツ
読みやすい段落構成の作り方
導入・本論・結論の各段落の長さの目安
- 導入: 100〜150字程度(1段落)
- 本論: 2〜3段落(各100〜150字)
- 結論: 100字程度(1段落)
どこで段落を区切るべきか?
- 主張の切り替え時
- 新しい論点を示すとき
- 例と結論を分けるとき
NG例と改善例(ビフォーアフター)
悪い例:「改行なしで読みにくい文章」
小論文では、主張を明確にすることが重要です。そのためには、論理的な構成を意識する必要があります。例えば、意見を述べる際には、その意見の根拠を示し、それを支える具体例を挙げることが求められます。これによって、説得力のある小論文になります。
良い例:「適切に改行し、論理的に整理された文章」
小論文では、主張を明確にすることが重要です。
そのためには、論理的な構成を意識する必要があります。例えば、意見を述べる際には、その意見の根拠を示し、それを支える具体例を挙げることが求められます。
これによって、説得力のある小論文になります。
大学受験で評価される小論文の書き方(応用編)
字数制限内で効果的に改行を使うコツ
- 無駄な表現を削る(例:「私は思う」→「私は考える」)
- 短い文章を意識する(1文は40字以内が理想)
- 接続詞を適切に使う(「しかし」「例えば」など)
採点官が評価しやすい段落の作り方
- 一つの段落に1つの主張を明確にする
- 視認性を考えたバランスの良い改行
- 「結論→理由→例→まとめ」の流れを意識する
まとめ
いかがでしょうか。
高校生向けに、小論文での段落分けの仕方を例文付きで紹介しました。
段落は意味や内容のまとまりなので、段落ごとに目的を持たせます。小論文は序論・本論・結論の3部構成が多いので、構成に沿って3段落に分けると書きやすくなります。
また、改行は段落分けをするときにだけ実施します。字数稼ぎを目的とした改行は減点対象になります。
Z会 小論文講座の案内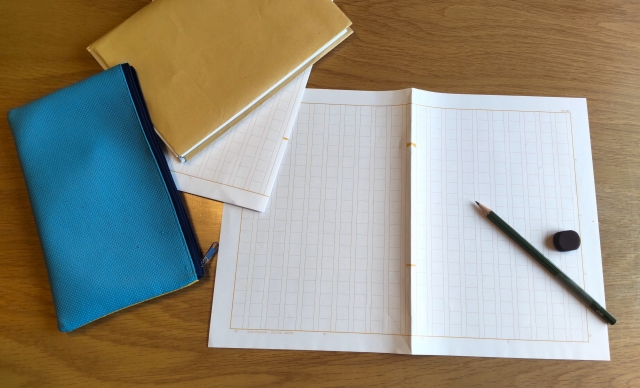


コメント