高校生向けに日本史の一問一答問題と解説を用意しました。今回は平安時代末期の保元の乱から鎌倉時代のはじまりまでをまとめています。
歴史総合や日本史探求の定期テスト対策、大学入試対策などにご活用ください!
※関連記事:日本史年号一覧:覚えやすい語呂合わせと入試によく出る重要な出来事
保元の乱・平治の乱とは?—戦の経過と影響
1156年、京都で保元の乱と呼ばれる戦乱が発生します。上皇と天皇の争いに武士が本格的に参加した争いでした。平氏と源氏が武家として飛躍的に地位を向上させるきっかけになりました。
さらに1159年には平治の乱が発生。平清盛が源義朝を倒しました。その後の武家政権樹立につながっていく大きな転換点になりました。
保元の乱発生の背景:後白河天皇と崇徳上皇の対立
保元の乱は、後白河天皇と崇徳上皇の争いを軸に、摂関家内部の争いや皇室の権力争いが絡んで発生しました。朝廷内部が混乱する中で、各武士が勢力の拡大を狙い、主要な勢力がそれぞれの立場を取りました。
源義朝と平清盛の立場
武士団も二分され、源義朝は後白河天皇側、平清盛も同じく天皇側に加勢しました。一方で、崇徳上皇側には源為義や平忠正が味方をしていました。この対立は源氏と平氏の内部でも対立を生み、以後の武士政権の礎となりました。
保元の乱が与えた影響
保元の乱(1156年)は、武士が政治的に台頭する契機となりました。乱の勝利によって平清盛と源義朝が権力を強化し、朝廷内での地位を大きく向上させました。
この乱の結果、朝廷内での貴族間の権力争いで武家の力を頼るようになりました。
平治の乱の原因と経過:源義朝と平清盛の対立
平治の乱(1159年)は、後白河上皇の近臣間での権力争いと、平家と源氏の対立が原因で起こりました。保元の乱で勢力を伸ばした平清盛が後白河上皇に接近した一方、源義朝と藤原信頼はその勢力を抑えようとしました。
平清盛が京を離れたすきに義朝と信頼はクーデターを起こして源通憲を自害に追い込みます。
ところが、清盛が反撃し、最終的に義朝と信頼は敗北。これにより平家が政権を掌握し、源義朝を棟梁とする源氏勢力は壊滅しました。
なお、源義朝以外の源氏勢力は健在で、源頼政は平清盛に味方して京都で一定の地位を得ていました。ただし、1180年に反乱未遂で以仁王とともにほろびました。
参考:戦国ヒストリー
平治の乱が与えた影響
平治の乱で平清盛は義朝を打ち破り、さらに朝廷における立場を強化します。これにより平氏は圧倒的な支配力を持つこととなり、貴族社会と一体化して勢力を拡大していきます。
この後、平清盛が武家出身ではじめて太政大臣に任命され、大輪田の泊に港を築いて日宋貿易をはじめるようになります。
治承寿永の乱とは?—その背景と重要な出来事
平清盛による政権運営が行われるなか、1180年に以仁王と源頼政が反乱を起こします。この反乱自体はすぐに鎮圧されますが、平清盛への反乱は全国各地で相次ぎ、1185年に平清盛の直系ぐグループはほろびました。
これを治承寿永の乱と呼びます。
治承寿永の乱の背景
治承寿永の乱(1180年)は、平家と源氏の間で繰り広げられた戦闘で、日本の歴史における重要な転換点です。
この乱は、平清盛が朝廷内の権力を掌握し、平家がその権力を保持していた時期に発生しました。しかし、平家の支配に不満を抱いた源氏やその他の勢力が反発し、対立が激化しました。
源頼朝や源義仲(木曽義仲)といった源氏の武士が立ち上がり、平家の圧制に抗しました。
この背景には、平家の横暴と、それに対する地方武士たちの反発があり、社会的な不満が高まっていました。また、貴族層の権力争いも関係しており、政治的な混乱が戦争を引き起こしました。
治承寿永の乱の結果と影響
治承寿永の乱は、最終的に源氏が勝利し、平家が没落する結果となりました。
源頼朝が鎌倉で独自の勢力を拡大し、武士としての権力を確立させます。この勝利により、平家は滅び、源氏が支配を握りました。

この乱がもたらした影響の一つは、武士階級の台頭です。平安時代末期にあたるこの時期、武士の権力が強化され、鎌倉幕府成立へと繋がります。
また、源氏の勝利は、以後の日本における武士社会の確立と、それによる政治体制の変革につながりました。
鎌倉幕府の成立—源頼朝の台頭と幕府体制の確立
1185年に平家との戦いに勝利した源頼朝は、朝廷より全国の守護と地頭の任命権を獲得します。この年が実質的な鎌倉幕府成立の年とされています。
源頼朝の役割と鎌倉幕府の成立
源頼朝は治承寿永の乱で源氏側を率いた人物であり、その後、鎌倉幕府を開いたことで知られています。
頼朝は、平家を倒した後、1185年に全国の守護・地頭の任命権を得、1192年に征夷大将軍の職に任命され、実質的な支配権を得ました。これにより、中央政権に対する武士の支配が始まり、平安時代の貴族中心の政治体制から、武士中心の新しい政権へと変わります。
頼朝は鎌倉に幕府を構え、武家政治を開始。これにより、武士が国家運営に直接関わるようになり、以後の日本の歴史を大きく変えることとなります。
鎌倉幕府の成立後の社会変革
鎌倉幕府の成立は、社会全体に大きな変革をもたらしました。平安時代の貴族層が支配していた中央集権的な政治体制から、地方の武士階級が権力を持つ体制へと変わったのです。
この変化により、武士が支配する土地や領地に対して支配権を確立し、また新たな法律や規範が整備されました。
頼朝は、鎌倉における権力基盤を強化し、武士社会を支えるための体制を作り上げました。これが後の日本の政治体制の基盤を築くこととなります。
テストに出やすい年号と出来事
保元・平治の乱から治承寿永の乱や鎌倉幕府成立までの範囲で、テストに出やすい年号や出来事をまとめました。
主要な年号とその意味
治承寿永の乱(1180年)、保元の乱(1156年)、そして鎌倉幕府の成立(1192年)は、いずれも日本の中世史において重要な年号です。
これらの年号は、それぞれの出来事が日本社会に与えた影響を記録しています。
治承寿永の乱は源氏と平家の決戦であり、平家の滅亡を意味します。保元の乱は武家の権力強化の起点となり、鎌倉幕府の成立は武士中心の政権の誕生を示します。
これらの年号は試験で頻出であり、その背景や関連する人物、出来事を覚えることが重要です。
重要人物とその役割
保元の乱から鎌倉幕府成立までの約30年間の間での重要人物についてまとめました。
保元の乱の重要人物
保元の乱は天皇と上皇の争いに摂関家がからみ、源氏と平氏が関わった争いでした。
以下のような勢力図になっていました。
| 天皇方(勝利者側) | 上皇方(敗者側) | |
| 後白河天皇 | 天皇家 | 崇徳上皇 |
| 藤原忠道(関白) | 摂関家(藤原家) | 藤原頼長(左大臣) |
| 平清盛 | 平氏 | 平忠正 |
| 源義朝 | 源氏 | 源為義 |
平治の乱の重要人物
保元の乱以降、信西が政治の中心になりました。その信西の政治に対して反発する勢力が起こしたのが平治の乱でした。
以下のような勢力図でした。
| 勝利者側 | 敗者側 | |
| 藤原通憲(信西) → 自害 | 後白河天皇の側近 | 藤原信頼 |
| 平清盛 | 武家 | 源義朝 |
治承寿永の乱の重要な人物
治承寿永の乱では、源義仲、源頼朝、源義経、以仁王、源頼政、平清盛などが重要な人物として登場します。
1180年、以仁王が平家打倒の令旨を出し、源頼政が呼応しました。この2人は早々に鎮圧されますが、平清盛も翌年病死します(1181年)。
その後、源義仲が平家との戦いに勝ち、最初に京都を占領しました。その源義仲を源義経が京都から駆逐し、1185年壇ノ浦の戦いで平家を滅ぼしました。
鎌倉幕府成立に関わった主要人物
鎌倉幕府の設立に最も重要な役割を果たしたのは、源頼朝です。
頼朝は、源氏を率いて平家を倒し、鎌倉に幕府を開くことで、武士による政権の始まりを象徴しました。
また、頼朝の死後、その子孫が続くこととなり、幕府政治の仕組みは次第に完成されていきました。
なお、鎌倉幕府の将軍については以下の記事でくわしく解説しています。
鎌倉幕府の将軍9名をわかりやすく解説!【高校生の日本史テスト対策】
まとめと試験対策のポイント
保元の乱、平治の乱、治承寿永の乱、そして鎌倉幕府の成立に関しては、それぞれの出来事の年号や、そこに登場する人物、結果として何が起こったのかをしっかりと覚えましょう。
特に試験では年号、人物、そしてその影響を問われることが多いため、これらの要素を整理して学習すると効果的です。
また、各戦乱の経過や背景、結果についての理解を深めておくと、より高得点を目指すことができます。
【高校日本史】平安時代末期の一問一答問題:保元の乱から治承寿永の乱まで
(1)1156年、天皇と上皇の対立から武家をまきこんだ大きな戦争が京都で起こりました。この戦を何といいますか。
(2)保元の乱で対立した天皇と上皇はそれぞれ誰ですか。また、どちらが勝利しましたか。
(3)保元の乱で後白河天皇方についた平氏の棟梁は誰ですか。
(4)保元の乱で後白河天皇方についた源氏の棟梁は誰ですか。
(5)保元の乱の後、後白河天皇の側近である藤原氏2名が対立します。誰と誰ですか。
(6)保元の乱の後、源氏と平氏が恩賞をめぐって対立します。このときの源氏の棟梁と平氏の棟梁は誰ですか。
(7)1159年、藤原信頼と信西の対立は武家を巻き込んだ戦に発展しました。この戦を何といいますか。
(8)平治の乱で藤原信頼が味方に引き入れた武家は誰ですか。
(9)平治の乱のはじまりは、藤原信頼と源義朝が天皇を幽閉したことでした。このとき幽閉された天皇は誰ですか。
(10)平治の乱で信西側の味方をしていた武家は誰ですか。
(11)平治の乱後、平清盛は律令制度における最高位である役職に武士としてはじめて任命されました。何という役職ですか。
(12)平清盛は天皇に娘・徳子を入内させ、生まれた子を次の天皇に即位させました。このとき即位した天皇は何天皇ですか。
(13)平清盛は当時の中国王朝と貿易を開始します。何という王朝ですか。
(14)平清盛は、現在の神戸港にあたる何という港を修築して貿易に使いましたか。
(15)1177年、後白河法皇の側近である藤原成親や僧俊寛らが平家打倒を企てたとして処罰されました。何という事件ですか。
(16)1180年、後白河天皇の皇子が全国に平氏追討の命令を出します。この皇子は誰ですか。
(17)以仁王が出した命令のように、皇子が出す命令のことを何といいますか。
(18)1180年、以仁王の令旨に応えて平氏の味方をしていた源氏の武将が以仁王とともに反乱を起こし敗死します。この武将は誰ですか。
(19)1180年、以仁王の令旨に応えるかたちで伊豆で挙兵し、石橋山の戦いで敗れた源氏の武将は誰ですか。
(20)1180年、信濃で挙兵し、越中倶利伽羅峠で平氏を破るなどして入京を果たした武将は誰ですか。
(21)1180年、平清盛は平氏政権に反抗する仏教勢力をおさえるために南都焼き討ちをさせました。この命令を受けて焼き討ちを実行した武将は誰ですか。
(22)1181年に天候不順のために飢饉が起こり、多くの人が亡くなりました。この飢饉を何と呼びますか。
(23)1184年には源頼朝の命を受けた武将たちも入京し、先に入京していた源義仲と交戦します。このとき入京した源頼朝の弟2人を答えてください。
(24)1184年に源義経らが崖から平氏を奇襲して破った戦いを何といいますか。
(25)1185年に起こった源氏と平氏の戦いで、那須与一の扇の的当てで有名な戦いは何ですか。
(26)1185年に平氏が滅亡した戦いを何といいますか。
(27)1180年の以仁王の挙兵から1185年の壇ノ浦の戦いまでの源平合戦を総称して何の乱と呼びますか。
解答
(1)保元の乱
(2)後白河天皇と崇徳上皇、後白河天皇の勝利
(3)平清盛
(4)源義朝
(5)藤原信頼と藤原道憲(信西)
(6)源義朝と平清盛
(7)平治の乱
(8)源義朝
(9)後白河天皇
(10)平清盛
(11)太政大臣
(12)安徳天皇
(13)宋
(14)大輪田泊(おおわだのとまり)
(15)鹿ケ谷の陰謀
(16)以仁王
(17)令旨
(18)源頼政
(19)源頼朝
(20)源義仲
(21)平重衡
(22)養和の大飢饉
(23)源義経・源範頼
(24)一ノ谷の戦い
(25)屋島の戦い
(26)壇ノ浦の戦い
(27)治承・寿永の乱
一ノ谷の戦い、屋島の戦い、壇ノ浦の戦いの覚え方
源平合戦のラスト3つの戦いは順番がややこしいです。一ノ谷の戦い、屋島の戦い、壇ノ浦の戦いです。
以下の順番です。
- 1184年一ノ谷の戦い
- 1185年屋島の戦い
- 1185年壇ノ浦の戦い
壇ノ浦の戦いは「平氏が滅亡した戦い」と覚えておきましょう。
壇ノ浦の戦いがラストだと覚えておけば、一ノ谷の戦いは「一」がついているから1番目の戦い、屋島の戦いは消去法で2番目の戦いと思い出しやすくなります。

日本史の問題集
最後に日本史のおすすめ問題集を紹介します。
※関連記事:日本史文化史の参考書と覚え方
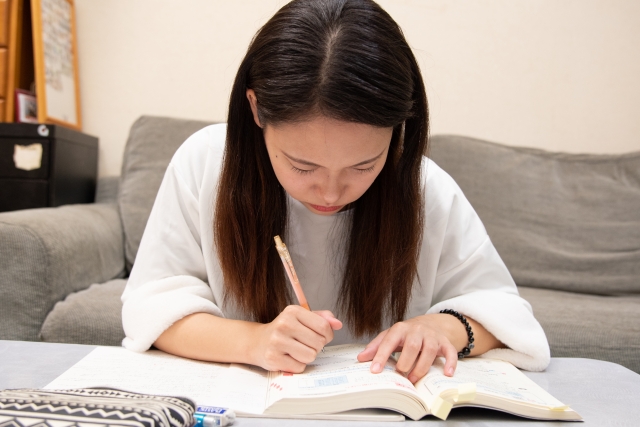
『金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本 改訂版』
1冊目は日本史参考書の定番、「金谷の日本史」です。古代~近現代まで3冊と文化史1冊の合計4冊に分けて解説してくれています。
内容はオーソドックスで、教科書をさらにくわしく解説してくれています。
すべてじっくり読むというより、問題集で問題を解きつつ因果関係が分かりにくいときに参考書として使う人も多いです。
特に、共通テストを受ける人は『文化史』だけでも読んでおくと役立ちます。

金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本【改訂版】 原始・古代史 (東進ブックス 大学受験 名人の授業)

金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本【改訂版】 中世・近世史 (東進ブックス 大学受験 名人の授業)

金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本【改訂版】 近現代史 (東進ブックス 大学受験 名人の授業)

金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本【改訂版】文化史 (東進ブックス 大学受験 名人の授業シリーズ)
出版社:ナガセ
『日本史B一問一答【必修版】【完全版】』
流れを理解できるようになったら、問題演習をして記憶に定着させる必要があります。
この問題集はそんなときに便利です。
「必修版」と「完全版」に分かれており、現在の学力や志望校のレベルに合わせて選べます。

日本史B一問一答【必修版】 (東進ブックス 大学受験 一問一答シリーズ)

日本史一問一答【完全版】2nd edition (東進ブックス 大学受験 一問一答シリーズ)
出版社:ナガセ
『よくわかる高校日本史探究』
学研が出版している「標準レベルまで」の参考書です。教科書よりも解説がくわしく、日本史探求に苦手意識を持っている人も理解しやすいです。
定期テスト対策用の問題ページもあり、定期テスト対策、中堅レベルまでに大学入試対策に便利です。

よくわかる高校日本史探究 (MY BEST)
出版社:Gakken
保元の乱・平治の乱・治承寿永の乱に関するQ&A
Q1: 保元の乱はいつ起こりましたか?
A: 1156年(保元元年)に発生しました。
Q2: 保元の乱の原因は何ですか?
A: 天皇家と摂関家の内部対立が主な原因です。崇徳上皇と後白河天皇の皇位継承争いに加え、藤原氏の家督争いも絡みました。
Q3: 保元の乱で活躍した武士は誰ですか?
A: 後白河天皇側に源義朝と平清盛が、崇徳上皇側に源為義と平忠正がつきました。
Q4: 保元の乱の結果は?
A: 後白河天皇側が勝利し、崇徳上皇は讃岐に流されました。この勝利により平清盛と源義朝が権力を得ました。
Q5: 平治の乱はいつ起こりましたか?
A: 1159年(平治元年)に発生しました。
Q6: 平治の乱の原因は何ですか?
A: 後白河上皇の近臣間の権力争いと、源義朝と平清盛の対立が原因です。
Q7: 平治の乱の経過は?
A: 藤原信頼と源義朝が後白河上皇を擁立してクーデターを起こしましたが、平清盛の反撃によって敗北しました。
Q8: 平治の乱の結果は?
A: 源義朝は討たれ、源氏は一時的に勢力を失い、平清盛が権力を掌握しました。
Q9: 治承寿永の乱はいつ起こりましたか?
A: 1180年から1185年にかけて行われました。
Q10: 治承寿永の乱の原因は?
A: 平家による専制政治に対する不満や、源氏による反乱が原因です。後白河法皇の皇族間の争いも影響しました。
Q11: 治承寿永の乱の主要な戦いは?
A: 主要な戦いには以下のものがあります:
- 1180年:石橋山の戦い(源頼朝の敗北)
- 1184年:一ノ谷の戦い(源氏が平家を撃破)
- 1185年:壇ノ浦の戦い(平家の滅亡)
Q12: 治承寿永の乱の結果は?
A: 平家が滅亡し、源頼朝が鎌倉幕府を開き、武士による政治が始まりました。
Q13: この3つの乱を整理して覚えるポイントは?
A:
- 保元の乱(1156年):皇族と貴族の権力争い
- 平治の乱(1159年):武士による権力争い
- 治承寿永の乱(1180~1185年):武士の時代への転換点
Q14: 試験で出やすい年号と覚え方は?
A:
- 1156年(保元の乱):「いい頃(1156)に保元」
- 1159年(平治の乱):「いい号令(1159)で平治」
- 1185年(壇ノ浦の戦い):「いい箱(1185)に平家滅亡」
まとめ
いかがでしょうか。
高校生の日本史の勉強用に、平安時代末期の争乱を一問一答にまとめました。保元の乱、平治の乱、治承・寿永の乱(源平合戦)の3つです。
治承・寿永の乱では以仁王の令旨にはじまり、源頼政や源義仲の挙兵も覚えておきましょう。
また、一之谷の戦い→屋島の戦い→壇ノ浦の戦いの順番も間違いやすいポイントです。
定期テスト対策、大学入試に向けてご活用ください。
平安時代について、下記の記事でも紹介しています。
【日本史の一問一答】平安時代初期(桓武天皇・嵯峨天皇)の問題や解説:三筆、天台宗と真言宗のまとめなど
平安時代の一問一答:薬子の変から後三年の役まで平安時代の変、乱、合戦を総まとめ
平安時代の一問一答:律令体制の変化(受領・遥任、荘園整理令、院政、強訴など)
日本史の一問一答:国風文化のまとめ(平安時代中期の文化:三蹟、古今和歌集など)
日本史の一問一答:院政期文化のまとめ(平安時代末期:浄土教、軍記物語、説話集、歴史物語、絵巻物など)



コメント