中学受験で図形を苦手にしている子は多いです。
公式を当てはめれば解けるような基本問題は入試にはあまり出ず、応用レベルが中心になります。
ですが、算数は1問ずつの配点が大きいため、苦手分野での取りこぼしは避けたいところです。
そこで、図形が苦手な子や入試によく出る図形問題を解く力をつけたい子向けに、おすすめの図形問題集を紹介します。
問題集の選び方や図形の基礎知識のおさらい、図形問題の解き方のコツも説明しているので、問題集選びと合わせてぜひご参考ください。
※関連記事:【中学受験】平面図形・空間図形の解き方
※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法
中学受験における図形問題の重要性とは?
図形問題は中学受験の算数において、合否を左右する重要分野のひとつです。特に難関中学では、図形の理解力・空間認識力・論理的思考力を問う問題が頻出し、「得意・不得意の差が出やすい」分野でもあります。
図形問題が中学受験において占める割合
図形問題の出題頻度と重要性
中学受験算数の中で図形分野が占める割合は、学校によって差はあるものの、全体の20~40%前後といわれています。特に難関校になるほど、複雑な図形や応用問題の出題率が高くなる傾向があります。
たとえば、以下のようなジャンルの問題が頻出です。
- 平面図形(角度、面積、合同、相似)
- 立体図形(体積、表面積、切断)
- 回転体、投影図
- 図形の移動・変化(展開図・回転・移動)
このように、単なる計算力では対応できない「図形特有のセンスと論理的思考」が試されるため、他の受験生と差をつけるチャンスにもなります。
図形問題の特徴と求められる能力
図形問題には、以下のような特徴があります。
- 文章問題よりも図やイメージで理解する力が必要
- 図を正確に描く力、書かれた図を読み取る力が重要
- 空間認識力や仮説・検証の思考法が問われる
そのため、求められる能力としては、
- 図形を視覚的に捉える力
- 論理的に手順を組み立てる力
- 試行錯誤を恐れない姿勢
- 計算ミスを防ぐ注意力
図形問題は「ひらめき」だけで解けるものではなく、基本を理解し、論理的に考える力を育てることが最も大切です。
図形問題の攻略法と学習ポイント
図形の基礎知識を徹底理解
まず大前提として、基本的な図形の性質を正確に理解することが図形攻略の第一歩です。
主な基礎知識には以下のようなものがあります。
- 三角形、四角形の内角の和、外角の性質
- 円の性質(接線、弧、中心角など)
- 立方体・直方体の辺・面・体積
- 回転体や切断図形の見え方
これらを図を書いて自分で確認する習慣をつけることが重要です。頭の中で考えるだけでなく、紙に描くことで理解が深まり、図形感覚が養われます。
また、用語(「底辺」「高さ」「対角線」「合同」「相似」など)を正しく理解し、図形用語で説明できるようにしておくことも有利です。
効果的な問題演習と解法のコツ
図形問題を攻略するためには、単に問題集を解くだけでなく、「どんな問題パターンに慣れるか」がカギになります。
以下のような学習法が効果的です。
- テーマ別に学習する
「角度問題」「面積問題」「立体の切断」など、ジャンルごとに問題を集中的に取り組むことで、出題パターンが見えるようになります。 - 図を必ず描く(トレース学習)
与えられた図を写しながら、補助線を自分で引く練習をすることで、「どこに注目すればよいか」が見えるようになります。 - 問題ごとに「解法の手順」を言語化する
「この問題は、対角線を引いて三角形に分ける」といった解き方の考え方を自分の言葉でまとめる練習をすると、本番でも応用が利きます。 - 1問を深掘りする学習法を取り入れる
「解けたら終わり」ではなく、「なぜこの解法を使うのか?」「他のやり方はあるか?」といった多角的な視点で1問を研究する習慣が、難問に対応する力を育てます。 - 間違えた問題は「解き直しノート」にまとめる
一度間違えた図形問題は、放っておくと同じパターンでまた間違えます。自分専用の「弱点ノート」を作り、反復練習することで確実に定着します。
図形問題の習得には時間がかかりますが、しっかり基礎から積み上げ、正しい方法でトレーニングを重ねることで、確実に力がつきます。
中学受験に役立つ図形問題集の選び方
図形問題は中学受験の算数において得点差がつきやすい重要単元ですが、効果的に学習するには目的に合った問題集の選定が欠かせません。特に図形は「感覚的な理解」では乗り切れず、段階的な理解と演習の積み重ねが必要です。
そこでこの章では、「どんな視点で図形問題集を選べばよいか」「学年別にどのような教材が最適か」について詳しく解説します。
図形問題集選びのポイント
難易度別に見る問題集の選定基準
図形問題集を選ぶ際には、まずお子さんの現在の理解度と目指す志望校のレベルに合わせた「難易度の見極め」が最も大切です。
以下はおおよその難易度別の選び方です。
| レベル | 特徴 | おすすめの使い方 |
|---|---|---|
| 基礎レベル | 図形の性質や計算練習が中心。 | 図形が苦手な子、5年生の初期段階に最適。 |
| 標準レベル | 入試頻出の典型問題が網羅されている。 | 受験勉強の中心教材として活用。 |
| 応用・発展レベル | 難関中学の過去問に近いレベルの問題。 | トップ校志望者や6年生の仕上げに適する。 |
図形問題は特に「基礎 → 標準 → 応用」へと段階的にレベルアップすることが効果的です。基礎が不十分なまま応用に進むと、解法暗記に頼ってしまい、実力が伸びにくくなります。
問題集の特徴と教材の選び方
選ぶ際には以下の点に注意しましょう。
- 解説の丁寧さ
- 補助線の引き方や図の見方が図解されているものを選ぶと、初学者にも理解しやすい。
- 解説が言葉だけで済まされている教材は、理解が進みにくいことがあります。
- 構成の分かりやすさ
- 「分野別」「レベル別」など体系的に整理されているものは、学習計画が立てやすく定着しやすい。
- 入試分析に基づいた内容か
- 実際の入試でよく出るパターンや頻出校の出題傾向が取り入れられているかどうかをチェック。
- 図の質と見やすさ
- 図形の教材では、「図の分かりやすさ」は非常に重要です。線が細すぎたり、色分けがないと理解の妨げになる場合も。
- 書き込み式か否か
- 書き込み式は直感的な学習に向いており、特に小学生にはおすすめです。一方、繰り返し使うならコピー可能なタイプが便利です。
各学年に適した図形問題集
図形学習は5年生から本格化し、6年生での応用・演習で完成度を高めます。それぞれの学年で適した教材を選ぶことが、受験対策の成功のカギになります。
小学5年生向け:基礎から始める
5年生では、以下のような力を養うことが目標です。
- 基本的な図形の知識(面積・角度・体積)
- 図形を正しく描く力
- 問題文を図に置き換える力
この時期におすすめの問題集は以下のタイプです。
- 教科書準拠+図形強化タイプ
→「塾技100 算数 図形編」などは、基本を押さえながら少し難しい問題も収録。 - ビジュアル中心の問題集
→「なぞぺー」シリーズや「学研の図形パズル」は楽しく図形感覚を育てるのに効果的。 - 書き込み式の反復教材
→「くもんの小学ドリル」シリーズなど、繰り返し演習に最適。
この段階では、「図形に慣れること」「手で描いて覚えること」が最重要です。
小学6年生向け:応用力を養う
6年生になると、実際の入試問題に近い形式に慣れ、図形問題に対して得点力をつけることが求められます。
この時期に選びたい教材:
- 入試過去問を分析した問題集
→「中学入試 最高水準問題集(図形編)」は、難関校対策に最適。 - 単元別実戦トレーニング本
→「中学への算数 図形特訓」や「予習シリーズ 算数 応用問題集 図形分野」など、問題の質・量ともに充実。 - 図形問題に特化したまとめ教材
→「受験研究社/図形トレーニングシリーズ」なども、総仕上げに有効。
6年生では、「どんなタイプの図形問題でも、自力で解法を組み立てられる」ことを目指すべきです。過去問演習と併用しながら、自分の弱点分野を意識して取り組みましょう。
まとめ
図形問題集の選び方には「レベル」「解説の質」「視覚性」「学年への適合性」が重要です。5年生では図形への抵抗感をなくし、6年生では得点源にできるレベルまで高める戦略が合格への鍵になります。
中学受験図形のおすすめ問題集9選
中学受験で図形を苦手にしている子や入試直前に図形の問題で点数アップしたい子向けのおすすめ問題集を紹介します。
初学者向け:基礎から学べる図形問題集
おすすめ問題集①:『算数図形 新装版 まんがではじめる中学入試対策!中学入試まんが攻略BON!』(学研プラス)
図形問題が苦手なお子様や、初めて図形に取り組む方に最適な一冊です。漫画形式で角度・面積・体積などの基礎を楽しく学べ、実際の入試問題にも挑戦できます。

算数 図形 新装版 まんがではじめる中学入試対策! 中学入試まんが攻略BON!
おすすめ問題集②:『中学入試 算数のつまずきを基礎からしっかり [図形] 新装版』(学研)
小学4年生から5年生前半までの基礎内容に対応しており、算数全般が苦手なお子様に適しています。少ない問題数で確実に理解を深められる構成です。
2025年6月に新版が出版。

中学入試 算数のつまずきを基礎からしっかり [図形] 新装版
おすすめ問題集③:『単問チェックで中学入試基礎固め/図形』(東京出版)

単問チェックで中学入試基礎固め/図形
中級者向け:発展的な問題に挑戦する図形問題集
おすすめ問題集④:『中学受験 すらすら解ける魔法ワザ 算数・図形問題』(実務教育出版)
平面図形から空間図形まで、入試で頻出の典型問題を網羅しています。解法のパターンを学ぶことで、応用力を養うことができます。

中学受験 すらすら解ける魔法ワザ 算数・図形問題
おすすめ問題集⑤:『中学入試 算数図形問題完全マスター』(数研出版)
基礎から標準レベルの問題を中心に、各単元に例題と練習問題があり、章末にはまとめの問題が用意されています。理解度に応じて段階的に学習を進められます。

中学入試 算数図形問題完全マスター
おすすめ問題集⑥:『中学入試 でる順過去問 図形 合格への307問 三訂版』(旺文社)
でる順もやはり便利です。入試頻出問題ばかりを集めて掲載してくれているので、とても効率よく入試対策ができます。
入試直前のチェック用としても役立ちます。

中学入試 でる順過去問 図形 合格への307問 三訂版 (中学入試でる順)
おすすめ問題集⑦:『中学入試 分野別集中レッスン 算数』(文英堂)
基礎から入試レベルまで幅広い問題演習ができます。
解説が非常にくわしく、公式や定理の省略もありません。

中学入試 分野別集中レッスン 算数 平面図形 (シグマベスト)

中学入試 分野別集中レッスン 算数 立体図形 (シグマベスト)
上級者向け:高度な図形力を試す問題集
おすすめ問題集⑧:『中学入試カードで鍛える図形の必勝手筋シリーズ』(東京出版)
「平面図形編」と「動く図形・立体図形編」があり、約200題の問題がカード形式で収録されています。問題の裏面に解答があり、繰り返し学習に最適です。図形問題のパターン化と解法の習得に効果的です。

中学入試カードで鍛える図形の必勝手筋 平面図形編
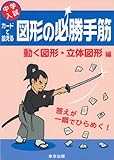
カ-ドで鍛える図形の必勝手筋: 中学入試 (動く図形・立体図形編)
おすすめ問題集⑨:『図形ドリル 中学受験 難関校 上級問題 プレジデントファミリー付録』
難関校を目指す受験生向けの上級問題集で、難度の高い図形問題に特化しています。高度な図形力を養うための演習に適しています。
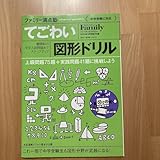
図形ドリル 中学受験 難関校 上級問題 プレジデントファミリー付録
図形問題集を活用した学習法
図形分野は、単なる暗記や計算力では乗り切れないのが特徴です。実力をつけるには、問題集を「解くだけ」で終わらせず、戦略的に使いこなす学習法が求められます。
この章では、図形問題集を最大限に活かすための学習スケジュールの立て方と、よくあるミスとその対策について解説します。
図形問題集を効果的に使うための学習スケジュール
学習計画の立て方
図形の実力を伸ばすには、「解く→理解→定着→応用」のサイクルを回すことが大切です。そのためには、計画的な学習スケジュールが不可欠です。
1. 単元ごとにテーマを分ける
図形の中にも「平面図形」「立体図形」「角度」「面積」「回転体」など複数の分野があります。いきなり広範囲に手を出すのではなく、1テーマ1週間などで区切って取り組みましょう。
2. 週単位でスケジュール化する
たとえば1週間の流れの一例は以下のとおりです。
| 曜日 | 内容 |
|---|---|
| 月 | 新しい図形単元の学習(解説・例題) |
| 火 | 問題集で基本演習 |
| 水 | 応用問題に挑戦 |
| 木 | 間違えた問題の見直し・ノートまとめ |
| 金 | 追加演習(別の問題集や塾テキスト) |
| 土 | まとめテスト・確認問題 |
| 日 | 休養 or 苦手単元の復習 |
3. 実践時間の確保がカギ
図形は「自分の手で図を書く」「補助線を入れる」といった能動的な練習が重要です。必ず時間を決めて、集中して解く習慣を作りましょう。
定期的な復習と進捗管理
定着のポイントは「復習のタイミング」です。
- 24時間以内に一度復習
- 1週間以内にもう一度
- 1か月後に再確認
この「3回復習ルール」で、短期記憶から長期記憶へとつなげられます。
また、進捗管理には以下のような方法がおすすめです:
- チェックシートを使って「できた・できなかった」を記録
- 間違えた問題に付箋を貼り、後日ピンポイントで復習
- 進捗率をグラフにしてモチベーションを維持
これにより、図形問題の「弱点分野」や「苦手なパターン」が可視化され、効率的に対策が打てます。
図形問題集でよくある間違いとその対策
初歩的なミスを防ぐ方法
図形問題では、思わぬミスで得点を落とすケースが多く見られます。よくある初歩的ミスとその対策を以下に示します。
| よくあるミス | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| 補助線の引き忘れ | 図の分析が不十分 | 問題ごとに「何を補うべきか」を考えるクセをつける |
| 長さ・角度の見間違い | 図が正確に描けていない | コンパスや定規を使って正確に描写、図形ノートで練習 |
| 単位のミス(cm⇔m) | 数値の確認不足 | 問題文に下線を引き、単位を色分けして記憶に定着させる |
| 書き間違い・転記ミス | 焦りや確認不足 | 解答後に「数字・単位・図」を見直す習慣をつける |
「見直しの時間を1問ごとに必ず確保する」ことが、ミス防止にはもっとも有効です。
よくある落とし穴と回避法
中学受験レベルの図形問題には、「一見簡単そうに見えて引っかかる」落とし穴がいくつもあります。
主な落とし穴:
- 条件の見落とし
問題文中の「垂直」「対称」「同じ長さ」など、図には描かれていないヒントを見落としてしまう。
→ 対策:「キーワードは必ずマーク」して、図に反映させる。
- 典型パターンに頼りすぎる
「この形はこう解く」と思い込んで、別解や応用パターンに気づけない。
→ 対策:1問につき最低2通りの解き方を試す練習をしておく。
- 図形感覚だけで解こうとする
感覚で解くクセがつくと、複雑な補助線や数値的根拠が必要な問題に対応できない。
→ 対策:ノートに「なぜそう解けたか」理由を書く習慣をつける。
まとめ:図形問題集を「戦略的に使う」ことが合格への近道
- 計画的に取り組み、単元ごとの学習を段階的に進める
- 繰り返し学習と進捗チェックで弱点を見える化
- ミスを分析し、原因ごとの対策を立てる
図形問題は「才能より訓練」で差がつく分野です。自分に合った学習法で、着実に力を伸ばすことができれば、入試本番で大きなアドバンテージになります。
図形問題集を選ぶ前に知っておくべき注意点
図形問題集はただ「有名だから」「難しそうだから」で選んでしまうと、学習効果が薄れることもあります。ここでは、購入前に保護者が注意すべきポイントを具体的に紹介します。
価格と内容のバランスをチェック
問題集の価格帯とその内容の違い
図形問題集の価格帯はおおよそ 700円〜2,500円 と幅があります。価格が異なる背景には、掲載問題の質や量、解説の充実度、編集者の専門性などの違いがあります。
| 価格帯 | 特徴 | 向いている学習者 |
|---|---|---|
| 〜1,000円程度 | 基本的な問題中心/解説は簡素 | 入門レベル・苦手克服から始めたい子 |
| 1,000〜1,800円 | 問題のバリエーションが豊富/解説も図付きで丁寧 | 中級レベル・幅広い問題を解きたい子 |
| 2,000円以上 | 難関校対策向け/複数の解法や補助線の説明も豊富 | 応用力を高めたい子・上位層向け |
価格だけで判断せず、「その子の現状と目的」に合った構成かを見極めることが重要です。
どの出版社を選ぶべきか?信頼性の高い教材とは
出版社別の教材の信頼性と選び方
中学受験における信頼性の高い図形問題集を出版している主な出版社には、以下のような特徴があります。
| 出版社 | 特徴 | 主なシリーズ名 |
|---|---|---|
| 旺文社 | 解説が丁寧で基礎〜応用まで対応 | 『中学入試 でる順』シリーズ |
| 学研プラス | 図解や図形パズル的要素が豊富で楽しく学べる | 『ひとりでとっくん』シリーズ |
| 日能研ブックス | 難関校向けのレベルの高い問題が揃っている | 『予習シリーズ対応教材』 |
| 文英堂 | 教科ごとの学習習慣を整えやすい構成 | 『自由自在』シリーズ |
ポイントは、その出版社の教材がどのレベルに対応しているかを理解し、塾や家庭学習と連携できるかをチェックすることです。
図形問題集を使った学習でのよくある疑問とその解決方法
図形問題集を買っても、「うまく進まない」「他の科目と両立できない」など、学習の現場ではよくある悩みがつきまといます。ここでは、そんな疑問に具体的に答えていきます。
図形が苦手でも大丈夫?
図形に対する苦手意識を克服する方法
多くの子が図形を苦手に感じる理由は、以下のようなものです。
- 図が頭の中でイメージできない
- 補助線の引き方が分からない
- 解き方がパターン化されていない
こうした苦手意識を克服するためのステップは以下の通りです。
ステップ①:書いて覚える
図形は「見て覚える」のではなく「書いて理解する」ことが大切。ノートに図を写しながら考える習慣をつけましょう。
ステップ②:解説を声に出して読む
図形問題の解説は、文章+図解で理解が進みます。音読しながら図と照らし合わせると、脳の複数の回路を使えて定着しやすくなります。
ステップ③:図形のパターンをストック化
「平行四辺形の性質」「相似の利用」など、よく出るパターンをノートにまとめておくと、問題を見るだけで使う知識が自然に引き出せるようになります。
他の教科とのバランスをどう取るか?
図形学習と他の科目のバランスの取り方
中学受験においては、算数以外にも国語・理科・社会をバランスよく学ぶ必要があります。図形ばかりに時間を使いすぎるのもNGです。
1. 週の時間配分を決めておく
たとえば、1週間のうち:
- 算数全体に5日
- そのうち図形に2日
- 計算力強化に1日
- 残りの時間を国語・理科・社会へ
というふうに、あらかじめバランスを決めておくと学習の偏りが防げます。
2. 朝学習やスキマ時間を図形にあてる
短時間でも集中できる図形の練習(例:1問5分)を、朝食前や塾前の10分などに組み込むと、無理なく継続できます。
3. 他教科と図形を連動させる
例えば、理科の光の反射・屈折や、社会の地図記号などでも図形的な考え方が必要です。関連付けて学ぶことで、理解が深まりやすくなります。
まとめ:選び方・使い方次第で図形は得点源になる
- 問題集は「価格=質」ではなく、「レベルと目的」に合わせて選ぶべき
- 信頼できる出版社や教材で、効果的な反復学習がカギ
- 苦手でも学習ステップと習慣で克服可能
- 他教科とのバランスを意識した時間配分が重要
図形問題集の効果を最大限に引き出す学習環境とは?
図形問題の力を伸ばすには、問題集そのものの質だけでなく、どんな環境で、どんなスタイルで学ぶかも非常に重要です。
学習環境を整える:自宅学習のポイント
集中できる学習環境作り
図形問題は「図を頭の中でイメージする」力が求められるため、思考が途切れない静かな学習空間が効果的です。以下のような工夫が有効です。
- 机の上を整理整頓する
→ 消しゴムのカスやマンガ、余計な文房具は排除。A4の図形ノートと鉛筆、定規、分度器だけを置く。 - タイマーを使って集中時間を意識
→ 20~30分で区切る「ポモドーロ学習法」が効果的。 - 正面に時計を置き、時間管理意識を育てる
- できれば家族が一緒に読書などをして静かな雰囲気を作る
図形学習は特に集中力が求められるため、「静かさ」「時間管理」「道具の最適化」がカギになります。
図形問題集を使ったオンライン学習の活用法
オンラインサポートや動画解説の活用法
自宅学習で図形が苦手な場合は、オンライン教材や動画解説を併用することで理解が加速します。
おすすめの活用法:
- YouTubeの中学受験算数専門チャンネルを見る
例:スタディアップ、花まる学習会チャンネルなど - タブレット教材(例:RISU算数、Z会タブレットコース)で図形演習+動画解説
- 図形に特化した講座(例:四谷大塚・早稲田アカデミーのWeb講座)
動画やオンライン授業では、補助線の引き方や面積・角度の考え方を“動き”で確認できるのが大きなメリットです。特に図形の動き(回転、展開図など)は映像学習が効果絶大です。
中学入試で必要な図形の基礎知識
前述の問題集で勉強をはじめる前に、図形の基礎知識をおさらいしておきましょう。
基礎的な内容を先に復習しておくと、問題集で勉強をはじめたときにとても学習が進みやすくなります。
角度の基礎知識
まず、角度の基礎知識をおさらいします。
三角定規の角度
三角定規は二種類あります。二種類とも内角の角度が決まっているので、覚えておきましょう。
- 直角二等辺三角形:45°・45°・90°
- 半正三角形:30°・60°・90°
平行な2直線の対頂角・同位角・錯角
平行な2直線でつくる対頂角・同位角・錯角は同じ大きさです。
合同や相似、面積比などを求める問題でもよく使うので覚えておきましょう。
体積・面積の求め方(公式)
基本的な平面図形・立体図形の体積や面積の求め方をまとめました。
しっかり覚えておきましょう。
| 平面図形の種類 | 面積の求め方 |
| 三角形 | 底辺×高さ÷2 |
| 四角形 | たて×横 |
| 台形 | (上底+下底)×高さ÷2 |
| ひし形 | 対角線×対角線 |
| 立体図形の種類 | 体積の求め方 | 表面積の求め方 |
| 柱体 | たて×よこ×高さ | 底面の周りの長さ×高さ+底面積×2 |
| すい体 | たて×よこ×高さ÷3 | (展開図にして面の面積をすべて足す) |
| 円柱 | 底面積×高さ | 底面積×2+底面の円周×高さ |
| 円すい | 底面積×高さ÷3 | 側面のおうぎ形の面積 (母線×母線×3.14×中心角/360°) + 底面積(半径×半径×3.14) |
合同・相似の条件
三角形の合同条件3つ、相似条件3つも覚えておきましょう。以下にまとめました。
三角形の合同条件
- 3組の辺が、それぞれ等しい。
- 2組の辺と、その間の角がそれぞれ等しい。
- 1組の辺と、その両端の角がそれぞれ等しい。
三角形の相似条件
- 3組の辺の比が、それぞれ等しい。
- 2組の辺の比が等しく、その間の角が等しい。
- 2組の角が、それぞれ等しい。
図形と比の基本原則
比を使って解く図形の問題はとても多いです。
特によく使うのが以下の基本原則です。3つとも覚えておきましょう。
- 高さが同じ2つの三角形では、底辺の比が面積の比になる
- 底辺が同じ2つの三角形では、高さの比が面積の比になる
- 相似な2つの図形では、面積比=線分比×線分比
※関連記事:【中学受験】「比」の解き方:苦手克服のコツ
図形問題集選びのQ&A
Q1. 問題集は何冊購入すればよいのか?
答え:目的に応じて「3冊前後」が目安です。
内訳は以下の通り:
| 用途 | 問題集のタイプ | 数 |
|---|---|---|
| 基礎固め | 入門レベルで図形のルールを学ぶ | 1冊 |
| 実践演習 | 中学受験頻出問題を収録 | 1冊 |
| 応用挑戦 | 難関校レベルや特殊図形問題 | 必要に応じて1冊 |
多すぎると完遂できず逆効果。1冊を3回繰り返す方が、3冊を1回ずつ解くより効果的です。
Q2. 図形の解法を速く覚えるコツは?
答え:「図形パターンノート」を作ることです。
やみくもに問題を解くより、以下のステップを意識してください。
- 出題された図形の「分類」を明確にする
例:相似・補助線・回転・展開図・角度計算など - 問題を解いたら、「図+考え方+ポイント」を1ページに整理する
- 毎週2〜3回見直して、頭の中に定着させる
こうすることで、図形を見ると「どのパターンか」が即座にひらめくようになります。
Q3. 図形問題集を使ってどれくらいの期間で実力がつくのか?
答え:通常は3ヶ月〜6ヶ月で成果が見え始めます。
ただし、効果が出るかどうかは「継続」と「復習」によります。
- 週に2〜3回、図形の演習時間を確保
- 1冊を2〜3周しながら復習→アウトプット重視
- できなかった問題にふせんを貼り、“自分専用の苦手対策帳”に
1日15分でも、半年間続ければ100時間近い演習量になります。反復が何よりの実力アップの鍵です。
図形の問題を解くコツ
中学入試では、単純に公式を当てはめれば解けるような図形問題はほぼ出てきません。応用問題ばかりです。
応用問題と聞くと苦手意識を持ってしまうかもしれませんが、図形の応用問題は解き方のコツさえ分かれば、同じような解き方をする問題が多いです。
補助線を引く
問題用紙に図形が描かれていることが多いです。大抵の問題では、そのままでは正解にたどりつけないようになっています。
補助線を引いて、図形の定理を使える箇所がないか探します。
よくあるのが、いびつな形の四角形に補助線を引いて高さか底辺の同じ三角形を2つつくるパターンです。
高さか底辺の同じ三角形が2つできると、前述の「図形と比の基本原則」が使えます。
また、このように解く問題では相似比もセットでよく使います。
図形を移動させて正多面体にする
円の切れ端のような図形や三角形の一部を切り分けられた図形の面積を求めるような問題では、切れ端を移動させて正多面体や円にすることができます。
すると、あとは公式を当てはめてすっきり解けます。
図形を切り分けて正多面体や二等辺三角形にする
上記の方法とは逆に、1つのいびつな形の図形が出てきたら切り分けてみましょう。
正多面体や二等辺三角形、直角三角形をつくりだして解くことができます。
試行錯誤する
図形の問題は試行錯誤が大切です。
図形を見てすぐどこに補助線を引くか、どこを切断すれば良いかが分からない問題も多いです。
正多面体になるところはないか、二等辺三角形になるところはないかなど、解きやすい形になりそうな箇所を探しましょう。
パズル教材を使う
立体図形でイメージしづらい場合はパズル教材もおすすめです。
以下のパズル教材は学研が作成した、中学受験生向けのものです。

立方体の切断の攻略 (受験脳を作る)
※関連記事:中学受験算数で図形を得意にできるおすすめパズル教材
まとめ:中学受験の図形問題を制するために最適な問題集と学習法
図形問題を攻略するための総括
図形問題は「センス」ではなく「習慣」で得点源になります。
最後に、問題集選びと学習法のチェックポイントを確認しましょう。
問題集選びのポイント
- 難易度が子どもに合っているか
- 解説が図付きでわかりやすいか
- 一冊で完結するのか、補助教材が必要か
効果的な学習法のポイント
- 毎週のスケジュールに「図形演習」の時間を明確に入れる
- 苦手な問題をふせんやノートでストックし、見直しを習慣化
- 動画やタブレット教材も必要に応じて活用
図形は、攻略すれば中学受験における“差がつくポイント”です。
問題集は「量」より「質」と「継続性」。自分のスタイルに合った一冊を、丁寧に使い倒すことが合格への近道です。
※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法



コメント