大学入試では 小論文 や 作文 を課す大学が多くありますが、「何が違うの?」と疑問に思う人もいるでしょう。
小論文は 論理的に考え、主張を展開する文章、作文は 感情や経験を表現する文章 という点が大きな違いです。
この記事では、小論文と作文の違いを詳しく解説し、大学入試で求められる 書き方のコツ も紹介します。
入試対策におすすめの参考書も紹介しているので、ご参考ください。
なお、中学受験や高校受験の作文の書き方については、以下の記事でくわしく解説しています。
※関連記事:【中学受験】作文の書き方やルール
※関連記事:【高校受験】作文・小論文の書き方(模範解答付き)
小論文と作文の違い
小論文と作文はどちらも「テーマに沿って書く」という点で共通しています。それぞれ下記のような文章のことです。
小論文は「意見」、作文は「感情」を伝える文章です。
参考:
小論文と作文の違いは?それぞれの重要ポイントを解説 – AOI
小論文とは?書き方や作文との違いを解説 – マナビジョン
小論文とは?論理的思考力が求められる文章
小論文とは、あるテーマに対して論理的に意見を展開する文章のこと です。単なる感想ではなく、「なぜそう考えるのか?」を明確にしながら、説得力のある論を展開します。
小論文の基本構成
- 主張(結論):筆者の意見を明確に示す
- 論拠(理由):なぜその主張が成り立つのかを説明する
- 具体例(証拠):事実やデータ、事例を用いて論拠を補強する
- 結論:主張を再確認し、論を締めくくる
小論文では 「論理性」「客観性」「説得力」 が重要視されます。
作文とは?感想や経験を表現する文章
作文は、個人の体験や感想を表現する文章 です。論理的な主張ではなく、感情や経験を読者に伝えることが目的になります。
作文の基本構成
- 体験談や感情を表現する:自分が感じたことや経験をもとに書く
- 自由な構成が可能:起承転結やテーマに沿った自由な書き方ができる
- 読み手に共感を与えることが重要
作文では 「表現力」「創造性」 が評価のポイントになります。
小論文と作文の違いを表で比較!
| 項目 | 小論文 | 作文 |
| 目的 | 主張を論理的に展開する | 自分の考えや感情を表現する |
| 構成 | 主張・理由・具体例・結論 | 起承転結または自由な構成 |
| 必要なスキル | 論理的思考・資料分析 | 表現力・感受性 |
| 試験での評価基準 | 論理性・客観性・説得力 | 表現力・創造性 |
これらの違いを、例文を使いながら「書き方」「目的」「構成」「オリジナリティ」の4つの観点から説明します。
文章の書き方の違い
まず、文章の書き方が異なっています。下記のとおりです。
- 小論文:自分の意見に読み手が納得できるように、理由や根拠を明確に書く
- 作文:自分の感情に読み手が共感できるように、そのときの状況をさまざまな表現方法で書く
書き方の違いを例文で説明
以下の例文で書き方の違いをご確認ください。
【テーマ:学校生活における友人関係】
小論文:
学校生活において友人関係は重要だ。
なぜなら信頼できる友人を持つ人は充実した学校生活を送る傾向にあるからだ。
作文:
これまでの3年間を振り返って、信頼できる友人がいたおかげで充実した学校生活を送ることができたと感じる。
勉強が上手くいかず落ち込んでいたとき、ある友人の言葉に救われた経験がある。普段は冗談ばかり言っていた友人なのに、このときばかりは真顔で私の目を真っすぐ見つめて励ましてくれた。
上記のように、小論文は「シンプルで、言いたいことがすぐ伝わるような書き方」をします。
対して作文は、「落ち込んでいた」「救われた」のような感情を入れた書き方をします。
文章の目的の違い
「意見」を伝えるのか、「感情」を伝えるのかで文章の目的にも違いがあります。
こうした目的の違いから、小論文では「客観性」が重要で、作文では「主観性」が重要です。
文章の目的の違いを例文で説明
以下の例文で目的の違いをご確認ください。
【テーマ:学校生活における友人関係】
小論文:
学校生活において友人関係は重要だ。
学生を対象にした調査で、「信頼できる友人がいる」と回答した人の9割は学校生活に「充実を感じる」と回答していた。ところが、「信頼できる友人がいない」と回答した人のうち「充実を感じる」と回答した割合は3割に過ぎなかったことが分かっている。
この理由から、私は学校生活において友人関係は重要だと考えている。
※注:調査結果は架空の内容です
作文:
これまでの3年間を振り返って、信頼できる友人がいたおかげで充実した学校生活を送ることができたと感じる。
私には仲の良い友人がいる。いつも冗談ばかり言って笑いあっていた。
あるとき、私は勉強が上手くいかず落ち込んでいた。そんな私の様子をみてその友人は、真顔で私の目を真っすぐ見つめて励ましてくれた。自信を失って目の前が真っ暗になったと感じていたが、この友人の一生懸命なまなざしに私は明るい光を感じられるようになった。
今後は落ち込んでいる友人がいたら、私が励まして元気づけてあげたいと思っている。
小論文は「読み手に賛同してもらうこと」が目的なので、「論理性」や「客観的な根拠」が重要です。上記の例では、架空の調査結果で根拠を示しています。
一方、作文は「読み手に感情を伝えること」が目的なので、「そのとき自分がどう感じたか」「今後自分がどうしていきたいと思っているか」という主観を書いています。
構成の違い
目的の違いは文章の構成の違いにもつながります。
大まかには、小論文は3部構成(序論→本論→結論)です。ですが、細かくみると以下のような違いがあります。
なお、各パートの字数目安も合わせて以下にお伝えします。
序論/起:10%
本論/承と転:70%
結論/結:20%
導入部分は10~15%ほど、本論やメインパートは70%ほど、最後の締めは15~20%ほどの字数にします。
この数字は厳密なものではなく、あくまで目安です。この目安に沿って書くと高得点の小論文・作文を書きやすいです。
文章の構成の違いを例文で説明
以下の例文で公正の違いをご確認ください。
【テーマ:学校生活における友人関係】
小論文:
学校生活において友人関係は重要だ。(序論:意見の主張)
学生を対象にした調査で、「信頼できる友人がいる」と回答した人の9割は学校生活に「充実を感じる」と回答していた。ところが、「信頼できる友人がいない」と回答した人のうち「充実を感じる」と回答した割合は3割に過ぎなかったことが分かっている。(本論:根拠付き)
この理由から、私は学校生活において友人関係は重要だと考えている。(結論:意見の再度主張)
※注:調査結果は架空の内容です
作文:
これまでの3年間を振り返って、信頼できる友人がいたおかげで充実した学校生活を送ることができたと感じる。(起:これから書く内容のあらまし)
私には仲の良い友人がいる。3年間同じクラス、同じ部活に所属して、いつも冗談ばかり言って笑いあっていた。(承:状況説明)
あるとき、私は勉強が上手くいかず落ち込んでいた。そんな私の様子をみてその友人は、真顔で私の目を真っすぐ見つめて励ましてくれた。自信を失って目の前が真っ暗になったと感じていたが、この友人の一生懸命なまなざしに私は明るい光を感じられるようになった。(展:話の転換と発展)
今後は落ち込んでいる友人がいたら、私が励まして元気づけてあげたいと思っている。(結:全体のまとめ、今後の展望)
上記のように、小論文では序論→本論→結論と書きます。序論と本論は同じ内容です。
一方、作文では上記のように起→承→転→結の4部構成から「承」と「転」をまとめて3部構成にして書きます。「起」と「結」の内容は違っていることが多いです。
オリジナリティの違い
文章の目的や構成の違いから、書き方の「オリジナリティ(自由度)」にも違いが出ます。
オリジナリティの違いを例文で説明
以下の例文で公正の違いをご確認ください。
【テーマ:学校生活における友人関係】
小論文:
学校生活において友人関係は重要だ。
学校は勉学の場であり、友人の存在は必ずしも必要ではないという意見もある。しかし、学生を対象にした調査で、「信頼できる友人がいる」と回答した人の9割は学校生活に「充実を感じる」と回答していた。ところが、「信頼できる友人がいない」と回答した人のうち「充実を感じる」と回答した割合は3割に過ぎなかったことが分かっている。
この理由から、私は学校生活において友人関係は重要だと考えている。
※注:調査結果は架空の内容です
作文:
これまでの3年間を振り返って、信頼できる友人がいたおかげで充実した学校生活を送ることができたと感じる。
私には仲の良い友人がいる。3年間同じクラス、同じ部活に所属して、いつも冗談ばかり言って笑いあっていた。
あるとき、私は勉強が上手くいかず落ち込んでいた。そんな私の様子をみてその友人は、真顔で私の目を真っすぐ見つめて励ましてくれた。自信を失って目の前が真っ暗になったと感じていたが、この友人の一生懸命なまなざしに私は明るい光を感じられるようになった。
今後は落ち込んでいる友人がいたら、私が励まして元気づけてあげたいと思っている。
上記の例を説明すると、小論文では、「友人関係は重要だ」という自身の意見を「明確に」述べます。「重要だと思います」「重要なときもあります」といった曖昧な表現はNGです。
さらに、「友人関係は重要ではない」という意見も紹介し、その意見に対する反論を述べています。最後に改めて「従って/この理由より」と付けて自身の主張をもう一度述べます。
これは小論文の定型文で、オリジナリティはありません。内容が同じなら誰が書いても書き方にそれほど違いは出ません。
一方の作文はオリジナリティが重要なので、同じ内容でも書く人によって書き方が変わります。
「勉強のことで落ち込んでいる様子」をもっとリアリティあふれる書き方にする人もいるでしょうし、友人関係がいかに「笑顔であふれていたものだったか」をもっと増しましで書く人もいるでしょう。
どれが正解ではなく、「どのように感情を伝えたいか」で大きく変わります。
大学入試で求められる小論文の書き方
小論文の書き方を簡潔に説明します。
小論文の基本構成(序論・本論・結論)
- 序論:テーマの説明と主張の提示
- 本論:論拠を示し、データや事例を交えて論理的に展開
- 結論:主張を再確認し、今後の展望を示す
論理的に書くための3つのポイント
- 主張と論拠を明確にする(「なぜそう考えるのか?」を明示)
- 具体例やデータを活用する(事実を基に説得力を高める)
- 文章を簡潔にする(冗長な表現を避け、わかりやすく伝える)
まとめ
- 序論・本論・結論 の流れを守る
- 論理的な主張と論拠 をセットで書く
- データや具体例を活用 して説得力を高める
大学入試での作文のポイントとは?
大学入試で作文が出題される場合、ポイントは以下のようになります。
作文の基本構成(起承転結or自由構成)
- 起承転結型(物語的な流れがある場合)
- 自由構成(テーマに沿って自由に書く場合)
表現力を高めるための3つのポイント
- 具体的な体験やエピソードを入れる(抽象的になりすぎない)
- 感情表現を工夫する(読み手に共感を与える)
- 読みやすい文章にする(適切な段落分けと接続詞の活用)
まとめ
- 作文は 自由な表現 が可能だが、構成を意識する
- 体験や感情表現を活用し、読み手に伝わる文章を意識する
- 「表現力」が評価される ことを忘れずに
小論文と作文、どちらが大学入試で必要?
大学入試で小論文が出題されるケース
- 医学部・法学部・教育学部などの推薦・AO入試
- 社会科学・人文学系の一般入試
特に、総合型選抜や医学部の後期試験では小論文がよく出題されます。
なお、医学部小論文の書き方については以下の記事でくわしく解説しています。
医学部小論文のテーマ・書き方・おすすめ参考書を徹底解説!合格するための対策法とは?
また、総合型選抜と学校推薦との違いを以下の記事でくわしく解説しています。
【推薦入試】学校推薦型選抜とは:総合型選抜や一般選抜との違い、推薦をもらうための方法を解説
作文が出題されるケース
- 一部の私立大学や短大の入試
- 推薦入試や面接対策としての課題
まとめ
- 大学入試では小論文がメイン(論理的思考力を評価)
- 作文は 推薦入試や特定の学部 で出題されることがある
- 志望大学の試験形式を事前にチェック することが重要
まとめ|小論文と作文の違いを理解し、大学入試に備えよう!

覚えておくべきポイント
- 小論文は 論理的思考 が求められる(主張・論拠・結論)
- 作文は 表現力 が重要(体験・感情表現)
- 大学入試では小論文が主流 で、推薦入試などで作文が出題されることもある
原稿用紙の使い方
入試では小論文や作文の回答を原稿用紙に書くことも多いです。
原稿用紙の使い方を知っておけば、「減点されにくい回答」を書きやすくなります。
入試ではタイトルを書かない
学校の宿題で原稿用紙に作文を書く場合、タイトルを書くのが普通です。
ですが、入試ではタイトルは書きません。本文からいきなり書きはじめます。
各段落のはじめの1マスは空ける
各段落のはじめの1マスは空けて書きます。
前述のようにタイトルなしで本文から書きはじめるので、最初の1マス目は空けておきましょう。
句読点の書き方
「、」や「。」の書き方にはいくつかルールがあります。
まとめて紹介します。
1マス使う
まず、句読点には1マス使います。
マスの右上に書きます。
行の始めに書かない
また、行の始めのマスには句読点を書きません。
必ず、行の途中か最後に書きます。
行の最後は文字と一緒に書く
行の最後のマスに文字を書く場合、句読点はその文字と同じマスに書きます。
「~だった。」の「た」で行が終わる場合、最後の1マスに「た。」と書きます。
またこの場合、句読点はマスの右下に書きます。
小さい「ゃ・ゅ・ょ」「っ」の書き方
小さい「ゃ・ゅ・ょ」「っ」も1マス使います。
句読点と同じく、マスの右上に書きます。
ただし、行の始めに小さい「ゃ・ゅ・ょ」「っ」を書いても大丈夫です。行の最後にほかの文字と一緒に書いても大丈夫です。
「~しちゃった。」と書くケースで、行の最後のマスに「ちゃ」と書いても、最後のマスに「ち」で次の行頭に「ゃ」を書いてもOKです。
かっこの書き方
原稿用紙で使うかっこには2種類あります。それぞれの使い方は以下のとおりです。
大学推薦入試対策におすすめの小論文の参考書
高校生向けに、大学入試対策におすすめの小論文の参考書を紹介します。
『何を準備すればいいかわからない人のための 総合型選抜・学校推薦型選抜』
最初に紹介するのは総合型選抜・学校推薦型選抜の解説からしてくれている小論文問題集です。
小論文をはじめて書く人、推薦入試で必要になり何をどうすれば良いか知りたい人向けです。
総合型選抜とは何か、学校推薦型選抜とは何か。小論文はどう書けば良いかが書かれています。

何を準備すればいいかわからない人のための 総合型選抜学校推薦型選抜(AO入試…
出版社:KADOKAWA
『改訂版 何を書けばいいかわからない人のための 小論文のオキテ55』
こちらは小論文の書き方をイチから解説してくれている参考書です。
小論文と作文の違いなど、小論文を書くにあたって知っておくべき内容にはじまり、「資料型小論文」では資料のどこを見れば小論文を書けるかといった「入試で役立つコツ」をたくさん紹介しています。
練習問題は少ないので、最初に読んだら別問題集で練習をし、ときどき「これってどうだったかな?」と気になったときに戻るようにしましょう。

改訂版 何を書けばいいかわからない人のための 小論文のオキテ55
出版社:KADOKAWA
まとめ
いかがでしょうか。
高校生向けに小論文と作文の違いを説明しました。
大学入試では小論文や作文を書く問題がよく出てきます。小論文は意見を伝えるので客観的に書き、作文は感情を伝えるので主観的な書き方をします。
小論文・作文は入試で高得点を取って逆転合格をねらえる重要なパートです。違いを理解して対策しやすくため例文もつけているので、ぜひご参照ください。
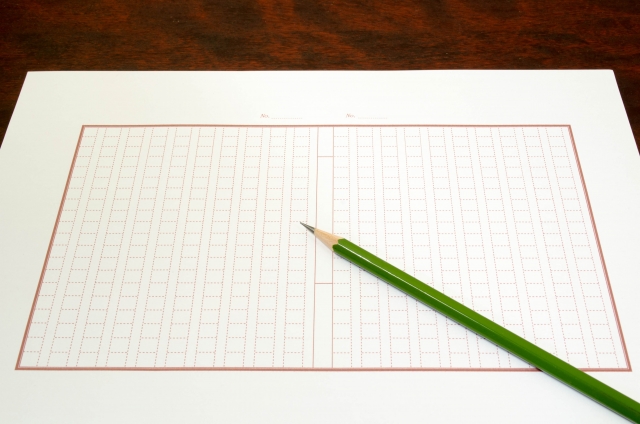


コメント