「国語がどうしても伸びない」「なんとなく読んでいて点数に結びつかない」──中学受験を目指す中で、国語に苦手意識を持つお子さんは少なくありません。
特に語彙力・読解力・記述力といった力は一朝一夕には身につきにくく、成績が停滞しやすい教科でもあります。
そこでこの記事では、国語が苦手な子どもによく見られる特徴や原因を丁寧に分析し、家庭でできる効果的な対策法やおすすめ問題集までを完全ガイドとしてまとめました。
保護者の方が「今すぐできるサポート」も紹介していますので、「うちの子、国語が心配…」と感じている方は、ぜひ最後までご覧ください。
※なお、理科や社会の苦手克服法は以下の記事でくわしく解説しています。
【保存版】中学受験「社会」の最強勉強法(地理、歴史、公民)
中学受験理科の勉強法を完全ガイド:苦手になる理由と対策、学習計画の立て方など徹底解説
※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。
Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法
中学受験で「国語が苦手」と感じる子どもが多い理由
塾で勉強をがんばっているのに国語が苦手な中学受験生は多いです(リセマムより)。
中学受験生が国語で苦手になる理由はさまざまです。まず、具体的な理由を見極めることが重要です。
考えられる理由を以下にまとめました。
国語の成績が上がりにくい本当の原因
語彙力・読解力の不足
一般的に、小学生の平均的な語彙数は約1万語、中学受験に必要な語彙数は2~4万語と言われています。
中学受験の国語は、「ただ文章を読めば解ける」というレベルではありません。
語彙力(言葉の意味や使い方の知識)と、
読解力(筆者の主張や登場人物の気持ちを的確に読み取る力)が問われます。
たとえば、「皮肉」「客観的」「矛盾」など抽象的な語彙が文章中に出てきても、意味が理解できなければ文章の意図もつかめません。
また、説明文では「因果関係」や「対比構造」に気づけないと、設問に正しく答えることが難しくなります。
さらに、物語文では登場人物の「心理の変化」を読み取ることが求められますが、語彙力が乏しいとその変化に気づけず、「なんとなく読んでなんとなく答える」状態になり、点数が安定しない原因となります。
「読み飛ばし癖」や集中力の課題
国語の文章は長文であることが多く、設問も細かく設定されているため、集中力を持続させる力が求められます。しかし、国語が苦手な子の中には、途中で飽きてしまい、読み飛ばす癖がついてしまっているケースが多く見られます。
たとえば、段落の最初と最後しか読まない、設問の「聞かれていること」をしっかり読まずに答えてしまうなど、「注意力不足」や「雑な読み方」が定着してしまっていると、得点につながる読み方ができません。
このような読み方では、本文の大事な根拠や筆者の主張を見落とすため、記述問題や選択肢問題で正答率が下がります。
記述問題への苦手意識
中学受験の国語で厄介なのが、「記述問題」です。
これは「答えが一つではない問題」であり、文章中の情報を整理して、自分の言葉で「正しく」「簡潔に」まとめる力が求められます。
しかし、国語が苦手な子は、以下のような悩みを抱えていることが多いです。
- 何を書けばいいのか分からない
- 書き出し方が分からない
- 答えの根拠を本文から探せない
- 字数制限の中でうまくまとめられない
これらはすべて、「答え方の型」や「根拠の探し方」が身についていないことが原因です。そのため、「記述=苦手」「空欄で出すしかない」という心理的な壁ができてしまい、結果的に国語全体への苦手意識が強くなるのです。
国語が「勉強のやり方が分かりにくい科目」と言われる理由
算数や理科は、「公式を覚える」「問題のパターンを反復する」など、勉強法が明確です。しかし、国語は「文章を読んで理解する」という曖昧な行動が中心で、明確な勉強手順が見えにくいため、子どもも保護者も「どう勉強したら成績が上がるのか」が分かりにくいと感じます。
さらに、間違った選択肢を選んでも「なぜ間違ったのか」が分かりにくく、復習の仕方も曖昧になりがちです。記述問題では、模範解答との違いが「正解・不正解」の線引きにならず、どこを直せばよいのかが見えないことも多いです。
このように、「感覚任せ」「なんとなく」で解いてしまう子どもが多くなりやすく、結果的に点数が伸びにくい=苦手意識が強くなるという悪循環に陥るのです。
塾でがんばっているのに国語が伸びづらい理由
塾の授業が知識分野偏重
中学入試国語を得意にするには、知識・長文読解・記述をセットにして勉強する必要があります。
ところが一部の塾、あるいは一部の国語講師は長文読解を授業であまり扱いません。
漢字や語句の意味などの知識分野の対策に大半の時間を回しています。
その結果、知識問題は高得点を取れるのにほかのタイプの問題を苦手にしてしまう子が多く発生してしまいます。
テクニック偏重の解答
塾の授業では「解答テクニック」を教わります。本文中にある言葉と設問の選択肢を照らし合わせるなどの方法です。
国語の点数を安定させるために必要なテクニックですが、テクニックを重視するあまり、本文内容を読み取ろうとしなくなる子も多いです。
学年が上がるにつれてテクニック偏重では解きづらい題材や出題構成が増えてくるため、テストの点数が下がってきます。
このように、国語は「塾でがんばっていれば自動的に成績が上がる教科」ではないとも言えます。
国語が苦手な子どもに共通する特徴と家庭で気づけるサイン
中学受験において国語が苦手な子どもには、共通した行動や思考の傾向があります。こうしたサインに早く気づくことで、保護者が適切なサポートをし、子どもの苦手意識を軽減することが可能です。
「なんとなく読んでる」子どもの特徴
国語が苦手な子どもに多く見られるのが、「本文をなんとなく読んでいるだけ」という状態です。これはつまり、文章の内容を深く理解せずに雰囲気で読んでいるということです。
家庭で見られる具体的なサイン
- 「読んだ?」と聞くと「うん」と即答するが、内容を説明できない
- 問題に対して「なんとなくこっちが正解っぽい」と答える
- 説明文のキーワード(たとえば「つまり」「一方で」など)に無頓着
- 物語文で人物の気持ちや変化に関心がない
このような子は、読み取るべき要点を押さえておらず、設問に対する根拠のある答えが出せない傾向があります。読書習慣があっても、内容を深く理解する読み方ができていないケースもあるため注意が必要です。
「解き方を説明できない」=理解できていないサイン
家庭で保護者ができる簡単なチェック方法のひとつが、「どうしてその答えにしたの?」と聞いてみることです。
答えの根拠を自分の言葉で説明できない場合、それは理解していないか、考えずに選んでいる可能性が高いです。
よくある反応
- 「なんとなく…」
- 「前に同じようなのが出たから」
- 「一番短かったから」
これは、本文中の根拠を見つけ出す力が弱い、あるいは設問の意図をつかめていない証拠です。国語の成績を上げるには、選んだ答えの「理由」を自分で言語化できるようにすることが重要です。
ポイント
- 記述問題でも「なぜそう思うのか」を説明できない場合は要注意
- 解答を選ぶ「プロセス」が曖昧=再現性がない=安定して点が取れない
「答え合わせが雑」=伸び悩みの原因
国語に限らず、復習・答え合わせのやり方は成績向上に直結します。ところが、国語が苦手な子どもほど、答え合わせの段階で以下のような行動が見られます。
よくある行動
- 答えが違っていても「まあいっか」と流す
- 解説を読まない、読んでも理解しようとしない
- 自分の答えと模範解答の違いを比べない
- すぐに次の問題に進んでしまう
こうした「雑な答え合わせ」では、間違いの原因分析ができず、同じミスを繰り返すことになります。特に記述問題では、なぜその表現では不正解なのか、どこをどう直せば得点になるのかを考える習慣が不可欠です。
家庭での対策
- 「なぜ間違ったのか」を一緒に考える習慣をつける
- 模範解答と自分の答えの違いをチェックさせる
- 間違いノートや気づきメモを作成して見える化する
このように、家庭でも子どもの「読む姿勢」「答える思考」「復習の質」を観察することで、国語の苦手傾向を早期に察知することが可能です。
国語が苦手な中学受験生のための克服法【プロ講師が徹底解説】
中学受験において「国語が苦手」と感じる子どもは少なくありません。しかし、国語は正しい方法でトレーニングを積むことで、確実に伸びる科目です。
ここでは、プロ講師が実践する効果的な克服法をテーマ別に解説します。
※なお、国語の読解テクニックについて、以下の記事でくわしく解説しています。
中学受験国語の読解テクニック
語彙力を高めるトレーニング
語彙力はすべての読解の土台です。語句の意味を知らなければ、文章の内容も設問の意図も理解できません。毎日の積み重ねで語彙は着実に増やせます。
「意味調べノート」の活用法
苦手克服に効果的なのが、「意味調べノート」の活用です。
- 長文読解や語彙問題でわからなかった言葉を1冊にまとめる
- 意味だけでなく、例文を自分で作ることで語感が身につく
- 時々復習し、定着を図る
この方法は、ただ調べて終わるのではなく、使える語彙として自分のものにする訓練になります。親子で一緒に意味を考えるのも効果的です。
日常で使える語彙を意識する方法
語彙力は机の上だけでなく、日常会話の中でも育てられます。
- 新聞・ニュース・読書の中で「今の言葉、どういう意味?」と問いかける
- 家族の会話で学んだ語彙を意識的に使わせる
- 「〇〇ってどんなときに使う?」という会話型トレーニングを実施
こうした環境づくりによって、子どもは自然に語彙を増やし、「読める・話せる・書ける」力へとつなげていきます。
以下のような図鑑を1冊リビングに置いておくと便利です。

「伝える力」が伸びる! 12歳までに知っておきたい語彙力図鑑
読解力を鍛える方法
国語が苦手な子の多くは、「文章を読んでも内容が頭に入らない」という共通点を持っています。ここから読解力を伸ばすには、段階的なトレーニングが有効です。
※なお、以下の記事で国語の読解力の伸ばし方をくわしく解説しています。
【保存版】中学受験 国語の読解力を劇的に伸ばす方法|プロ講師直伝の読解テクニック&おすすめ問題集
「音読」「要約」から始める
まずは「音読」と「要約」で文章全体の構造をつかむ練習をしましょう。
- 音読することで、文の切れ目や接続語に注意が向き、文章理解が深まる
- 要約は、大事な情報とそうでない情報を区別する訓練になります
- できれば親が聞き役・添削役になり、「なぜこの要約にしたのか?」と聞くとさらに効果的
特に説明文では、構成(問題提起→理由→具体例→結論)に注目させると理解が深まります。
論理的文章は対比させて読む
中学入試の論理的文章は大抵、対比を用いた文章が選ばれます。
あるテーマについて「筆者の主張」と「筆者の主張への反対意見」が表現され、それぞれの根拠も説明されています。
読み進めながら、段落ごとに「筆者の主張」「筆者の主張への反対意見」に分けるとかなり読みやすくなります。
文学的文章は事実と心情を時系列で追う
文学的文章は事実と登場人物の心情をそれぞれ時系列で追いながら(本文中に線を引きながら)読みましょう。
何らかの事実/事件が発生し、
それに対して登場人物が感情を抱きます。
その感情が原因となって人物が何らかの行動を取ります。
例えば下記のような具合です。
事実:友人が主人公との約束を破った
↓
感情:主人公が憤慨した
↓
行動:学校で友人に会っても主人公は目を合わさないようにした
文学的文章で問われるのは大抵、上記の「行動の理由」です。
「なぜ主人公は学校で友人に会っても主人公は目を合わさないようにしたのでしょうか?」のように問われます。
解答部分にあたるのが「事実」と「感情」です。
事実と心情を時系列で追うと行動の理由が分かりやすくなり、設問にも正答しやすくなります。
選択問題は消去法で解く
選択問題を苦手にしている人は多いですが、正しい選択肢を選ぼうとすると逆にむずかしくなります。
選択問題は消去法で解きましょう。
明らかに本文内容と違う選択肢を最初に消します。
つづいて、各選択肢の文言や内容が本文と合っているか比較し、「合っていない選択肢」を消していきます。
残った選択肢が正解の選択肢です。
「設問文の読み方」テクニック
問題文(設問文)を読み飛ばすクセがある子には、設問の読み方指導が重要です。
- 「〜はなぜですか?」「〜とはどういうことか?」など設問の型に注目させる
- 設問の主語と目的語を明確にする(例:「筆者が言いたいことは何か」→「筆者」に注目)
- 「答えの根拠は本文中のどこか」を意識させるため、線を引かせる習慣をつける
設問文自体がヒントであることを理解できれば、正答率はぐんと上がります。
※なお、以下の問題集を使うと国語の読解テクニックを短期間でマスターしやすいです。5-6年生向けです。

中学入試 国語 塾技100 (中学入試 塾技)
記述問題の苦手克服
記述式の問題は、中学受験で合否を分ける重要なポイントです。「何を書いたらいいか分からない」となる前に、書くための基本技術を身につけましょう。
「答えの根拠」を本文に線を引いて確認
- 記述の前に、まず「どこが答えのヒントになるか」を本文に線を引く練習をする
- 線を引いた箇所をもとに、自分の言葉でまとめ直すトレーニングをする
- 最初は口頭でもOK。「なぜこの文を選んだの?」と親が聞き役になる
本文と答えのつながりを明確にすることで、記述の土台ができていきます。
「書き出しパターン」を覚える練習法
「どう始めたらいいか分からない」子に有効なのが、記述の書き出しテンプレートを覚えることです。
例:
- 「〜からです。」
- 「筆者は〜と考えているからです。」
- 「私は〜だと思います。それは〜からです。」
まずはパターンを真似して書くところから始め、自信をつけていきましょう。慣れてきたら自分の表現にアレンジするよう促します。
※なお、以下の記事で国語の記述問題対策の仕方をくわしく解説しています。
【中学受験国語の記述対策】記述問題の書き方のコツや小学生が知っておきたい記述のルールを紹介
過去問と模試の活用法
国語が苦手な子こそ、過去問と模試を「分析ツール」として活用することが大切です。
- 「何の問題で間違えたか」を記録する(語彙/読解/記述などに分類)
- 解いた後は必ず「振り返りノート」をつけてミスの傾向を可視化
- 模試の記述は、他人の模範解答と比較し、「何が足りなかったか」を考察する
特に過去問では、「設問の意図を読む力」「制限時間内に読む訓練」が養われます。同じ学校の出題傾向を分析することで、対策も絞れるようになります。
保護者ができる国語サポートの具体策
国語は「何をどう勉強すればいいか分かりにくい科目」であり、子ども一人での習得が難しいこともあります。だからこそ、保護者の適切な関わりが、苦手克服のカギとなります。
ただし、「教える」ことよりも、「寄り添う」ことが効果的です。
一緒に問題を読む&考える「共読」のすすめ
「共読(きょうどく)」とは、子どもと保護者が一緒に文章を読み、内容や問題について会話をする学習法です。国語が苦手な子どもにとって、「読んだ内容を話す」ことは、理解を深める非常に有効な手段です。
共読のやり方:
- 子どもが読む本文を、保護者も一緒に音読または黙読する
- 「どんな話だった?」「この部分、どう思う?」と問いかける
- 記述問題では、「あなたならどう答える?」と会話形式で考えを引き出す
共読のメリット:
- 子どもが文章を“なんとなく読む”ことが減る
- 思考や理解の浅さに、保護者も気づきやすくなる
- 「一緒に考える」ことで、子どもが国語に前向きになりやすい
学習というよりも「親子の読書時間」という気持ちで取り組むと、子どもも緊張せずに話しやすくなります。
「国語が苦手=親の責任」ではない
国語が苦手だからといって、「もっと本を読ませておけばよかった」「話を聞いてあげられてない」と自分を責めてしまう保護者の方もいます。しかし、国語の苦手は“環境”より“方法”に原因がある場合がほとんどです。
国語の力は、算数のように「順を追って積み上げられる学力」ではありません。語彙、読解、記述など、複数の力がバランスよく必要とされるため、苦手が目立ちやすいだけなのです。
また、現代の文章(評論や資料文など)は日常生活で触れにくく、学校の勉強だけでは補えないケースも多いため、「苦手な子が多くて当たり前」と考えるくらいがちょうど良いです。
「親の自分も国語が苦手だったから仕方ない」と思わず、今からの関わり方で十分に変えられます。
「読書量を増やす」だけでは足りない理由
「国語に強くなるには読書をたくさんすればいい」とよく言われますが、読書だけで成績が上がるとは限りません。実際、読書好きな子でも記述問題が苦手なケースは珍しくありません。
その理由は以下の通りです。
読書の落とし穴
- 物語だけに偏った読書では、説明文・論説文の理解が育たない
- 「ただ読むだけ」では、文章の構造を捉える力や設問に答える力は鍛えられない
- 読んだ内容をアウトプットする機会がなければ、思考の深まりや表現力が養われにくい
読書を“国語力アップ”につなげるには
- 読んだ後に「どんな話だった?」と感想や要約を話してもらう
- 「この登場人物はどう思った?」「この場面でなぜこうしたの?」と問いかける読書にする
- 物語に加えて、新聞の子ども向けコラムや図鑑系の読み物も加えるとバランスがよくなる
つまり、読書は大切な土台ではありますが、読解力や記述力につなげるには“読むだけ”では不十分です。読んだ後の“対話”や“思考の整理”が、国語力の育成に直結します。
※なお、以下の本では、読解力を上げる方法をマンガで学ぶことができます。

マンガでわかる!読解力を10日で上げる方法 ~中学受験国語カリスマ講師直伝~
国語が苦手な中学受験生のための「1週間の国語対策プラン」
◆前提
- 毎日30〜60分を想定
- 学習効果を高めるため、必ず音読/要約/意味調べ/線引き/振り返りの習慣を組み込む
- 使用教材例:
- 『ふくしま式「本当の語彙力」が身につく問題集』
- 『出口汪の国語シリーズ』
- 『論理エンジン』や公立中高一貫校用の記述問題集
月曜日|語彙トレーニング+音読
- 【15分】意味調べノート(3語)を作成し、例文づくり
- 【15分】出口汪シリーズの短文読解を音読+要約(口頭でOK)
- 【15分】記述問題1問(記述の「書き出しパターン」を使って)
ポイント:意味調べ→使って覚えること。音読の最後に「今日の要約」を口で説明すると◎
火曜日|読解力強化+設問の読み方練習
- 【20分】長文読解(物語文)1題:線引き&設問を分析
- 【15分】設問文の読み方練習(どこを聞いてる?を明確に)
- 【10分】記述練習(自分の答えと模範解答を比較)
ポイント:「どこを聞いているか」赤ペンで書き込む癖をつけよう。
水曜日|語彙+短文記述力アップ
- 【15分】語彙問題+例文づくり(昨日と違うジャンルの語彙)
- 【20分】記述トレーニング2問(「根拠に線引き→書き出しパターン」の流れ)
ポイント:語彙は「知ってる」で終わらせず、「使える」に変えるのが大事。
木曜日|物語文読解+記述
- 【25分】物語文読解+記述問題(1題)
- 【10分】設問文の確認と本文の照らし合わせ
- 【10分】答え合わせと解答の見直し(どこがズレたか確認)
ポイント:感情の変化・場面転換などに印をつけながら読むと◎
金曜日|説明文読解+語彙+記述
- 【20分】説明文読解1題:要点を箇条書きでまとめる
- 【10分】語彙の復習(今週出た語句から3つピックアップ)
- 【10分】記述1問(本文に根拠線+書き出しパターン活用)
ポイント:説明文は「筆者の意見」と「理由・根拠」を意識して線引き。
土曜日|過去問または模試演習の日(週末演習)
- 【40〜60分】過去問または模試1題(時間を計って解く)
- 【20分】復習(設問の読み取り/線引き/記述の自己分析)
ポイント:復習こそ実力UPの鍵。「なぜその答えになるか」を言語化しよう。
日曜日|1週間の振り返り&読書+語彙
- 【10分】今週の記述や読解の間違いノートを見返す
- 【20分】好きな本の読書タイム+印象的な語句を3つ抜き出す
- 【10分】語彙ノートに追加・例文を作る
ポイント:知識の「定着」は日曜の振り返りで完成する。
補足アドバイス(保護者向け)
- 1日の終わりに「今日学んだことは?」と聞く習慣で、定着力がアップします。
- 「共読」(一緒に読む・考える)時間を週に1〜2回入れると効果絶大。
- 続けるコツは、「今日はこれだけできた!」の成功体験を言葉にすることです。
国語が苦手な子におすすめの問題集・教材【プロが厳選】
中学受験の国語対策では、市販の問題集・教材を正しく選ぶことが非常に重要です。ただし、「偏差値が高い教材=良い教材」ではなく、お子さんの現在の課題に合ったものを選ぶことが最大のポイントです。
ここでは、語彙・読解・記述の3領域別に、専門家が推薦する人気教材を紹介します。
※このセクションは以下のサイトを参考にしております。
アガルート「【中学受験】国語の問題集・参考書のおすすめ12選!読解力&記述力アップには?」
マイベスト「中学受験向け国語参考書のおすすめ人気ランキング」
ダイヤモンド教育Labo「中学受験の国語が苦手!?克服するための勉強法やおすすめ問題集・参考書を明利学舎の鈴木塾長が紹介!」
タイプ別に選べる!国語が苦手な子向け問題集
中学受験で国語が伸び悩む子の多くは、「語彙力」「読解力」「記述力」のいずれか、または複数に課題があります。 それぞれの課題に特化した教材を選ぶことで、弱点を効率的に補うことができます。
【語彙力UP】『ふくしま式「本当の語彙力」が身につく問題集』
- 対象学年:小学4~6年生
- 出版社:大和出版
- 特徴:語彙の「意味理解」と「使い方」に重点を置いた構成
国語が苦手な子に最も多い問題の一つが「語彙力不足」。この教材は単なる漢字や意味の暗記ではなく、文脈の中で言葉を使いこなす力を養えます。
例えば、「なぜこの語を使うのか」「他にどんな言い換えができるか」といった思考型の問題が多く、記述問題にもつながる語彙力の強化に効果的です。

ふくしま式「本当の語彙力」が身につく問題集[小学生版]
【読解力UP】『出口式 改訂版はじめての論理国語』
- 対象学年:小学1年〜6年(レベル別)
- 出版社:水王舎
- 特徴:論理的読解をわかりやすく解説、挿絵や図も豊富で理解しやすい
「なんとなく読む」「感覚で解く」国語から脱却するのに最適な教材です。出口汪氏の教材は、「筆者の主張」「理由」「具体例」など文章構造をつかむ力を段階的に養う設計になっており、論説文・説明文が苦手な子に特におすすめです。
また、解説も丁寧なので、家庭学習でも取り組みやすく、保護者も一緒に学びやすい点が高評価です。

改訂版 はじめての論理国語 小1レベル

改訂版 はじめての論理国語 小2レベル

改訂版 はじめての論理国語 小3レベル

はじめての論理国語 小4レベル

はじめての論理国語 小5レベル

出口式 はじめての論理国語 小6レベル
【記述力UP】『論理エンジン』や『アインストーン国語』
- 対象学年:小学5年生〜(論理エンジン)、5年〜(アインストーン)
- 出版社:水王舎、好学出版
- 特徴:構造的に「書く力」を育成する本格派教材
記述問題に苦手意識を持つ子どもには、「何をどう書けばよいか」という論理の型を学べる教材が有効です。『論理エンジン』は、「だから・しかし・たとえば」などの論理の接続を使った文章構成の指導が特徴的で、初学者でも段階的に記述力を高められます。

論理エンジン小学生版5年生: 読解・作文トレ-ニング

論理エンジン小学生版6年生: 読解・作文トレ-ニング
また、公立中高一貫校の適性検査で問われる記述問題の練習にも使える教材は、「意見を述べる」「根拠を明示する」訓練にも最適です。
中でも『アインストーン』は塾でも使える国語の読解・記述・作文の対策専用の問題集です。

好学出版 アインストーン 国語 2025年度版
おすすめの使い方と注意点
国語教材は「買ってやらせるだけ」では効果が出にくい科目です。以下のような使い方をすることで、効果が最大化します。
- 1日1ページ・10分程度で習慣化する(毎日少しずつが重要)
- 解説部分を親子で一緒に読む(考え方の理解を深める)
- 間違えた問題は、「なぜ間違えたか」を言語化させる
- 記述問題は丸つけ後に「他の言い方」も考えてみる(表現力が育つ)
また、苦手な子には「正解・不正解」にこだわらず、「考えた過程」に焦点を当ててフィードバックすることが大切です。
保護者のサポートで学習効果が倍増する理由
国語力は「一人で伸ばす」のが難しい力の一つです。保護者の声かけや共学習が加わると、教材の効果が格段に高まります。
学習効果を高める保護者の関わり方
- 「どうしてそう思ったの?」と聞く → 子どもの思考を言語化する訓練になる
- 「これはこういう言い方もできるね」と表現を補足する → 語彙や表現力が広がる
- 「一緒に考えよう」と取り組む姿勢 → 子どもが安心して学べる
とくに記述対策などは「自分の考えを説明する」必要があるため、家庭での“対話”がそのまま記述トレーニングになります。
中学受験で国語が得意科目になると得られる3つのメリット
国語は「センスの教科」ではなく、「論理的に読んで、考えて、答える」力をコツコツ育てることで、誰でも伸ばすことができます。
特に中学受験において、国語が得意になることは、単に1教科の得点源になる以上の大きなメリットをもたらします。
他教科の成績アップにもつながる
国語力=「読む力」「意味をとらえる力」「論理的に考える力」です。これらは、実は算数・理科・社会といった他の教科でも必須になります。
- 算数:文章題の条件整理、問題文の意図を正しく把握する力が求められます。
- 理科:実験の手順や観察結果の説明文を読み解く必要があります。
- 社会:資料の読み取り、長文問題への対応などで読解力がカギになります。
つまり、国語が得意になることで「他教科の文章も読みやすくなる」ため、全体的な成績の底上げにつながります。
合格可能性の高い志望校選びができる
中学受験では、学校ごとに出題傾向が異なり、国語の配点が高い学校も多く存在します。たとえば、開成・桜蔭・豊島岡・渋幕などの最難関校では、国語で差がつくケースが多く、合否を分ける科目とも言われます。
また、「国語が得意=安定して得点できる武器を持っている」という状態は、入試全体の戦略に余裕ができることにもつながります。 例えば、国語で高得点が見込めれば、他教科で多少苦手があっても、合格圏内に入る可能性が上がります。
※なお、6年生で志望校変更に悩んだときの対策について、以下の記事でくわしく解説しています。
中学受験で志望校を下げるべきか迷ったらどうすれば良いか|後悔しない判断軸と親子で納得する進路選び
論理的思考力が将来まで武器になる
中学受験の国語では、「なぜそう考えたのか」「根拠を示す」「相手に伝わる文章を書く」といった、論理的思考力や表現力が鍛えられます。
これは受験が終わっても、将来にわたって大きな財産となります。
- 中学校・高校での記述式テスト
- 大学受験の小論文・面接
- 社会に出てからの説明力・説得力
すべてにおいて、「読んで考えて伝える力」は活かされます。国語が得意になることは、一生使える武器を早くから身につけることに等しいのです。
まとめ|国語が苦手でも大丈夫!正しい勉強法で必ず伸びる
国語に苦手意識をもっている子でも、焦らず適切なステップを踏んで学習を重ねていけば、確実に力は伸びていきます。「できない」ではなく「やり方を知らないだけ」というケースが大半です。
焦らず、着実にステップを踏むことが成功のカギ
国語力は、ある日突然伸びるものではありません。「語彙力」「読解力」「記述力」それぞれを段階的に積み上げることが重要です。
- 初めは「語句の意味を調べる」「要約を練習する」など基礎から。
- 次に「設問文の読み方」や「答えの根拠探し」など応用へ。
- 最終的に「記述で自分の意見を書く力」へとつなげていく。
このように、正しい方法で取り組めば、国語は「苦手」から「得意」へと確実に変わります。
最終的に「読んで考える力」は一生の財産になる
中学受験をきっかけに身につけた国語力は、その後の人生で必ず役に立ちます。
- 本や新聞を理解できる
- 授業や講義の内容を正確に整理できる
- 自分の考えを論理的に伝えられる
これらは、将来、学問・仕事・人間関係すべてに影響する力です。
今の努力は、受験だけでなく、子どもの一生を支える力になります。
※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。
Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法
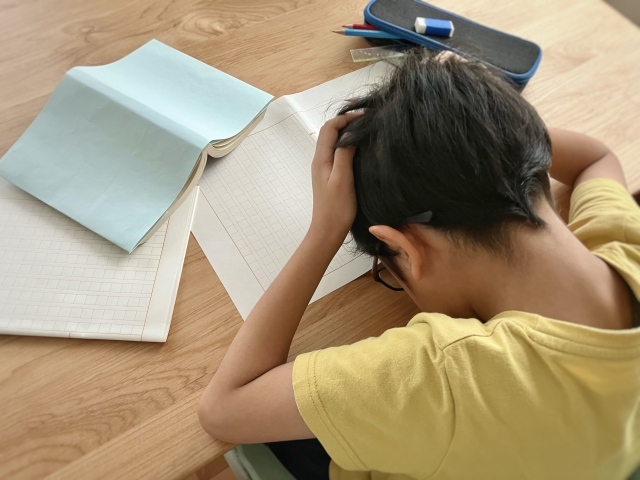


コメント