江戸時代の歴史は、将軍の交代や政治の改革、文化の発展などがぎっしり詰まっていて、テストや高校入試でもよく出題されます。でも、「どの順番だったっけ?」「誰が何をした人かごちゃごちゃ…」と苦手に感じていませんか?
この記事では、中学生向けにわかりやすく、江戸時代の年表を使って時代の流れを整理しながら、定期テストや入試に出やすい人物・出来事を徹底解説します。
記述問題の対策や一問一答のコツ、無料プリント付きの練習問題も用意しているので、この記事1本でしっかり実力アップが目指せます!
※なお、鎌倉時代や明治時代の年表や解説を以下の記事でしています。
鎌倉時代の年表
中学定期テスト必勝!明治時代の年表をマスターする5つのステップと明治時代のテスト頻出ポイント
- 中学生向けの江戸時代年表勉強法
- 江戸時代の分かりやすい年表
- 江戸時代の出来事と重要ポイントの解説
- 定期テスト・高校入試に出る江戸時代の人物ベスト14
- 江戸時代によく出る定期テスト・入試問題の傾向と対策
- 江戸時代の年表で流れをつかむ練習問題(無料プリント付き)
- 歴史の流れを学べる本・参考書
- まとめ
中学生向けの江戸時代年表勉強法
歴史のテストで高得点を取るには年表をみながら勉強するのがおすすめです。
年表を活用した勉強法を紹介します。
自分で歴史年表を作成する
江戸時代の出来事を理解するために、タイムラインを作成しましょう。時系列で出来事を整理することで、全体像をつかみやすくなります。
教科書や問題集に書いてある年表をそのまま活用しても大丈夫ですが、「自分で作成」すると歴史の流れを理解しやすくなり、その後の暗記がとてもしやすくなります。
イラストやマインドマップの活用
年表には図やイラストを描いたり、メモを書いたりしましょう。
何があったのか、関係者(幕府側の為政者、諸藩、庶民、株仲間)の反応を可視化すると、覚えやすくなります。
また、マインドマップを作成することで人名や出来事の関連性を理解しやすくなります。
用語集の作成
江戸時代には独特の用語が多く登場します。
政治改革、文化、農業、外交など、「苦手」と感じる分野をまとめた用語集を作成し、定期的に復習することで定着させましょう。
複数の問題集で学習
江戸時代は期間が長いうえに幕府の統治方法と庶民の生活の乖離(かいり)が大きくなっていく時代でした。
1冊の問題集だけだと良く分からないまま丸暗記になりがちです。同じ範囲を別の問題集でも勉強してみると、異なる角度から同じ内容を復習できるので理解が進みます。
テスト対策に年表が役立つ理由
中学生の歴史のテストでは、単なる用語暗記では点数がとれない問題が増えています。たとえば:
- 「○○のあとに起きた出来事を選べ」
- 「○○と△△は同じ時期の出来事か?」
このような時系列や因果関係を問う問題に対応するには、「江戸時代の年表」を活用するのが効果的です。
なぜなら、年表を使えば:
- 出来事がいつ・どの順番で起きたかがひと目でわかる
- 幕府の政策や改革の流れが理解できる
- 文化や人物の活躍時期もあわせて覚えられる
つまり、年表をただ読むだけでも、テストに出やすい知識が自然に頭に入るのです。
暗記ではなく「流れ」で覚えるコツ
江戸時代を学ぶときに大事なのは、「丸暗記」ではなく「流れ」で覚えることです。以下のような方法で、「つながり」を意識して覚えると、ぐっと理解しやすくなります。
☑将軍ごとに覚える
→ たとえば、「徳川家康のときに関ヶ原の戦いがあった」「徳川吉宗の時代に享保の改革が行われた」など、誰の時代の出来事かで分けて覚えると整理しやすいです。
☑出来事の「原因」と「結果」を意識する
→ 「鎖国はなぜ始まったのか?→キリスト教や外国の影響を防ぐため」など、ストーリーのように理解すると記憶に残りやすくなります。
☑文化・改革・外交などテーマ別に分類する
→ 江戸時代には「元禄文化」「享保の改革」「ペリー来航」など多様なジャンルがあります。ジャンルごとにマーカーで色分けした年表を使うと、より効果的です。
以上のように、年表を活用して流れで学ぶことで、理解力も暗記力もアップし、定期テストや高校入試でも高得点を狙えるようになります!
江戸時代の分かりやすい年表
| 1603年 | 徳川家康が征夷大将軍に任命される(江戸幕府を開く) |
| 1613年 | 全国に禁教令を出す(キリスト教禁止) |
| 1615年 | ・大坂の陣で豊臣家滅亡 ・武家諸法度、禁中並公家諸法度が制定される |
| 1624年 | スペイン船の来航禁止 |
| 1635年 | 参勤交代の制定 |
| 1637-1638年 | 島原・天草一揆が起こる |
| 1639年 | ポルトガル船来航禁止(鎖国完成と言われる) |
| 1669年 | アイヌのシャクシャインと松島藩の間で戦いが起こる |
| 1687年 | 5代将軍・徳川綱吉が生類憐みの令を出す |
| 1709年 | 新井白石による正徳の治がはじまる |
| 1716年 | 徳川吉宗が8代将軍に就任、享保の改革がはじまる |
| 1767年 | 老中・田沼意次が政治の実権をにぎる |
| 1782年 | 天明の大飢饉が起こる |
| 1787年 | 老中・松平定信による寛政の改革がはじまる |
| 1792年 | ロシアのラクスマンが根室に来航、通商を求める |
| 1804年 | ロシアのレザノフが長崎に来航、通商を求める |
| 1825年 | 異国船打払令が出される |
| 1833年 | 天保の大飢饉が起こる |
| 1837年 | 大塩平八郎の乱が起こる |
| 1839年 | 蛮社の獄(高野長英、渡辺崋山らが投獄) |
| 1841年 | 老中・水野忠邦による天保の改革がはじまる |
| 1842年 | アヘン戦争で清がイギリスに敗れる |
| 1853年 | ペリーが浦賀に来航 |
| 1854年 | 日米和親条約をむすぶ |
| 1858年 | 日米修好通商条約をむすぶ |
| 1860年 | 桜田門外の変が起こる(大老・井伊直弼が暗殺される) |
| 1867年 | ・将軍・徳川慶喜が大政奉還をする ・王政復古の大号令が出される |
| 1868年 | 戊辰戦争で旧幕府勢力が敗れる |
江戸時代の出来事と重要ポイントの解説
前述の年表をもとに、重要ポイントをお伝えします。
歴史の流れを理解しやすくなるように、時系列で解説しています。
なお、内容は山川日本史探求教科書をもとにしています。
参考:山川出版社「日本史探求教科書」
1603年 – 江戸時代の始まり
- 徳川家康が江戸幕府を開く
- 安定した政権が確立され、江戸時代が始まる
1600年、徳川家康は関ヶ原の戦いに勝利して戦国時代の覇権者となり、天下を統一する道を切り開きます。
1603年には征夷大将軍に任命され、江戸に幕府を開きました。これが江戸時代の始まりです。ここから約260年間にわたる平和な時代である江戸時代がスタートします。
1615年 – 大坂の陣
- 徳川家康の息子、2代将軍・徳川秀忠の時代
- 大坂の陣で徳川家の統治が安定化
徳川家康が関ヶ原の戦いで勝利して江戸幕府を開くと、豊臣家の一族である大坂の豊臣秀頼やその支持者たちは、幕府の支配に不満を抱いていました。
大坂の陣は激しい戦闘となりましたが、最終的には徳川軍が勝利しました。
豊臣秀頼は自害し、豊臣家は滅亡します。これにより、徳川家康の勢力が一層強まりました。
1633年 – 鎖国政策
- 徳川家康の孫、3代将軍・徳川家光の時代
- 鎖国政策が導入され、外国との交流が制限される
江戸幕府が成立すると、政権の安定化が図られました。大名の統制のために武家諸法度がつくられ(2代目徳川秀忠のころ)、公家や朝廷の統制のために禁中並公家諸法度がつくられていました(初代徳川家康のころ)。
徳川家光のころには参勤交代を定めて国内の統治をさらに進め、外部からの影響を受けないようにするために鎖国政策が進められました。
対外交渉の制限
幕府は他国との外交交渉を厳しく制限し、外国人の来航を制限しました。
貿易も幕府が指定した場所や商人によるものに限られました。
- オランダ・中国:長崎の平戸→出島で交渉
- 朝鮮:対馬藩が窓口
- 琉球:薩摩藩が窓口
- アイヌ:松島藩が窓口
異国船の排除
外国船が日本の海域に入ることを防ぐため、異国船の接近を禁じました。これが「鎖国」の名前の由来の一つです。
鎖国政策の結果
鎖国政策により江戸時代は一定の平和な時期を迎え、国内の発展が進みました。同時に国際的な情勢から取り残される一因ともなりました。
鎖国政策は日本の歴史において独自の特徴を生み出し、江戸時代の社会や文化の発展に影響を与えました。
- 1634年 島原・天草の乱
- 1639年 ポルトガル船来航禁止(鎖国の完成)
1688年 – 1704年頃 – 元禄文化の隆盛
享保の時代には浮世絵や文学などが隆盛し、文化が栄えました。
元禄文化の特徴
元禄時代は、贅沢で豪奢な文化が隆盛した時期です。主に上方(大坂とその周辺)で栄えました。
商業の発展や都市の繁栄により、余暇や余裕のある階層が文化や芸術に優れた時間と資源を注ぎ込みました。
歌舞伎の隆盛
歌舞伎が興隆し、華やかな舞台芸術が人気を博しました。
俳優や舞台装置、衣装が派手で多彩なものとなりました。
浮世絵の発展
浮世絵が発展し、日常の風景や美しい女性の姿を描いたり、歌舞伎の役者を描いたりしました。
一般庶民にも手頃な価格で楽しめるようになりました。
都市文化の発展
商業の発展に伴い、都市での文化が隆盛。遊里(遊女がいた地域)や花魁(高級遊女)文化も栄えました。
元禄文化の文化人とその代表的な作品
| 有名な作家 | 井原西鶴 | 『好色一代男』 |
| 近松門左衛門 | 『曾根崎心中』 | |
| 有名な俳人 | 松尾芭蕉 | 『奥の細道』 |
| 有名な画家 | 菱川師宣 | 『見返り美人図』 |
| 尾形 光琳 | (『燕子花図屏風』など。中学生は覚えなくても大丈夫です。) | |
| 土佐光起 | (『春秋花鳥図屏風』など。中学生は覚えなくても大丈夫です。) |
1716年 – 1745年 – 享保の改革
- 将軍・徳川吉宗が改革を行う
- 幕府の財政安定や商業奨励などの改革が行われる
この頃から幕府財政は貧しくなっていきます。幕府の収入を増やす、民衆の生活を安定させるという課題に取り組む必要にせまられていました。
財政の改革
幕府の財政は困難な状況にありました。金庫のお金が毎年減っていました。
そこで享保の改革ではぜいたくな出費を減らし、節約策を進めました。
商業の奨励
幕府の収入を増やすため、商業を発展させて商人などからの税収入を増やそうとしました。
商業の発展を促進するために、特に大名や寺社などが商業に参入することを奨励しました。これにより、地域経済の活性化が期待されました。
物価の安定化
物価が上がったり下がったりすると庶民の生活が苦しくなります。そこで物価の乱高下を防いで価格の安定を図りました。
これにより、庶民の生活が安定することが期待されました。
享保の改革における政策の一覧
| 公事方御定書 | 裁判の基準を定めた |
| 目安箱の設置 | 庶民の意見を投書させた |
| 新田開発 | 田畑を増やして年貢収入を増やそうとした |
| 小石川養生所の設置 | 貧しい江戸の町民に無償で医療を提供する |
改革の結果
享保の改革は一定の成果を収めました。
幕府の財政がある程度安定し、商業の発展が促進されました。また、物価の安定化によって、社会全体の安定が図られました。
ただし、改革の過程で一部の大名や旧来の特権層が影響を受け、反発も見られました。
1750年 – 1787年 – 田沼の改革
- 老中・田沼意次が改革を行う
- 幕府の財政再建や商業奨励を目指すが、後に混乱を招く
将軍・徳川吉宗の享保の改革により一定の安定がもたらされましたが、その後も経済や社会の変化に対応する必要がありました。
この時、田沼意次が老中(幕府の最高実力者)として政権を握り、独自の政治改革を進めました。
貨幣改鋳で通貨の価値を安定化
当時の貨幣は価値が不安定でした。同じ100円玉で120円のものが買えたり、50円のものしか買えなかったりという状態です。
庶民は混乱していました。
田沼はこれを改善するために貨幣を新たに発行しなおし、経済の安定を図りました。
株仲間の奨励
幕府への税収入を増やすため、株仲間(商人の同業者組合)を奨励しました。株仲間の利益が増えれば幕府への税収入も増えるためです。
百姓一揆や打ちこわしが発生
株仲間の奨励や貨幣改鋳(かいちゅう)で商業は大いに発展しました。ところが株仲間や田沼とその配下など一部の特権階級だけがもうけていると批判も起こり、百姓一揆や打ちこわしも発生しました。
- 百姓一揆…農村での百姓による暴動
- 打ちこわし…町での町人による暴動
改革の結果
田沼の政治改革により貨幣の安定や商業の発展が進み、社会全体の安定が促進されました。
一方で、風説禁止令などにより言論の自由が制限され、一部で不満が広がることもありました。
田沼意次の政治改革は、江戸時代中期の社会の変化に対応する一環として行われ、その影響は当時の社会に大きな影響を与えました。
1787年 – 1793年 – 寛政の改革
- 老中・松平定信が改革を行う
- 武士の生活抑制や税制改革が行われる
江戸時代後期には経済や社会の変化が進み、天明の飢饉で農村が大打撃を受けたこともあり、幕府の統治方法が時代に合わなくなっていきました。
- 幕府が求める農村の在り方…米づくりをがんばってほしい
- 江戸時代後期の農村の状況…米より商品作物(売ってお金にできる農作物。藍など)をつくってお金もうけをしたい。それが無理なら、実家の生活は苦しいから江戸に出稼ぎに行きたい。
寛政の改革はこれらの課題に対処し、幕府の経済的な安定や農村の振興を図ることを目指しました。
倹約令の公布
老中・松平定信は出費を減らして生活を立てなおすため、豪華な着物を禁止するなどの倹約令を出しました。
幕府だけでなく藩や庶民にも倹約を求めました。
囲い米の実施
諸藩や農村に余剰分のお米を日ごろから蓄えさせ、飢饉が発生したときに食糧に困らないようにしようとしました。これを囲い米の制といいます。
天明の飢饉を教訓にした政策でした。
出稼ぎの制限と農村への帰農を奨励
飢饉の影響で田をたがやしているより町に出てほかの仕事をすることを選ぶ農民が数多くいました。
松平定信は町への出稼ぎに制限を設けるとともに、すでに農村から出てしまっている人たちに対しては少額の融資や農具の貸与などで帰農をうながしました。
改革の結果
寛政の改革によって一定の経済的な安定が図られ、庶民の生活が改善されました。
しかし、一方で改革の影響により一部の旧来の特権層が影響を受け、社会的な不満も生じました。特に将軍・徳川家斉は浪費癖がひどく、倹約を求める松平定信と折り合いが悪かったのでした。
結局、将軍に嫌われて辞任に追い込まれました。
1804年 – 1830年頃 – 化政文化の興隆
1700年前後に上方で栄えた元禄文化に対して、19世紀前半は江戸を中心とした化政文化が栄えました。
化政文化の特徴
化政時代は、元禄文化から一転して質素で倹約な文化が求められた時期です。
浪費家として有名な徳川家斉が将軍になり、幕府財政の立て直しを図ったことが影響しています。
たびたび改革が行われ、贅沢を戒め、倹約や節度を奨励しました。
芸事や文学も質素なものが重んじられました。
近代化の端緒
この時期には洋式の学問や技術が導入され、近代化への動きが見られました。
浮世絵の変化
浮世絵もテーマ性が変わり、風俗や美人画だけでなく風景や歴史ものなど多様なジャンルが登場しました。
化政文化の文化人とその代表的な作品
| 有名な作家 | 滝沢馬琴 | 『南総里見八犬伝』 |
| 山東京伝 | 黄表紙 | |
| 十返舎一九 | 『東海道中膝栗毛』 | |
| 有名な俳人 | 小林一茶 | 『おらが春』 |
| 有名な画家 | 東洲斎写楽 | 『富嶽三十六景』 |
| 喜多川歌麿 | 美人画で有名 | |
| 歌川広重 | 『東海道五十三次』 |
1830年 – 1844年 – 天保の改革
- 老中・水野忠邦が改革を行う
- 財政逼迫(ひっぱく)と外国の脅威に対抗するため幕府の収入を増やそうとして失敗
当時、飢饉がたびたび起こり、庶民の生活は苦しくなっていました。
大坂では元役人の大塩平八郎が乱を起こすなど、打ちこわしや一揆も頻発していました。
幕府への批判を封じる・幕府の収入を増やす・物価を抑制するという課題がありました。
厳しい倹約令の発令
寛政の改革同様に、水野忠邦も倹約令を出します。
豪華な着物やアクセサリーは禁止、歌舞伎のような娯楽もほぼ禁止にするなどしたため、庶民から猛烈に反発されました。
株仲間の解散
物価の上昇により庶民の生活は苦しくなっていました。その原因を株仲間と考えた水野忠邦は株仲間を解散しました。
人返しの法の実施
農村から江戸への出稼ぎ者が多かったことが、江戸の物価上昇と幕府の年貢減少につながっていると水野忠邦は考えました。
そこで、江戸への出稼ぎ者をできるだけ農村に帰らせる「人返しの法」を発令しました。
上知令で諸藩から猛反発
ロシアなど外国船がたびたび日本にやってきて開国を求めるようになっていました。
幕府の税収入を増やして軍備を増強しようとして上知令を発令しましたが諸藩から強い反対を受けました。
上知令…年貢の多い土地を諸藩から取り上げて、代わりに年貢の少ない土地を渡す命令
改革の結果
倹約令による庶民からの反発や、上知令への諸藩の強い反対によって水野忠邦は失脚し、改革は2年で終わりました。
19世紀半ば – 1868年 – 幕末の動乱と明治維新
- 黒船来航などをきっかけに、幕末の動乱が始まる
- 最終的に明治維新が実現し、江戸時代が終わる
江戸時代後期から外国船がたびたび日本近海に現れ、開国を求めるようになります。
幕府は鎖国政策を盾に開国要求を反対します。
アヘン戦争で清が敗れる
1840-1842年のアヘン戦争で清国(今の中国)が敗れます。
このことを知った幕府は衝撃を受け、外国の軍事力の強さを警戒するようになります。
1853年 – アメリカのペリー提督があらわれる
1853年、アメリカのペリー提督が4隻の軍艦(黒船)をひきつれて浦賀にあらわれます。港を開いて貿易をするように求めました。
結論を聞くために1年後にまた日本にやってくると約束していったん立ち去ります。
1854年 – ペリー提督再来日し、日米和親条約がむすばれる
翌年(1854年)、ペリー提督は約束どおりあらわれます。
日本は港を開いて貿易をすることを決め、日米和親条約をむすびます。
これにより、下田と函館の開港が決まりました。
1858年 -日米修好通商条約がむすばれる
1854年の日米和親条約につづいて、1858年には日米修好通商条約がむすばれます。
これにより、函館・新潟・神奈川・兵庫・長崎の5港を開港することになりました。
物価が急上昇し、庶民の不満が高まる
外国との条約は日本側に不利な内容でした。
金や生活物資が不足し、国内の物価は大いに上昇して庶民の不満が急激にたかまりました。
1867年 – 将軍・徳川慶喜が大政奉還をする
次々と外国の言いなりになってしまう幕府の姿勢をみて、諸藩は勢いづきます。
なかでも長州藩と薩摩藩が同盟して幕府を倒そうとしました(薩長同盟)。
この動きをみて将軍・徳川慶喜は大政奉還を決意します。
大政奉還…朝廷に政権を返すこと。徳川家は「政権担当者」から「イチ大名」になることで、薩摩や長州の攻撃を避けようとした。
1868年 – 戊辰戦争
旧幕府側の勢力と明治政府との間に戦争が起こります。
最終的に北海道の五稜郭で明治政府側の勝利が確定しました。
※関連記事:中学定期テスト必勝!明治時代の年表をマスターする5つのステップと明治時代のテスト頻出ポイント
定期テスト・高校入試に出る江戸時代の人物ベスト14
江戸時代は長く続いたため、登場する人物も多く、誰を覚えればよいのか迷ってしまうことがありますよね。
しかし、定期テストや高校入試でよく出る人物は、ある程度決まっています。
ここでは、中学生が覚えておくべき江戸時代の重要人物ベスト14を、ジャンルごとに分けてわかりやすく紹介します。
これをおさえておけば、テスト対策もバッチリです!
覚えておくべき有名な将軍たち

江戸時代は「江戸幕府」が約260年もの間、日本を治めた時代です。将軍の政治や判断が、その時代の出来事と深く関わっています。
まずはテストに必ずと言っていいほど出てくる有名な将軍4人を見ていきましょう。
徳川家康(とくがわ いえやす)
江戸幕府を開いた初代将軍。1600年の関ヶ原の戦いで勝利し、1603年に征夷大将軍となりました。
→【覚え方ポイント】「江戸幕府スタート=家康」
→【よく出る問題】関ヶ原の戦いや幕藩体制、武家諸法度との関係
徳川秀忠(とくがわ ひでただ)
家康の子で2代将軍。あまり目立ちませんが、江戸幕府の基礎固めを行った人物として重要です。
→【出題例】将軍の代替わりと体制の整備
徳川吉宗(とくがわ よしむね)
8代将軍で、「享保の改革」を行いました。質素倹約や目安箱の設置など、さまざまな改革を行い、幕府を立て直そうとしました。
→【覚え方ポイント】「改革=吉宗」
→【出題頻出】享保の改革の内容、目安箱や公事方御定書
徳川慶喜(とくがわ よしのぶ)
最後の将軍。大政奉還(1867年)を行い、政権を朝廷に返しました。
→【覚え方ポイント】「江戸幕府の終わり=慶喜」
→【出題例】幕府の終わりと明治維新への流れ
政治改革や事件に関わった人物
江戸時代には、幕府を立て直すための改革が何度か行われました。
これらの改革を行った人物たちは、テストに非常によく出題されます。以下の4人は特に重要です。
新井白石(あらい はくせき)
6代将軍・家宣のもとで政治を行い、「正徳の治(しょうとくのち)」と呼ばれる改革を実施。
→【キーワード】金銀の海外流出を防ぐ、質素倹約
→【ポイント】外国貿易の制限や通貨の安定を図った
田沼意次(たぬま おきつぐ)
10代将軍・家治の時代に商業を重視する政策を行った人物。
→【キーワード】株仲間、公認商業、わいろの問題も
→【よく出る問題】商業の発展と矛盾、政治の腐敗
松平定信(まつだいら さだのぶ)
11代将軍・家斉の時代に「寛政の改革」を実施。
→【キーワード】倹約令、朱子学の奨励、囲い米
→【ポイント】厳しい政策で一時的に財政安定を図るが、庶民には不評だった
水野忠邦(みずの ただくに)
12代将軍・家慶の時代に「天保の改革」を実施。
→【キーワード】株仲間の解散、人返し令、上知令
→【出題例】改革の失敗とその原因
文化で名を残した人物
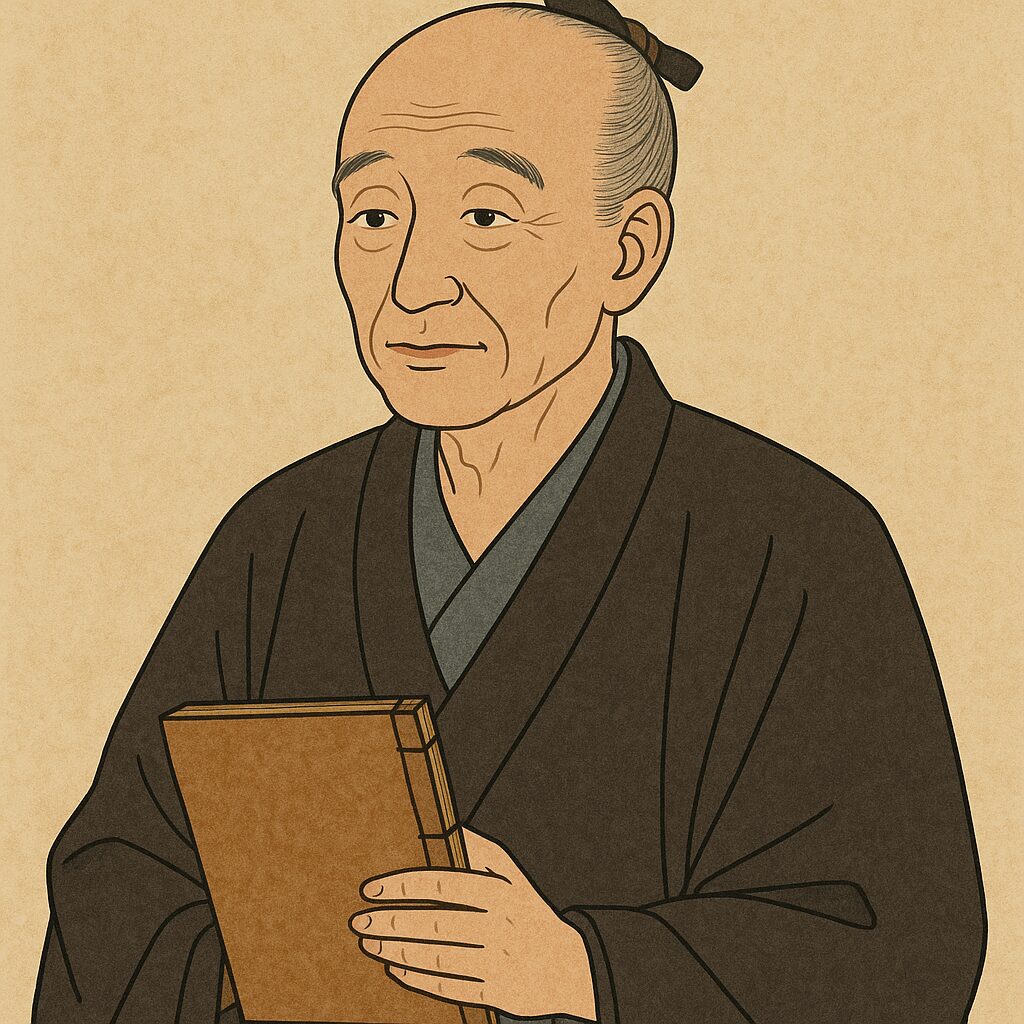
江戸時代は、政治だけでなく文化の発展も特徴的です。特に中期にあたる元禄時代には、町人文化が花開き、多くの芸術家・文人が活躍しました。
元禄文化(げんろくぶんか)
元禄時代(1688〜1704年)に栄えた町人中心の文化で、以下の人物が特に有名です。
- 井原西鶴(いはら さいかく):町人の生活を描いた小説『好色一代男』などを執筆
- 近松門左衛門(ちかまつ もんざえもん):人形浄瑠璃や歌舞伎の脚本家として『曽根崎心中』などを生む
- 松尾芭蕉(まつお ばしょう):俳諧を芸術の域に高めた俳人。代表作『奥の細道』はテスト頻出!
→【ポイント】元禄文化は「町人が活躍した文化」と覚えよう
→【よく出る問題】人物と作品、文化の特徴の組み合わせ問題
化政文化(かせいぶんか)
化政文化は、江戸時代後期(1804年〜30年代ごろ)に栄えた文化です。
名前は、文化(ぶんか)・文政(ぶんせい)という年号からきています。江戸を中心とした町人文化がさらに発展したのが特徴です。
この時代もテストによく出る有名な文化人が多くいます。作品名と人物名のセットで覚えることがポイントです。
- 十返舎一九(じっぺんしゃ いっく)
→ 代表作:『東海道中膝栗毛(とうかいどうちゅう ひざくりげ)』
→ 内容:弥次さん喜多さんの珍道中を描いた滑稽な読み物(今でいうコメディ小説) - 滝沢馬琴(たきざわ ばきん)
→ 代表作:『南総里見八犬伝(なんそうさとみはっけんでん)』
→ ポイント:長編小説の名作。勧善懲悪のストーリーが人気。 - 葛飾北斎(かつしか ほくさい)・歌川広重(うたがわ ひろしげ)
→ ジャンル:浮世絵(風景画)
→ 北斎の代表作:『富嶽三十六景(ふがくさんじゅうろっけい)』
→ 広重の代表作:『東海道五十三次(とうかいどうごじゅうさんつぎ)』
→【覚え方ポイント】化政文化は「町人文化の完成形」「読み物と浮世絵」がキーワード。
→【よく出る問題】
- 作品名と作者の組み合わせ問題
- 元禄文化と化政文化の違い(中心地、文化の特徴など)
以上が、江戸時代のテスト頻出人物ベスト14解説です。
この10人の役割・時代背景・関係する出来事を「流れで理解」すれば、暗記ではなく得点できる歴史学習ができます!
江戸時代によく出る定期テスト・入試問題の傾向と対策
江戸時代の範囲では、記述問題・並び替え問題・一問一答など、さまざまな形式の問題が出題されます。ここでは、出題されやすいテーマとその対策をわかりやすく解説します。
記述問題に出やすいテーマ例
鎖国の目的と結果を説明する問題
「鎖国(さこく)」は、江戸時代の中でもテストに頻出のテーマです。
記述問題では「なぜ鎖国をしたのか」「どんな影響があったのか」を説明させる出題がよくあります。
☑ポイント
- 目的:キリスト教の禁止、幕府の支配を強めるため
- 結果:貿易が制限され、平和な時代が続いたが、海外の情報が入りにくくなった
☑記述例:
「キリスト教の広まりを防ぎ、幕府の支配を安定させるために鎖国を行い、貿易は長崎の出島など一部に限られた。」
江戸時代の改革を比較させる問題
「享保の改革・寛政の改革・天保の改革」は、内容を比較して違いを説明する問題が多く出題されます。
☑ポイント
- 共通点:幕府の財政立て直しを目指した
- 違い:
- 享保(徳川吉宗)→目安箱・公事方御定書など
- 寛政(松平定信)→倹約令・朱子学重視
- 天保(水野忠邦)→株仲間の解散・上知令(未実施)
☑記述例:
「3つの改革はいずれも財政再建を目指したが、実施内容や背景に違いがある。」
年代整序問題・一問一答の対策法
並び替え問題を解くコツ
年表問題でよく出るのが「出来事の順番を並び替える問題」です。
☑対策のコツ
- まずはざっくり年代で区切る(17世紀・18世紀など)
- 将軍や改革と出来事をセットで覚える(例:徳川吉宗=享保の改革)
☑並び替え例:
- 島原の乱(1637年)
- 享保の改革(1716年〜)
- 天保の改革(1841年〜)
重要用語を覚える語呂合わせ
語句暗記が苦手な人には「語呂合わせ」が効果的です。江戸時代でよく使われる語呂を紹介します。
- 鎖国の完成:1639年(いろさく 鎖国)
- 徳川吉宗の改革:1716年(いないイロイロ吉宗)
- 島原の乱:1637年(いろみな 島原)
☑覚えるのが苦手な人は、オリジナルの語呂を作るのも◎!
江戸時代の年表で流れをつかむ練習問題(無料プリント付き)
江戸時代の年表を使って、「流れをつかむ力」を養える無料練習問題を用意しました。
一問一答形式で知識をチェック!
短時間で解ける一問一答形式の問題で、重要語句を確認しましょう。定期テスト前の総チェックにぴったりです。
📌 例題
Q1. 江戸幕府を開いた人物は?
Q2. 享保の改革を行った将軍は?
Q3. 鎖国体制のもとで、唯一貿易が許されたヨーロッパの国は?
※答え:Q1. 徳川家康、Q2. 徳川吉宗、Q3. オランダ
記述練習で得点アップを目指そう
入試や応用問題では記述がカギ。下記のような問題で、思考力を鍛えよう。
📝 練習問題:
「幕府が鎖国政策を取った理由と、その影響について説明しなさい。」
→ テンプレートに自分の言葉を当てはめて書く練習が効果的!
プリントPDFダウンロードはこちら
定期テストや入試対策にすぐ使える、江戸時代年表付きプリントをPDFでご用意しました。
自宅学習や塾教材としても活用可能です。
- 年表まとめプリント(A4サイズ)
- 一問一答プリント(解答付き)
- 記述対策問題集(模範解答付き)
歴史の流れを学べる本・参考書
最期に、歴史の流れを勉強しやすい本や参考書を3冊紹介します。
『中学社会 スーパー歴史年表』
問題集に答えを書き込みながら年表を仕上げていくスタイルです。
自分で書いていくので頭に残りやすいです。
出版社:文英堂
『中学 マンガとゴロで100%丸暗記 歴史年代』
年号を語呂合わせで覚えられる参考書です。
年号を覚えるのが苦手な中学生に人気です。
出版社:増進堂・受験研究社
『中学社会 歴史年表書きこみノート』
こちらも年表に書き込みながら覚える方式です。
秀逸なのが、イラストや資料をふんだんに掲載してくれている点です。
「文字だけだと覚えづらい!」という人も視覚的に覚えられます。
出版社:学研プラス
まとめ
中学生向けに江戸時代の年表や出来事を紹介し、年表を使った勉強法を紹介しました。
年表の理解は中学生の歴史学習において不可欠です。
年表の作成やイラストの活用、用語集の作成、そして複数の問題集による学習で効果的に江戸時代の年表をマスターし、定期テストで高得点を獲得しましょう!
定期テストに向けてもっと勉強したい人向けに、下記の記事で一問一答問題をたくさん解けます。


コメント