共働き家庭で中学受験をするケースは増えてきています。
「中学受験は親の受験」とも言われますが、親が2人とも働いていると子どもの勉強をみる時間がどうしても限られてしまいます。
そんな状況にストレスを感じている親御さんは多いのではないでしょうか。
そこで、共働き家庭が中学受験をするときにかかえる課題と、その課題に対処して中学受験を乗り切る方法を紹介します。
子どもに責任感を持たせるようにすると勉強に対して前向きに取り組みやすくなり、結果的に志望校合格にも近づけます。
※なお、家庭でできる中学受験準備の始め方について、以下の記事でくわしく解説しています。
中学受験準備:いつから始める?どういう子が中学受験で有利になる?
※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。
Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法
共働き家庭の中学受験、なぜ大変なのか?
中学受験は「子どもだけの戦い」ではなく、「親子で取り組むプロジェクト」と言われるほど、家庭の関与が大きい教育イベントです。
現在、共働き家庭で中学受験を選択するところは増えています。厚生労働省の国民生活基礎調査によれば、4分の3以上が共働きの家庭であり、中学受験率も20%となっています。
共働き家庭にとっては、限られた時間とエネルギーの中で、このプロジェクトを遂行しなければならず、さまざまな困難に直面します。
受験に必要な親の関与度は意外と高い
中学受験においては、親のサポートが受験の成否を左右すると言っても過言ではありません。主な関与内容には以下のようなものがあります:
- 塾の送り迎え・お弁当の準備
- 宿題や学習の進捗管理、ミスのチェック
- 志望校の情報収集と受験スケジュールの組み立て
- 模試の振り返りと学習計画の調整
- 精神面での支え(不安やプレッシャーのケア)
共働きでフルタイム勤務の場合、こうした日常的な関与をこなす余裕が物理的に足りないことが多く、結果として子どもが孤立したり、親が無理をして疲弊することにつながります。
家庭学習のサポート時間が取れないという現実
共働き家庭では、平日の夜に子どもの学習をじっくり見てあげる時間が限られています。以下のようなシーンが頻繁に起こります:
- 子どもが塾から帰る時間には親が帰宅していない
- 宿題の確認や質問対応が翌日に持ち越される
- 朝は出勤準備で忙しく、学習サポートができない
また、塾から出される大量の宿題や、家庭学習での復習など、日々の積み重ねが合否を分ける中学受験において、こうした「空白時間」が子どもの学習遅れに直結するリスクもあります。
※なお、社会の思考力の伸ばし方について、以下の記事で詳しく解説しています。
共働き家庭でもできる!中学受験「社会」で思考力を伸ばす親子の学び方とは?
塾や学校との連絡・管理に手が回らない
中学受験を控えた子どもには、塾の授業・模試・面談・学校のイベントなど、さまざまな予定や連絡事項が日々飛び交います。特に共働き家庭にとっては、これらの管理が大きな負担になります:
- 塾の連絡事項を見落とす
- 学校との面談日程が合わない
- 模試の申し込み・送迎・結果確認が後手になる
このような「連絡ミス」や「情報の行き違い」が、子ども本人の準備不足や不安感にもつながることがあり、保護者の情報管理能力や調整力が常に試されるのが共働きの難しさです。
精神的・経済的な負担も二重で重い
中学受験には、塾代や模試代、教材費など年間で100万円を超える支出が一般的です。共働きだからこそ経済的にはカバーできる面もありますが、その分精神的な負担が大きくなることも忘れてはなりません。
- 「働いているから十分にサポートできないのでは?」という罪悪感
- 夫婦間での役割分担・温度差によるストレス
- 子どもの不調や不安に対してすぐに対応できないもどかしさ
また、「子どもが失敗したら自分たちのせいだ」とプレッシャーを感じる親も少なくありません。つまり、時間・お金・感情のすべてが消耗する状態に陥りやすいのが、共働き家庭の中学受験なのです。
まとめ:共働き家庭ならではの「見えにくい負担」が存在する
中学受験における共働き家庭の大変さは、時間的・精神的・経済的な負担が複雑に絡み合う点にあります。ただし、これらの困難は工夫次第で乗り越えることも可能です。
それでも共働き家庭が中学受験に挑む理由
共働きという忙しいライフスタイルの中で、なぜあえて中学受験というハードルの高い選択をするのか? その背景には、子どもの将来を見据えた明確な目的意識や、「教育に妥協したくない」という家庭の理念があります。
将来の選択肢を広げるという価値
共働き家庭の多くは、子どもの将来において「選べる自由」を与えたいという強い思いを持っています。中学受験を通じて私立中学校や国立中等教育学校などに進学することで、以下のようなメリットが得られます:
- 進学先の多様性(大学附属校、先進的な教育方針の学校など)
- 海外大学進学や探究学習への対応
- 英語・ICT・探究など21世紀型スキルの早期習得
将来の進路を自分で選べる環境を整えるために、早い段階で教育環境の質を高めておくことは重要であり、それが中学受験を選ぶ理由のひとつです。
教育における「質」の重要性
公立中学校は地域によって教育レベルや校風に差がありますが、中学受験を経て進学する私立・国立校は、教育の「質」が比較的安定しているというメリットがあります。
- 少人数制や習熟度別授業によるきめ細やかな学習指導
- 落ち着いた学習環境と高い進学実績
- 教員の質やカリキュラムの独自性(探究活動・留学制度・キャリア教育など)
また、大学受験を見据えた「先取り学習」や、個性を伸ばす教育を重視する学校も多く、教育への投資効果が高いと判断する家庭も増えています。
共働き家庭は時間的に子どもの教育を家庭内で細かくサポートするのが難しいため、学校教育そのものに高いクオリティを求める傾向があるのです。
中高一貫校のメリット(学力・環境・人脈)
中学受験を経て入学する「中高一貫校」には、以下のような大きなメリットがあり、これが共働き家庭にとって強い動機になります:
学力面のメリット
- 高校受験がないことで6年間を計画的かつ一貫したカリキュラムで学べる
- 中3〜高2にあたる時期に大学受験の対策を前倒しできる
- 難関大学への合格実績が高い学校が多い
環境面のメリット
- 落ち着いた校風で学習意欲が高い生徒が多い
- 教員の進路指導力・生徒サポート力が強い
- 長期間を同じ仲間と過ごすことで人間関係の安定が得られる
人脈・ネットワークのメリット
- 卒業後も続く「同窓ネットワーク」や社会的なつながりが形成されやすい
- 保護者の間でも価値観の近い人が多く、情報共有や協力がしやすい
特に共働き家庭にとっては、学校の教育力・環境が安定していることが、子どもの精神的安定や学習面のサポートに大きく影響するため、このような中高一貫校の存在は非常に魅力的です。
まとめ:中学受験は「共働きだからこそ」選ぶ価値もある
中学受験は確かに大きな負担を伴いますが、将来の自由な進路選択、質の高い教育、そして中高一貫校がもたらす安定した学習環境という点で、共働き家庭だからこそ「教育の質」に早い段階から投資する意義があるのです。
共働き家庭が中学受験を乗り越えるための5つの工夫

時間的・精神的・経済的な制約がある共働き家庭にとって、中学受験はハードルの高い挑戦です。しかし、多くの家庭が工夫と戦略でこの壁を乗り越えています。
ここでは、実際に成果を上げた家庭に共通する5つのポイントを紹介します。
①スケジュール管理の徹底(デジタル活用も)
忙しい共働き家庭にとって、スケジュール管理の効率化は受験成功の基盤です。
家族全員でGoogleカレンダー管理
家族のスケジュールを「見える化」するために、GoogleカレンダーやTimeTreeなどの共有ツールを導入する家庭が増えています。
- 父・母・子それぞれの予定を色分け管理
- スマホ通知で忘れ防止
- お互いの空き時間を確認しやすい
これにより、突然の塾の変更連絡や面談予定にも即対応できるようになります。
試験日や模試日、塾の予定も見える化
- 模試・学校説明会・入試説明会の情報は即カレンダーへ
- 塾からの配布プリントは写真に撮って保存し、リンクで共有
- 家族が「いつ何があるのか」を把握することで、役割分担や送迎調整がスムーズに
②子どもの自立心を育てる教育スタイル
共働き家庭では、子ども自身が勉強を進める力=自走力が重要になります。
「自走型学習」を促す声かけと仕組み
- 「何時から何をやるか?」を自分で決める習慣を持たせる
- 学習後は親と簡単な振り返り時間を5分持つ
- 「できたことを認める」「次の課題を考える」など、親は伴走者に徹する
ルールを家族で決めて習慣化
- 「夜9時以降はスマホ禁止」「夕食後は1時間だけ勉強」など、家族全体でルールを共有
- 曖昧な禁止ではなく、「一緒に決めたこと」として守ることで、自主性と責任感を育てる
③信頼できる塾・家庭教師の選び方
「預けて安心できる教育機関」との連携は、共働き家庭にとって非常に重要です。
家庭との連携が密な塾の特徴
- 定期的な保護者面談や連絡帳機能がある
- 学習状況や子どもの様子をメール・アプリで報告
- 質問対応時間や自習スペースが充実しており、家庭での補完が少なくて済む
共働き家庭向けサポートが手厚い塾とは
- 送迎バスあり/オンライン授業対応可
- 欠席フォロー体制が整っている(映像授業・振替)
- LINE連絡やオンライン面談など、柔軟な対応が可能
※個別指導や家庭教師も検討対象になるが、「講師の継続性」「コミュニケーション力」も選定ポイント。
塾と家庭教師の併用方法について、以下の記事でくわしく解説しています。
中学受験は塾と家庭教師の併用で合格率アップ!併用のコツと成功事例を徹底解説
※なお、中学受験塾の選び方について、以下の記事でくわしく解説しています。
共働き家庭の中学受験塾選びのポイント
④外注の活用(家事代行・学習サポート)
「全部自分たちでやろうとしない」ことが、中学受験成功のためには重要です。
お金で時間を買うという選択肢
- 家事代行(週1回の掃除や作り置き)
- 買い物代行やネットスーパーの活用
- タクシー送迎アプリや時短家電(乾燥機付き洗濯機など)
これらは決して贅沢ではなく、受験期の限られた時間を最大限に活かす投資です。
教育費とのバランスのとり方
- 家事代行やタクシー送迎は、季節講習や受験直前期だけスポット利用する方法も有効
- 「毎月使う金額」を可視化し、家計とのバランスを定期的に見直す
- 支出に優先順位をつけて、「削るべきでない教育費」と「外注すべき家事負担」を整理する
⑤夫婦での役割分担と定期的な振り返り
家庭内での連携がうまくいっているほど、子どもも安心して受験に集中できます。
パートナーシップが成功の鍵
- 「送迎は夫」「プリント管理は妻」など、具体的な役割を事前に分担
- 不満が溜まらないように、定期的なタスク見直しミーティングを設定
- 親が協力し合う姿は、子どもに安心感と信頼感を与える
面談・模試後に夫婦で共有する習慣
- 模試結果や成績表は、「夫婦で一緒に見て話し合う」時間を必ず作る
- 担任や塾講師からのアドバイスも、LINEやメモで共有
- 「次はどうするか?」を話し合うことで、方針のぶれを防ぐ
まとめ:忙しくても、中学受験は「戦略」と「チーム力」で乗り越えられる
共働きだから無理…とあきらめる必要はありません。スケジュール管理・教育方針・外部リソース・夫婦の連携といった点をしっかり設計することで、共働き家庭でも十分に中学受験を乗り越えられます。
共働き家庭ならではの強みとは?
「忙しいから中学受験は難しい」と思われがちな共働き家庭ですが、実は“共働きだからこそ伸ばせる力”も数多くあります。以下にその代表的な3つの強みを解説します。
親が働く姿を見せることが教育になる
共働き家庭では、子どもが親の努力や社会での役割を日常的に目にすることができます。
- 親が「仕事を頑張る姿」は、子どもにとって目標に向かって努力する大人のロールモデル。
- 「お母さん(お父さん)も頑張ってるから、僕(私)も頑張る」と、自然に努力する価値を理解できる。
- 「働く=社会に貢献する」という姿勢が、将来のキャリア観にも良い影響を与えます。
このように、仕事を通じた背中の教育は、勉強への向き合い方にも良い影響を与えることがあります。
限られた時間で集中する「時間管理力」
共働き家庭の子どもは、時間の大切さを早い段階から実感し、効率的に行動する力を身につけやすい傾向があります。
- 「親が帰ってくるまでに宿題を終わらせよう」
- 「塾に行く前にご飯・着替え・準備を自分で済ませる」
このような生活の中で、自然と以下のような力が育ちます。
- スケジュール感覚(段取り力)
- 集中力(限られた時間で成果を出す)
- 自己管理力(優先順位をつける力)
なお、週末は家族で軽くお出かけをすると、良いリフレッシュになります。軽い運動はストレス解消になり、イライラや倦怠感を解消して気持ちを安定させやすくなります(運動がメンタルヘルスに与える影響)。
リフレッシュされた状態で学習することができれば、子どもの勉強への集中力もアップします。
多様な価値観・社会性を自然に学べる
共働き家庭では、親が社会と関わることで、子どももさまざまな人間関係や考え方に触れる機会が多くなります。
- 父母がそれぞれ別の仕事・職場で異なる人間関係を築いている
- 家族内の会話でも「会社」「お客様」「上司・部下」などの社会的視点が交わる
こうした環境の中で、子どもは自然と次のような力を養っていきます。
- 柔軟な思考力
- 他者の立場を想像する力
- 自己表現と協調性のバランス
多様な価値観に触れながら育つことは、中学受験後のグループ活動やディスカッション型の授業でも大いに役立ちます。
体験談:共働きで中学受験を成功させた家庭のリアルな声
実際に共働き家庭で中学受験を乗り越えたご家庭の声から、成功の裏にあった工夫や葛藤を紹介します。現実的な視点と再現性のあるヒントが詰まっています。
成功した家庭の1日のスケジュール例
以下は、小6の受験生を持つ共働き家庭の平日のタイムスケジュールの一例です。
| 時間帯 | 内容 |
|---|---|
| 6:30〜7:30 | 起床、朝食、学校の準備、朝学習(15分の計算や漢字練習) |
| 8:00〜15:30 | 学校(給食あり) |
| 16:00〜16:30 | 家で軽食後、塾(直行) |
| 17:00〜21:30 | 塾の授業あるいは宿題(自習) |
| 22:00〜22:30 | 夕食(親が用意できない日は作り置きや惣菜活用) |
| 22:30~23:00 | 宿題、家庭学習(親と少しだけ解き直し確認) |
| 23:00 | 就寝(家族全員での振り返り会話は毎日5分) |
※ポイント:
- 送迎の工夫:祖父母の手を一部借りた
- 学習は短時間集中:長時間ダラダラより、集中30分×2回
- カレンダー共有:Googleカレンダーを親子で見て行動
小5~小6で最もつらかった時期とその乗り越え方
特に小6夏休み〜秋は“親子ともに疲労がピーク”になりやすい時期です。
つらかったこと:
- 親:「仕事も繁忙期、でも子どもに付き合う時間も必要で寝不足」
- 子:「模試の成績が伸び悩み、やる気が下がる」「友達と遊べず孤独感」
乗り越え方:
- 「がんばったことシート」を冷蔵庫に貼って親子で1日1つ褒め合う
- 週1回だけ「勉強しない日」を作って、外食や映画でリフレッシュ
- 学校の担任や塾に「悩み」をこまめに共有し、孤立しない仕組みを作った
→ 最後まで走り切れた理由は、「勉強の話ばかりにしない工夫」と「親が子どもの感情に寄り添う姿勢」でした。
合格後の家族の変化・振り返って思うこと
合格はゴールではなく「家族としての達成感と、新たな出発点」だと語る家庭が多くあります。
家族の変化:
- 親子関係がより「チーム」のようになった
- 子どもが「自分で考えて行動する」習慣がついた
- 親も「人に頼ること、外注することは悪くない」と価値観が変わった
振り返っての感想:
- 「仕事を続けながらでもできたことで、親として自信がついた」
- 「大変だったけれど、家族の絆は確実に深まった」
- 「子どもが『僕も社会で役立つ人になりたい』と言ってくれて感動した」
【現役塾講師が解説】共働き家庭の中学受験アドバイス
共働き家庭にとって中学受験は、「時間」と「情報」の戦いとも言えます。現場で日々親子と接する塾講師の立場から、限られたリソースの中で成果を最大化する3つのポイントをお伝えします。
「付き添い型」ではなく「伴走型」でサポートを
共働き家庭の場合、子どもに常時付き添うのは難しいのが現実です。そこで大切なのが、「つきっきりで教える親」ではなく、「困った時に伴走する親」を目指すこと。
- わからない問題は一緒に悩む姿勢で(すぐに答えを教えない)
- 日々の取り組みを“聞く・ほめる・共感する”時間を意識的に作る
- 「●時までに終わらせてね」という時間管理の声かけも効果的
このようなスタンスが、子どもの自立と安心感の両方を支えます。
「勉強量」よりも「継続の仕組み」がカギ
中学受験では「毎日3時間勉強」が理想かもしれませんが、共働き家庭ではその“量”にばかりこだわると親子ともに疲弊します。
- ポイントは「短くても毎日やる仕組み」を作ること
→ 例:朝15分、夜20分の“固定スロット制” - 親がいない時間でも実行できる学習習慣を育てることが重要
- 続けやすい方法:ToDoリスト、タイマー学習、チェック表など
“頑張れる日”より“やめない仕組み”が合格を支えます。
「塾との連携」は“お任せ”ではなく“チーム戦”
現役講師から見ると、塾と家庭の連携がうまくいっているご家庭ほど伸びやすいです。共働きだからこそ、受け身ではなく戦略的に塾を活用することが成功のポイント。
- 面談は必ず夫婦どちらかが参加し、子どもを第三者の視点で見る機会に
- 塾に「家庭の状況・支援できる範囲」を伝えておくとアドバイスが的確に
- 学習の優先順位を塾とすり合わせて、やるべきことを絞る勇気も必要
「家庭・子ども・塾」が同じ方向を向くことで、無理なく前に進める体制が整います。
まとめ:共働き家庭でも中学受験は実現可能!必要なのは「戦略」と「協力」
共働き家庭にとって中学受験は決して楽な道ではありませんが、「限られた時間とエネルギーをどう使うか」という戦略と、家族や塾、外部サービスとの協力体制が整えば、十分に実現可能です。
- スケジュール管理や役割分担で効率的に動く
- 子どもの自立心を育てて親の負担を減らす
- 信頼できる塾やサポートを見極める目を持つ
これらを意識すれば、共働きでも無理なく中学受験を乗り越えられます。大切なのは「一人で抱え込まず、チームで進む」ことです。
※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。
Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法
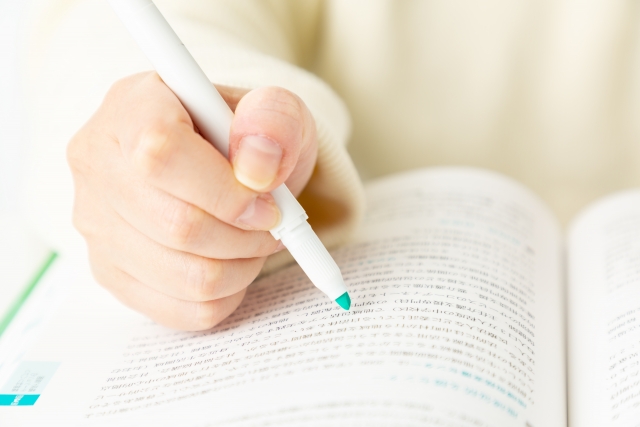


コメント