中学受験生やその保護者の方の悩みのたねの1つが、国語の長文読解ではないでしょうか。
「模試のたびに偏差値がエスカレーターになる…」
「算数は偏差値60近く取れるのに、国語は40台…」
国語は配点が大きいですから、苦手なままだと入試が不安になりますよね。
国語が伸びない原因は読解力だと思っている方、多いです。
実は国語が苦手な原因の多くは、読解力がないからではないんです。
読解問題の解き方を教わっていないだけなんです。
そこで今回は、国語の偏差値を短期間で伸ばすための勉強方法を3つ紹介します。
国語が足を引っ張って、泣く泣く志望校を変更しないといけない…なんてことになる前に、早めに対策しておきましょう!
※関連記事:【中学受験】理科を得意にできる勉強方法
※関連記事:【中学受験】社会を得意にできる勉強方法
【下記バナーは難関中学受験対策で定番のZ会のPRです。記述特訓など、特訓系の講座だけ受けることも可能です。】
※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。
Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法
中学受験国語が苦手な子の特徴5つ
国語の点数が伸びない子には共通してみられる特徴があります。
- 漢字や熟語を覚えていない
- 書き抜き問題が苦手
- 記述問題の答え方を間違っている
- テストで時間が足りず、いつも最後まで解けない
- 国語をセンスで解こうとしている
それぞれ説明します。
漢字や熟語を覚えていない
先述のように国語が苦手な子に多いのが、漢字や熟語といった知識の軽視です。漢字を読めないとそれだけで長文を読みづらくなります。
また漢字・熟語は中学受験では珍しい、「知っていれば解ける問題」です。
「暗記教科」と言われる理科や社会も、丸暗記ではあまり点数にならないのに対して、国語の漢字は丸暗記で点数になります。
※関連記事:中学入試によく出る漢字・熟語・慣用句・ことわざの問題
ここを押さえておかないのは本当にもったいないです。
書き抜き問題が苦手
受験国語の書き抜き問題は、実はボーナス問題です。
国語が得意な子はほとんど100発100中で正解しており、「書き抜きは確実に得点できる問題」だと思ってます。
ところが、国語が苦手な子は書き抜き問題の解き方を知らず、1つ解くのに非常に時間をかけてしまっています。
記述問題の答え方を間違っている
記述問題は「~こと」「~から」など、終わり方が決まっています。
決められた終わり方以外だと、解答内容が正しくても減点されます。これも、偏差値が伸びない大きな原因になっています。
テストで時間が足りず、いつも最後まで解けない
国語が苦手な子がそろって口にするのが、
「時間が足りなかった」
です。
どの教科でも時間が潤沢にあるわけではありませんが、とりわけ国語は苦手な子ほど時間が足りなくなる傾向が強いです。
原因は「長文を何度も読んでいるから」です。
もちろん、長文を読むのは大事です。1度は全文に目をとおしておくほうがいいです。
ですが、下記のようなことをしていると、時間がどんどん足りなくなってしまいます。
- 長文と設問を何度も往復している
- 長文の同じ箇所を何度も読み返している
理想的な説き方は、本文を1度読んだら後は設問をサラっと解いて終わり、です。
国語をセンスで解こうとしている
国語が苦手な子に1番多くみられる特徴がこれです。
国語をセンスで解こうとしています。
プロの小説家のような素晴らしい文章を書くにはセンスも必要でしょう。(小説家は膨大な量の練習をされているので、センスだけで文章を書かれているわけではありませんが。)
ですが、ただ問題を解いて正解・不正解を決めるだけなら、センスはなくても問題ありません。
ちゃんとした読み方・解き方があります。それを身につければ国語の偏差値を押し上げられます。
中学受験国語の偏差値をあげる方法
国語は2か月もあれば偏差値をあげられます。そのヒントが前項でお伝えした
「国語が苦手な子の特徴」
です。
これらの特徴のうち、以下の2つの条件を満たす特徴をつぶします。
- 知っていれば正解できる
- すぐに解決できる
前述の5つの特徴を、この条件に合うかどうかで表に分類しなおしました。
| 漢字や熟語 | 書き抜き問題 の解き方 | 記述問題 の答え方 | テストで 時間切れ | 読み方・ 解き方 | |
| 知っていれば正解できる | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ |
| すぐに解決できる | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |
◎がその条件にとても当てはまるもので、
〇はまあまあ当てはまるものです。
短期間で偏差値をあげるには、
「知っていれば正解できる」「すぐに解決できる」の両方で◎がついているものを克服しましょう。
- 書き抜き問題の解き方
- 記述問題の答え方
の2つです。
国語の偏差値をすぐに5ポイントあげる方法
前述のように、
「書き抜き問題の解き方」「記述問題の答え方」の2つがわかれば、すぐにでも偏差値があがります。
多少の個人差はありますが、偏差値5ポイントは上がります。
書き抜き問題の解き方を覚える
まず、書き抜き問題の解き方から解説します。
書き抜き問題はふつう、本文中のある言葉を別の言葉で言いかえているか、説明している言葉を書き抜く問題です。
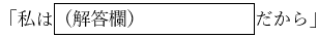
の□内に入る言葉を探します。
解答条件として、下記のような字数制限がされています。
- 〇文字で書き抜きなさい
- 〇文字以内/程度で書き抜きなさい
この解答条件はそのまま「解答のヒント」になります。
上記の例でいうと、下記の3つの条件をすべて満たす言葉でないといけません。
- 「私は」からはじまる
- 「~だから」につながる
- 10文字でひとまとまりの意味になっている
これらの条件すべてに該当する言葉は非常に少ないです。本文全体でせいぜい3つくらいでしょう。
その3つを1つずつ解答欄に入れてみて、「私は~だから」で話がつながればそれが答えです。
まず問題文の字数を確認し、当てはまる箇所を探し、解答欄に入れてみる。これで正解を1問拾えます。
記述問題の答え方を覚える
記述問題は文末の書き方が間違っていると減点されます。
文末の書き方には以下の3種類あります。3つとも覚えておきましょう。
- 「どういうことか説明しなさい。」
→ 「~ということ」で終わる - 「どういう意味か説明しなさい。」
→ 「~という意味」 - 「理由を説明しなさい。」
→ 「~(だ)から/~ため」で終わる
解答内容を正しく書けるようになるには2か月かかりますが、文末の書き方だけなら明日からでも修正できます。
国語のテストがある人は、そのテストから修正しておきましょう。
2か月で国語の偏差値15上げる勉強方法
つづいて、2か月後に偏差値を15上げる勉強方法をお伝えします。
前述の5つの特徴のうち、下記の2つの対策です。
- テストで時間切れ
- 読み方・解き方
この2つを克服すれば国語の偏差値を大きく上げられます。
2つとも勉強方法は同じです。
読解問題を解説から読む
読解問題を解くときは、まず解説から読みましょう。
国語の勉強というと、ほとんどの子はいきなり問題にとりかかります。勉強の順番を逆にします。
下記の順番に演習しましょう。
- 本文の解説を読む
- 本文のポイントを頭に入れる
- 本文を読んで問題を解く
本文のポイントをある程度把握した状態で長文を読みます。
解説の内容をイメージしながら読めるので、論旨の展開の仕方や物語文の表現方法を確認しながら読めます。
国語は、ほかの教科と同じく解法を身につけて解く教科です。本文のテーマが変わっても書き方は同じです。
どういう書き方をしていれば(論旨の展開をしていれば)、次にどのような内容が来るかを予想して読めるようになります。
予想どおりの内容がくれば問題はスラスラ解けますし、予想と違っていても「どこがどう違うのか」を把握しながら読み進めます。
何度も本文を読み返して時間をロスすることもなくなります。
「何が書かれているのか」「どうしてその答えになるのか」
がわかっている状態で問題を解けばすらすらと解けます。
そのために、読解問題はまず解説を読むところからはじめます。
同じ問題を3回以上解く
1題解けるようになっても、これで終わりではありません。
同じ読解問題を3回以上は解きましょう。できれば5回解くほうがいいです。
算数や理科・社会なら、同じ範囲の問題を繰り返し解きますよね。かけ算の問題も何十回・何百回と解いたはずです。
理科の電流も社会の鎌倉時代も、宿題やテスト勉強などで3~5回は解いているはずです。
- 1回目:解き方を知る
- 2回目:解き方の確認
- 3回目:ようやく解き方の定着スタート
国語の読解問題も同じものを3~5回解いて、「こういう読み方をする」「こういう解き方をする」と定着させましょう。
読解で頻出の4テーマに慣れる
まったく同じ文章は二度と出てこないでしょうが、似たような文章や同じテーマの文章は何回も出てきます。
国語の読解は、下記の4テーマがよく出てきます。
- 友情
- 親子
- 自然(環境)
- 科学
読み方・解き方を身につけていけば、テーマごとのポイントや論旨の展開の仕方が身に付きます。
何回も解いて、読み方・解き方を定着させるようにしましょう。
希学園の子で、1か月で偏差値が20以上上がった子もいました。これはさすがにレアケースですが、2か月で10以上は上がります。
前述の「書き抜き問題」「記述問題の答え方」で5ポイントあがりますから、
この2つの勉強方法で偏差値15は上がります。
漢字や熟語を継続的に覚える
ここまで紹介した2つの勉強法と並行して進めてほしいのが、「漢字・熟語の暗記」です。
5年生終わりまでには全部覚えられるペースで勉強しましょう。
いずれも出題は「学年別漢字配当表」という文部科学省の学習指導要領で定められた範囲からです。
これは小学校で習う1,026字の漢字からなっており、小学校の内容を超えたむずかしい漢字は出ません。
ただし、問題にはならなくても本文中に小学校で習う以上の漢字が出てくることがあります。
その場合、漢字にルビはふってくれていますが、ルビがないと読めない小学生は不利になります。
その語彙の意味を知らないでしょうから、本文の内容もずいぶん読み取りづらくなるからです。
いくら読み方・解き方を身につけても、「書いてある内容がよくわからない」と大まかなところまでしか理解できません。
5年生の途中まではそれでもなんとかなりますが、6年生ではさすがに太刀打ちできません。
漢字・熟語のインプットが進むと、「長文の読み方・解き方」も精度が上がっていきます。
偏差値がさらに上昇して、最終的に60くらいまではいきます。
下記の漢字ドリルが定番です。AmazonのPRリンクをつけているので、リンク先で購入いただけます。

中学入試 でる順過去問 漢字 合格への2610問 四訂版 (中学入試でる順)

出る順「中学受験」漢字1580が7時間で覚えられる問題集 [さかもと式]見るだけ暗記法
ほとんどの受験生は偏差値60あれば十分でしょうが、
60以上にするには記述力をかなりきたえるようにしましょう。
※関連記事:【中学受験】国語の記述勉強法・記述力アップの問題集
通信教育を試してみる
塾に通ってみて上手くいかなければ、通信教育を試してみるのも一つの手です。
移動時間がゼロですし、塾に比べて短時間の1回あたりの勉強が短時間に設計されています。「塾と併用」「通信教育単独」のどちらも選べます。
難関中学対策ならZ会
難関中学、最難関中学(首都圏御三家、灘中学、ラサール中学など)を目指しているならZ会がおすすめです。下記のような特長があります。
- トータル受講、ライトな受講(要点集中プラン)を選べる
- 1科目から受講できる
- 塾と同じかそれ以上の難易度の問題にもチャレンジできる
- 1万字以上の超長文の読解対策や記述特訓など入試頻出分野の対策講座を取れる
※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法
苦手、嫌いを克服するなら進研ゼミ
中学受験対策の通信教育として進研ゼミも多くの受験生に選ばれています。楽しく、自信をつけながら学べるという特徴があります。
- 視覚的に理解しやすい授業動画
- 1回15分の設計で勉強がつづけやすい
- 赤ペン先生がほめながら添削してくれる
- 合格実績は4,000名以上
※関連記事:進研ゼミ小学講座の特徴と効果的な利用法
中学受験国語の長文読解のコツ
つづいて国語の長文読解のコツを簡潔にお伝えします。
詳細は以下の記事で紹介しています。
※関連記事:中学受験国語の読解テクニック:塾や家庭教師が個別指導で教えている方法
論理的文章は対比させて読む
中学入試の論理的文章は大抵、対比を用いた文章が選ばれます。
あるテーマについて「筆者の主張」と「筆者の主張への反対意見」が表現され、それぞれの根拠も説明されています。
読み進めながら、段落ごとに「筆者の主張」「筆者の主張への反対意見」に分けるとかなり読みやすくなります。
文学的文章は事実と心情を時系列で追う
文学的文章は事実と登場人物の心情をそれぞれ時系列で追いながら(本文中に線を引きながら)読みましょう。
何らかの事実/事件が発生し、
それに対して登場人物が感情を抱きます。
その感情が原因となって人物が何らかの行動を取ります。
例えば下記のような具合です。
事実:友人が主人公との約束を破った
↓
感情:主人公が憤慨した
↓
行動:学校で友人に会っても主人公は目を合わさないようにした
文学的文章で問われるのは大抵、上記の「行動の理由」です。
「なぜ主人公は学校で友人に会っても主人公は目を合わさないようにしたのでしょうか?」のように問われます。
解答部分にあたるのが「事実」と「感情」です。
事実と心情を時系列で追うと行動の理由が分かりやすくなり、設問にも正答しやすくなります。
選択問題は消去法で解く
選択問題を苦手にしている人は多いですが、正しい選択肢を選ぼうとすると逆にむずかしくなります。
選択問題は消去法で解きましょう。
明らかに本文内容と違う選択肢を最初に消します。
つづいて、各選択肢の文言や内容が本文と合っているか比較し、「合っていない選択肢」を消していきます。
残った選択肢が正解の選択肢です。
まとめ
いかがでしょうか。
中学受験の国語を苦手にしている子は多いですが、読解が苦手なのではありません。
解き方や国語の勉強の仕方を知らなかったことが大きな原因です。
記事内で紹介した勉強方法はいずれも家庭学習で取り組めるものです。
国語を得意教科にして、得点源にしたいですね!
※関連記事:【中学受験】国語の読解力を訓練するためのオススメのドリル・問題集10選
【下記バナーは難関中学受験対策で定番のZ会のPRです。記述特訓など、特訓系の講座だけ受けることも可能です。】
※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。
Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法
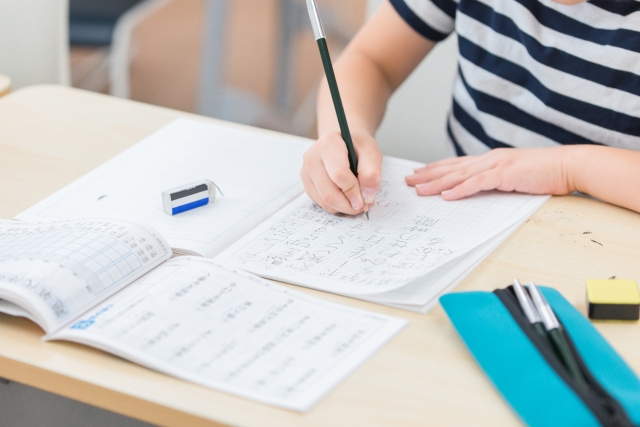


コメント