中学入試の国語で出題される漢字・慣用句・ことわざを問題形式にまとめました。
知識系の覚えもれをなくして、1点でも多く点数を取り切れるようにがんばりましょう!
最後に漢字の覚え方やおすすめのドリルも紹介しています。
※関連記事:【中学入試】面接でよく聞かれる質問例と模範解答例
Z会の通信教育 中学受験コース※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。
Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法

中学入試によく出る漢字の問題
漢字の書きの問題
問い. 次のカタカナを漢字に直しなさい。(1)ガイトウの明かりが道を照らす。
(2)外国とユウコウな関係を築く。
(3)楽器がきれいな音色をカナでる。
(4)銀行にヨキンする。
(5)今朝は昨日よりアタタかい陽気だ。
(6)野球の試合がハクネツしている。
(7)友人とのカンダンを楽しむ。
(8)鏡にウツる自分の姿に驚く。
(9)委員長としてのツトめを果たそう。
(10)彼女はイシの強い人だ。
(11)A国とB国は長年、ケンアクな関係だ。
(12)彼は大きなシュッパン社で仕事をしている。
(13)物事のゼヒを彼女に問いただそう。
(14)世界ジョウセイは予断を許さなくなっている。
(15)多くのりんごがシュッカされている。
(16)カイドウ沿いにあるレストランで昼食を取る。
(17)彼は身のケッパクを主張している。
(18)子どものスコやかな成長を祝う。
(19)災害で食料のキョウキュウが止まっている。
(20)警察官の説得で犯人は人質をカイホウした。
(21)ダンゾク的に雨が降る。
(22)エベレストのトウチョウに成功する。
(23)練習にミが入らない。
(24)大体のケントウをつけて道を進む。
(25)大きな責任をオう。
(26)風邪がナオった。
(27)水面に朝日がウツる。
(28)鳥のシュウセイを研究する。
(29)カクシン的な研究成果を発表する。
(30)石けんが顔にツいた。
(31)この辺りはシオの流れが速い。
(32)会議がナゴやかな雰囲気で進行する。
(33)ユカタを着て花火を見に行く。
(34)冬のナゴリを残す庭。
(35)判決にイギを唱える。
解答
(1)街灯
(2)友好
(3)奏
(4)預金
(5)暖
(6)白熱
(7)歓談
(8)映
(9)務
(10)意志
(11)険悪
(12)出版
(13)是非
(14)情勢
(15)出荷
(16)街道
(17)潔白
(18)健
(19)供給
(20)解放
(21)断続
(22)登頂
(23)身
(24)見当
(25)負
(26)治
(27)映
(28)習性
(29)革新
(30)付
(31)潮
(32)和
(33)浴衣
(34)名残
(35)異議
漢字の読みの問題
問い. 次の漢字の読みがなを書きなさい。(1)歩合
(2)体面
(3)元来
(4)口調
(5)強情
(6)矢面
(7)為替
(8)重宝
(9)雪崩
(10)八百屋
(11)声色
(12)納豆
(13)雨具
(14)彼岸
(15)都合
(16)湯気
(17)性分
(18)雑木林
(19)屋外
(20)作物
(21)競売
(22)迷子
(23)田舎
(24)故郷
(25)素人
(26)帰省
(27)画一
(28)安否
(29)潔い
(30)形相
(31)本望
(32)気配
(33)示唆
(34)天然
(35)養生
解答
(1)ぶあい
(2)たいめん
(3)がんらい
(4)くちょう
(5)ごうじょう
(6)やおもて
(7)かわせ
(8)ちょうほう
(9)なだれ
(10)やおや
(11)こわいろ
(12)なっとう
(13)あまぐ
(14)ひがん
(15)つごう
(16)ゆげ
(17)しょうぶん
(18)ぞうきばやし
(19)おくがい
(20)さくもつ
(21)けいばい
(22)まいご
(23)いなか
(24)こきょう
(25)しろうと
(26)きせい
(27)かくいつ
(28)あんぴ
(29)いさぎよ(い)
(30)ぎょうそう
(31)ほんもう
(32)けはい
(33)しさ
(34)てんねん
(35)ようじょう
対義語の問題
問い. 次の熟語の対義語を漢字で書きなさい。(1)違反
(2)親切
(3)自立
(4)成功
(5)清流
(6)単一
(7)永遠
(8)遺失
(9)需要
(10)特別
(11)有名
(12)落第
(13)勤勉
(14)原因
(15)権利
(16)記憶
(17)起点
(18)共同
(19)給水
(20)濃縮
解答
(1)順守
(2)冷淡
(3)依存
(4)粗雑
(5)濁流
(6)複合
(7)一瞬
(8)拾得
(9)供給
(10)普通
(11)無名
(12)及第
(13)怠惰
(14)結果
(15)義務
(16)忘却
(17)終点
(18)単独
(19)排水
(20)希釈
同義語の問題
問い. 次の熟語の同義語を漢字で書きなさい。(1)貧乏
(2)未然
(3)推量
(4)有名
(5)決心
(6)節約
(7)成分
(8)落胆
(9)応用
(10)消息
(11)欠点
(12)改良
(13)突然
(14)永久
(15)方法
(16)寛大
(17)立身
(18)意外
(19)委細
(20)達成
解答
(1)貧困
(2)事前
(3)推測
(4)著名
(5)決意
(6)倹約
(7)要素
(8)失望
(9)利用
(10)音信
(11)短所
(12)改善
(13)不意
(14)永遠
(15)手段
(16)寛容
(17)出世
(18)案外
(19)詳細
(20)成就
四字熟語の問題
問(1)次の意味になる四字熟語を書きなさい。(1)多くの人が同じことや同じ意見を言うこと。
(2)人や国が自分たちに必要な物資を自分たちだけで生産してまかなうこと。
(3)たえまなく、常に進歩していること。
(4)もってのほかであること。
(5)大人物は若い頃は目立たないが、徐々に実力をつけて後に大成すること。
(6)前置きをせずに用件や本題にすぐに入ること。
(7)自分に都合のいいように物事を持っていくこと
(8)これまで1度もなく、これからも起こらないと思われること。
(9)非常に関心があり、次々と興味がわいてくること。
(10)公正で少しも私心がないこと。
(11)油断すると物事に失敗してしまうので、十分に気を付けること。
(12)田園で世間のわずらわしさから離れ、心穏やかに暮らすこと。
(13)大体同じで、細かい部分だけ違っていること。
(14)人の意見や批評が気にならないこと。
(15)老いも若きも、男性も女性も、あらゆる人々。
問(2)次の に入る漢数字を一字入れて、ことばを完成させなさい。(16) 寒 温
(17) 日 秋
(18) 人 色
(19) 転び 起き
(20) 苦 苦
解答
(1)異口同音
(2)自給自足
(3)日進月歩
(4)言語道断
(5)大器晩成
(6)単刀直入
(7)我田引水
(8)空前絶後
(9)興味津々
(10)公明正大
(11)油断大敵
(12)晴耕雨読
(13)大同小異
(14)馬耳東風
(15)老若男女
(16)三寒四温
(17)一日千秋
(18)十人十色
(19)七転び八起き
(20)四苦八苦
中学入試によく出る慣用句・ことわざの問題
問(1) 次の慣用句・ことわざの意味を書きなさい。(1)色を失う
(2)はかりにかける
(3)漁夫の利
(4)一目置く
(5)目をかける
(6)紺屋の白ばかま
(7)百聞は一見に如かず
(8)実を結ぶ
(9)歯が立たない
(10)論より証拠
(11)火中の栗を拾う
(12)猫をかぶる
(13)良薬は口に苦し
(14)顔が売れる
(15)ぬかに釘
(16)能ある鷹はつめを隠す
(17)肩をすくめる
(18)どんぐりの背比べ
(19)寝耳に水
(20)キジも鳴かずば撃たれまい
問(2)次の意味になるように□に入る言葉を入れて、慣用句・ことわざを完成させなさい。(21)弱り目に、□目:災難が起こっているときにさらに災難が降りかかってくること
(22)□も筆の誤り:どんなに名人であっても失敗することはあるということ
(23)歯に□着せぬ:思ったことを遠慮せずずけずけ言うこと
(24) □を傾ける:相手の話をじっと聞くこと
(25) □に水:ほんの少しの助けでは意味がないこと
解答
(1)驚いたり恐れたりして、どうしていいかわからなくなること。
(2)物事の利害を比べること。
(3)両者が争っている間に第三者が利益を得ること。
(4)相手が自分よりも優れていると認めて、相手に遠慮すること。
(5)ひいきにすること。
(6)他人のことに忙しくて自分のことに手が回らないこと。
(7)何度も聞くより実際に自分で見るほうがよくわかること。
(8)努力した分の成果が出ること。
(9)自分の力ではどうにもできないこと。
(10)あれこれ論じるよりも証拠を示せば物事は明らかになるということ。
(11)他人の利益のために、あえて困難なことに手を出すこと。
(12)本性を隠しておとなしそうなふりをすること。
(13)良い忠告は聞くのがつらいが、身のためになること。
(14)広く世間に知られて有名になること。
(15)手ごたえや効き目が全くないこと。
(16)本当に能力のある人は、自慢したりひけらかしたりしないこと。
(17)相手に対して「あきれ」や「どうしようもない気持ち」を表現すること。
(18)みんな平凡で、特に目立って優れているものがないこと。
(19)思いがけないことが起こったり、思いがけない知らせを聞いたりして驚くこと。
(20)無用なことを言ったばかりに災難にあうこと。
(21)たたり
(22)弘法
(23)衣
(24)耳
(25)焼け石
中学入試で漢字・慣用句・ことわざが大切な理由
中学入試の国語では、漢字・慣用句・ことわざの暗記が非常に重要です。その理由を3つお伝えします。
確実に点を取れる
国語の配点の多くは長文問題です。中学によって配点バランスはことなりますが、8割が長文です。
ですが、2割前後は漢字や慣用句のような「暗記すれば取れる問題」です。全問正解すれば、国語の試験を100点満点で20点からスタートできるようなものです。
受験勉強次第で確実に点数につながる問題ですから、しっかり得点につなげておきたいですね。
長文読解の言い換え問題で点を取れる
配点の多くを占める長文読解でも、漢字・慣用句などの知識が得点につながります。
長文読解では、本文のある表現を別の言い方に置きかえたものを探す問題が頻出です。
例えば本文中に「目くじらを立てる」(怒る)という表現が出てきて、同じ意味で別の言葉を選択肢から選んだり本文中から探したりする問題です。
その語彙や漢字を知らないと本文内容から意味を推測せざるを得ないため、ハイレベルな読解力が必要です。ですが、知っていればほとんどボーナス問題のようなものです。
※関連記事:おすすめの国語辞典
長文読解や記述問題に強くなる
中学入試で問われる漢字や慣用句・ことわざは小学校で習う範囲にほぼ限定されます。
ところが、長文中に出てくる漢字や語彙は小学生レベルを大きく超えたものも少なくありません。
難しい語彙には語注がつきますが、その語彙を知っている人と知らない人とで理解の深さに大きな差が出ます。
知っている人は「良い/悪い」「うれしい/悲しい」といった微妙なニュアンスまで読み取ることができますが、知らない人はそこまで読み取れません。
入試問題ですから、知っている人と知らない人で差をつけるために、そうした難しい漢字や語彙が関係する内容を問題に出してきます。
- ちょっとしたニュアンスの違いを問う問題
- 筆者が言いたいことを別の言葉で表現する問題
などが読解や記述問題で頻出です。
ほかの受験生よりも漢字や語彙を豊富にたくわえておくことが、長文読解での差にもつながっていきます。
※関連記事:【中学受験】国語辞典を使う習慣をつくって語彙力・読解力を伸ばす方法
※関連記事:文章力・記述力をトレーニングするおすすめのドリル・問題集
漢字・慣用句・ことわざの覚え方
受験勉強は量が多くて忙しいですから、漢字・慣用句・ことわざはできるだけ短時間で成果を出したいところです。
そこで、効率のいい覚え方を3つ紹介します。
漢字は成り立ちから覚える
まず、漢字は成り立ちから覚えましょう。
漢字には「へん」「つくり」「かんむり」「あし」「かまえ」「たれ」「にょう」の7種類の部首があり、それぞれ意味があります。
例えば「きへん」なら木に関係していますし、また「おうがい(頁)」なら「人間の頭部」を表しているので「顔」「頭」に使われます。
中学受験に必要な熟語は5000語以上と言われていますから、1つ1つバラバラに覚えるより成り立ちの種類ごとに覚えるほうが頭に入りやすく、残りやすいです。
「書き」と「読み」の両方で覚える
漢字の問題は「書き」と「読み」にわかれています。
どちらもややこしい書き方(「裕」と「祐」など)、ややこしい読み方の漢字(「和らぐ」「和む」など))が出題されます。
「大体覚えている」という程度だと、いざというときに正しく思い出せません。
読み→書きで覚えても、読み→書きはささっと済ませてしまう人もいますが、きっちり覚えておくために、書き→読み、読み→書きの両方で覚えるようにしましょう。
慣用句・ことわざは意味⇔語彙の両方で覚える
慣用句・ことわざは意味→語彙、語彙→意味の両方で覚えましょう。
問題パターンは大きくわけて下記の2種類です。
- 意味から語彙を答える問題
- 語彙の意味を選ぶ問題
どちらのパターンで聞かれても大丈夫なように、両方のパターンで演習を重ねておきましょう。
中学受験用の漢字・慣用句・ことわざの問題集
国語の知識系のドリルを2種類紹介します。
『中学入試 でる順 漢字/ことわざ・語句・文法』
漢字はコチラ↓

中学入試 でる順過去問 漢字 合格への2610問 四訂版 (中学入試でる順)
ことわざ・語句・文法はコチラ↓

中学入試 でる順過去問 ことわざ・語句・文法 合格への1204問 四訂版 (中学入試でる順)
慣用句はコチラ↓

中学入試でる順ポケでる国語 慣用句・ことわざ 四訂版 (POKEDERU series 2)
出版社:旺文社
特徴:
近年の中学入試を徹底的に分析し、頻出度の高い問題を「でる順」に掲載しました。
旺文社より引用
1つの単元は基本的には「まとめのページ」→「スピードチェック」→「入試問題にチャレンジ!」の3ステップで構成されているので、無理なく着実に合格への力をつけることができます。
巻頭には国語の入試傾向とその対策がわかる分析記事が、巻末には入試直前に総確認ができる「直前チェック編」がついています。
『出る順「中学受験」漢字1580が7時間で覚えられる問題集』

出る順「中学受験」漢字1580が7時間で覚えられる問題集 [さかもと式]見るだけ暗記法
出版社:大和出版
特徴:
見るだけでOK!
Amazonより引用
直近の約10年間に全国の中学入試で出題された漢字・語彙問題を出る順にA~Cにランク分けし、「書き取り」「四字熟語」「同音・同訓異字」などカテゴリーごとに出題。
この1冊で、中学入試対策はバッチリ!
中学受験国語の勉強を効率良くする方法
1人で勉強していると、下記のようなことがあります。
- 思うように成績があがらない
- 解説を読んでもいまいち理解できない
- 1つ1つの解説は理解できるが、問題を解くときに知識をうまく使えない
こういうときの対策方法を3つお伝えします。
通信教育を試してみる
中学受験国語の長文読解は「読み方」「解き方」の両方で実力とテクニックを求められます。しかも難関中学になるほど、長文の文字数は長くなり、記述問題が増えます。
難関中学入試対応に強い通信教育は「超長文対策」や「記述対策」に強く、中堅中学の入試に強い通信教育は小学生の「つまずきやすい箇所」や「ライバルに差をつけやすい問題」にしっかり対応しています。
それぞれの強みを活かした通信教育だけで受験される方や、塾と併用されている方がとても多いです。
難関中学対策ならZ会
難関中学、最難関中学(首都圏御三家、灘中学、ラサール中学など)を目指しているならZ会がおすすめです。塾と併用される方やZ会だけで中学受験をされる方も多いです。
下記のような特長があります。
- トータル受講、ライトな受講(要点集中プラン)を選べる
- 1科目から受講できる
- 塾と同じかそれ以上の難易度の問題にもチャレンジできる
- 記述特訓や理科の複雑な計算対策など入試頻出分野の対策講座を取れる
※関連記事:Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法
Z会の通信教育 中学受験コース苦手、嫌いを克服するなら進研ゼミ
中学受験対策の通信教育として進研ゼミも多くの受験生に選ばれています。楽しく、自信をつけながら学べるという特徴があります。
- 視覚的に理解しやすい授業動画
- 1回15分の設計で勉強がつづけやすい
- 赤ペン先生がほめながら添削してくれる
- 合格実績は4,000名以上
※関連記事:進研ゼミ小学講座の特徴と効果的な利用法
先取り学習を楽しくするならRISU
算数の先取りをするのに便利な学習道具としてRISU算数という、「算数に特化したタブレット型の通信教育サービス」があります。
ゲームのようにステージをクリアすればするほど算数の問題を解けるようにしていくシステムです。
小学校の勉強先取りはもちろん中学受験の問題もたくさんあり、RISUの会員で四谷大塚の全国小学生学力テストやSAPIXの模試で全国1位を取っている子も出ています。
費用のシステムが分かりにくいので、その解説も含めて下記の記事で紹介しています。
オンライン家庭教師を活用する
- 塾に通うほどではない
- 通える範囲内に良い塾がない
- わからないところだけピンポイントに対策したい
- プロ講師に教わりたい
こういうときは、家庭教師が便利です。特に受験直前期に家庭教師を活用する方が多くなります。
また、最近ではオンライン家庭教師の優位性がかなり際立ってきています。
普段は塾や予備校で教えている指導者がプロ家庭教師として活躍しています。オンラインなので、移動圏外に住んでいる人がちょっと空いた時間に授業をしています。
トップクラスの実績を持つプロ講師に教われば、1人であれこれ工夫するより5倍10倍早く、的確にポイントを押さえた学習ができます。
特に社会はプロと学生で指導力に大きな差が表れる科目です。「暗記科目」だと思うと興味がわきにくいかもしれませんが、プロが教えると興味を持つようになって楽しく勉強できるようになることがよくあります。
ほかの科目の勉強方法・問題
ほかの科目の勉強方法や問題を下記の記事で案内しています。ぜひ、ご覧ください。
【算数】割合の解き方
中学入試によく出る割合の問題
比の解き方
中学入試によく出る比の問題
速さの解き方
中学入試によく出る速さの問題
平面図形・空間図形の解き方
【国語】【中学受験】国語の勉強法と入試出題傾向を解説
【中学受験】国語長文読解を短期間で伸ばす勉強法
記述問題の書き方と勉強方法
おすすめの記述・作文問題集
【理科】【中学受験】理科を得意にできる勉強方法
【中学受験】理科のおすすめ問題集
中学入試の理科によく出る問題の一問一答
中学入試理科でよく出る問題の語呂合わせ一覧
中学受験の理科でよく出る記述問題
中学入試の理科でよく出る計算問題の公式一覧とおすすめの計算問題集
【社会】【中学受験】社会で貯金を20点つくる勉強法を紹介
中学入試の社会によく出る問題の一問一答
【中学入試】社会によく出る年号・年代の語呂合わせ
中学入試の社会でよく出る記述問題
【中学受験】社会のおすすめ問題集
※Z会の中学受験コースのメリットや活用法を下記の記事で紹介しています。
Z会中学受験コースだけで難関中学に合格する方法
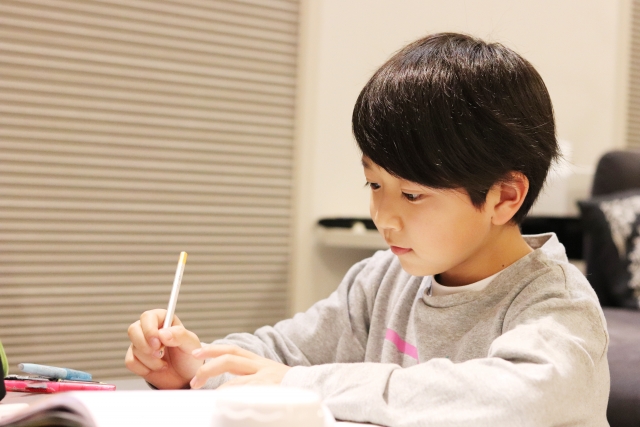


コメント